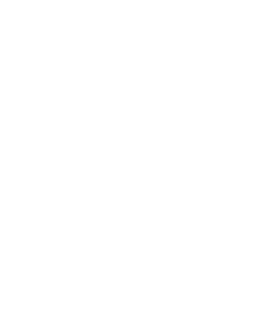2019/12/19
ローカルおじさんが語るプロデュース論<前編>
 日野昌暢
日野昌暢

博報堂ケトルのプロデューサーである、日野昌暢の日々を綴る連載「プロデューサー道」の第2回です。
「プロデューサー道」なんて大げさな連載タイトルにしちゃったんですけど、もう一つの連載名案は「日野昌暢のローカルおじさんが行く!」でした。自分のプロデューススキルを、衰退が続く日本の地域活性化に繋げたい!という想いを強く持つ僕としては、むしろそっちの方がしっくり来ていたのですが、話題の領域を広く持っていたいとも思って「プロデューサー道」にしました。でも、僕は「そうです、私が、ローカルおじさんです」なわけで。ローカルの地域活性とプロデュースは、切っても切り離せないと思っているし、とある後輩が飲み会で名付けた「ハイパーローカルプロデューサー」(笑)になりたいと思っているんですね。でも、ところで、そもそもプロデュースってなんなのよ?
広告会社にはプロデューサーの肩書きを持っている人は意外にも多くはないんです。ケトルのディレクターたちが面白い仕事を次々に生み出すのは、企画力やアイデアもさることながら、様々なスキルを持つプレイヤーやクライアントさんの思惑を踏まえて、統合的に考え、ちゃんと成立するように、ちゃんとうまくいくように取り計らう“プロデュース力”が高いからだと感じています。CMも、グラフィックも、プロモーションも、PRも、商品開発も、統合的にプラニングしながら、ちゃんと実現できるプロデュース力の高いディレクターたちが揃っているのが博報堂ケトルなんです。でも肩書きは「クリエイティブディレクター」。
博報堂だと、「営業職」と呼ばれる人たち(博報堂では2019年から営業局をビジネスデザイン局と呼ぶようになりました)がプロジェクトをプロデュースしていることが多い。博報堂で最も人数が多い職種は営業職ですが、広告業界の強い営業職の人っていうのは結局“プロデュース力”が強い。でも、彼らも肩書きはプロデューサーじゃないんですね。つまり、プロデュース力の高い人たちはたくさんいるけど、肩書きはプロデューサーじゃない人が多いのが広告会社なんです。いろんな思惑やスキルを持つ人たちの真ん中に入っていって、関係者ごとに異なる思惑や欲望、モチベーションも気にかけながら、時間や予算の実現性も計算して、プロジェクトが思った以上のものに仕上がるプロセスに有効な働きかけをするのがプロデュース。
このプロデュース力というものが、日本中でさまざまな挑戦が行われている”地域活性”にすごく役に立つんじゃないかと思っているんです。それがどういうことなのか!?第三回でお話できればと思います!それではまた!
(下写真:広島県の宮島の絶景カフェで、違いがわかる男風に瀬戸内海を眺めてみました)


「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






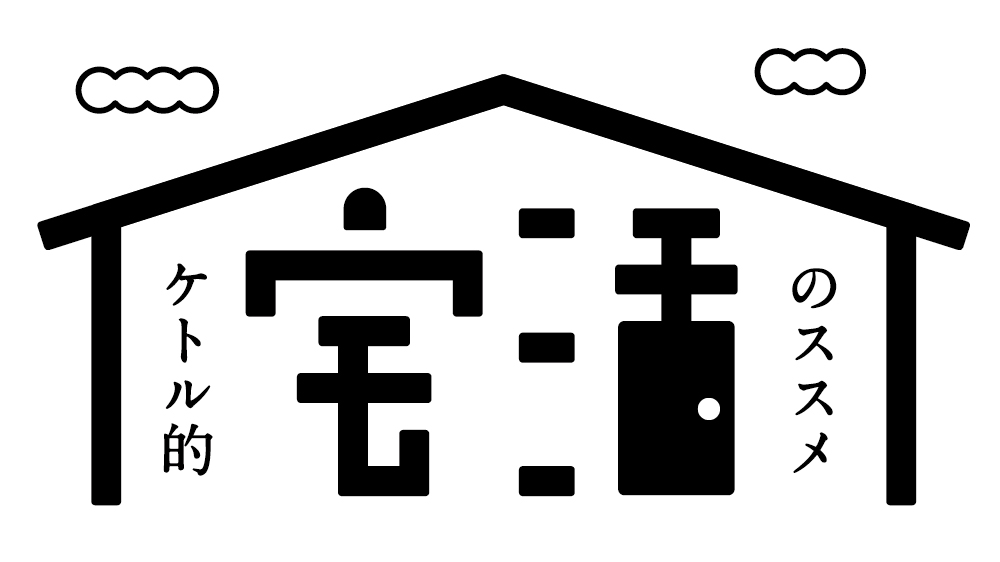

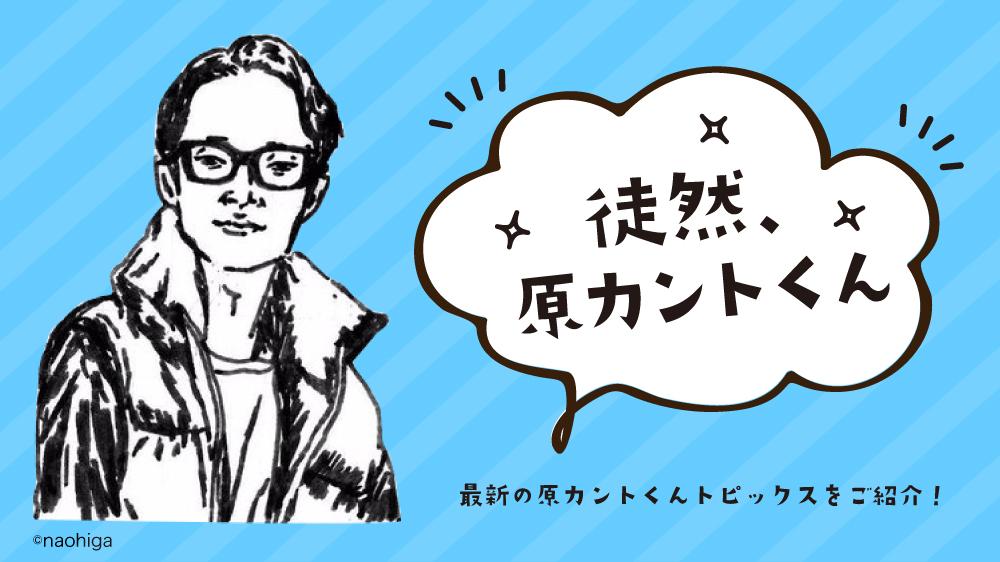

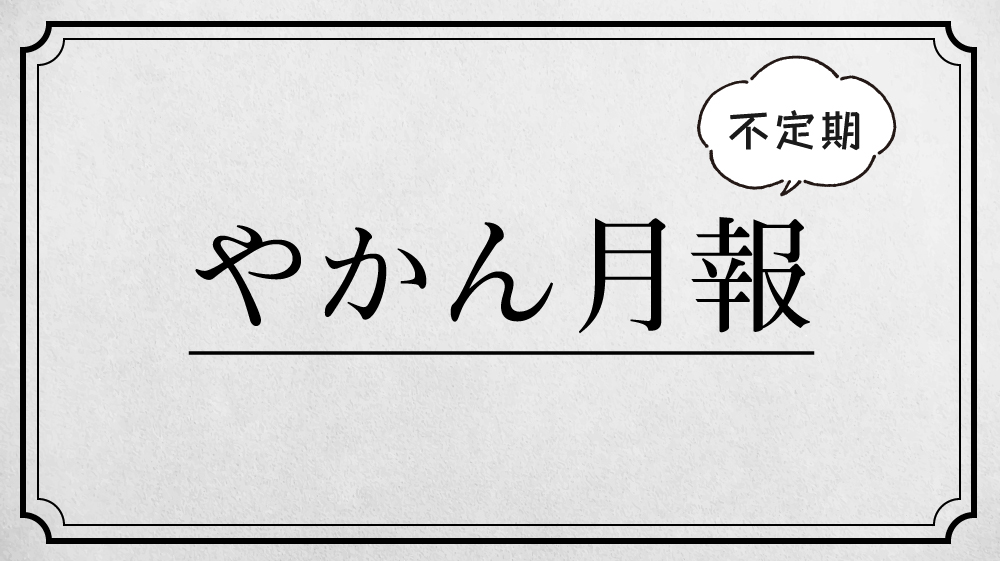
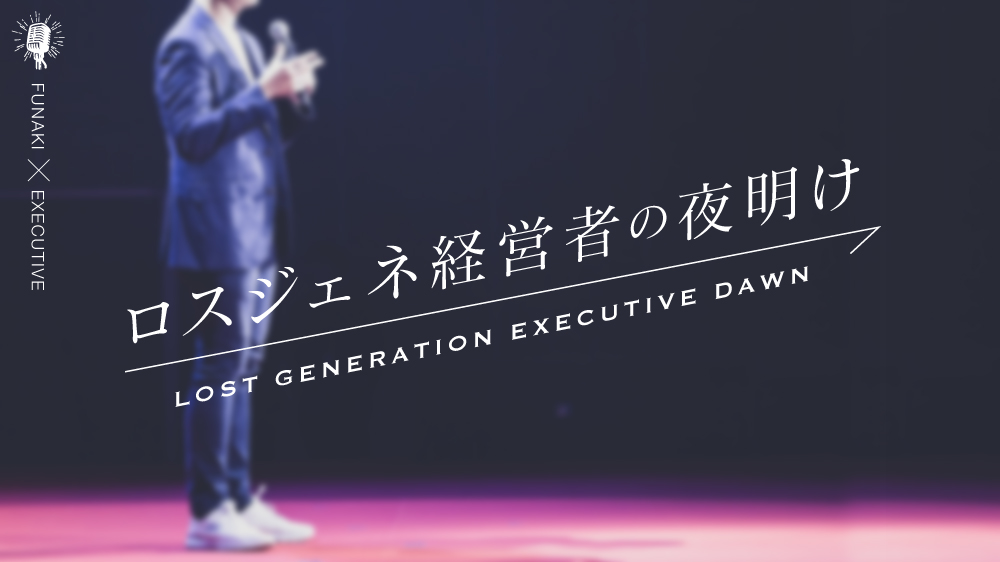

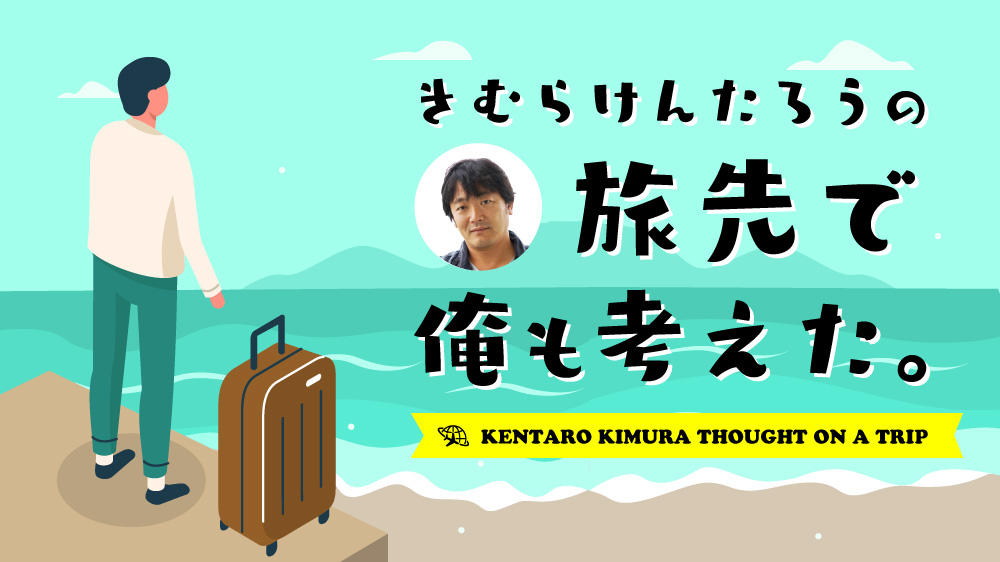

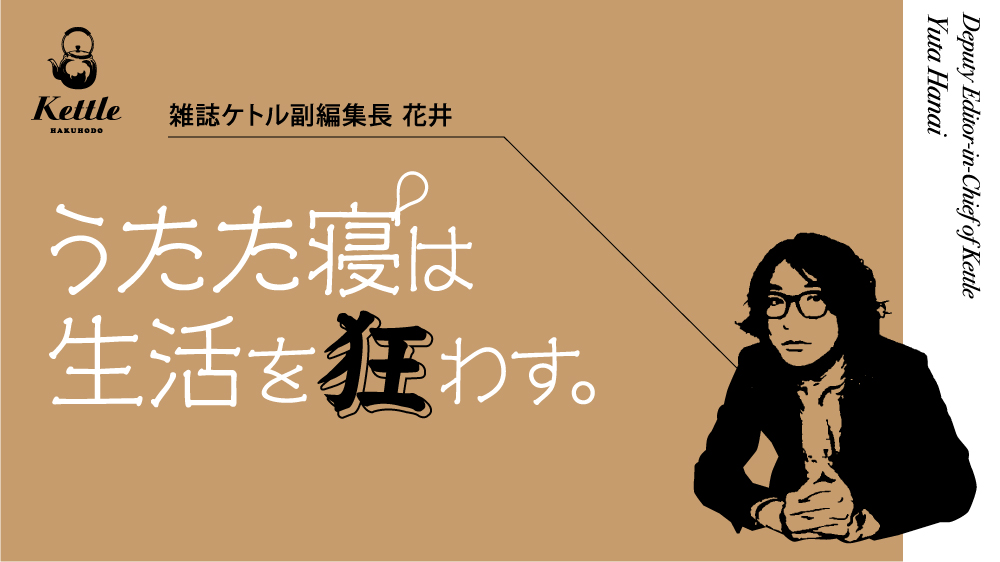






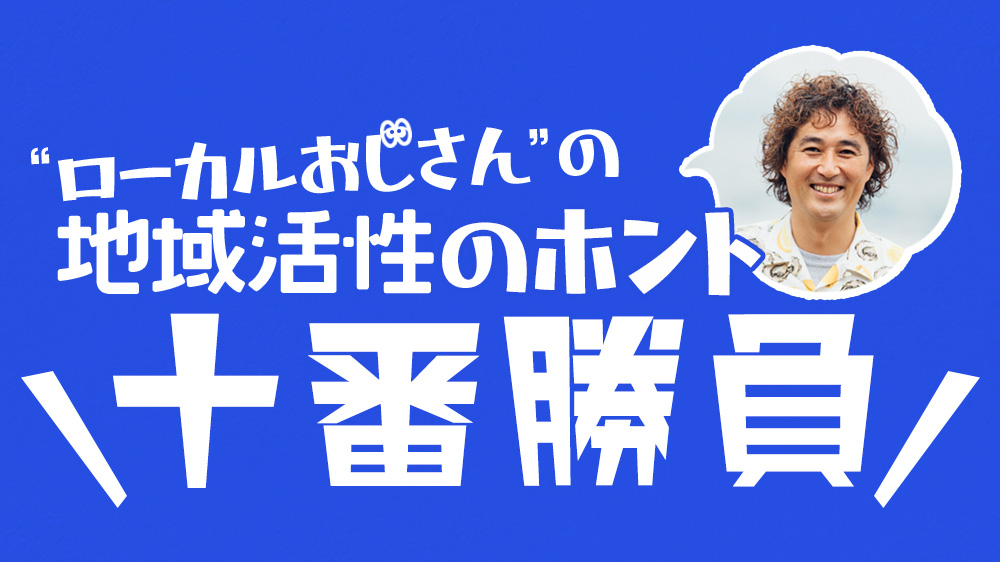
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「プロデューサー道」記事一覧
「プロデューサー道」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター