2020/04/15
”関わりしろ”をプロデュースする
 日野昌暢
日野昌暢

博報堂ケトルのプロデューサーである、ローカルおじさんこと日野昌暢の日々を綴る連載「プロデューサー道」の第5回です。今回は”関わりしろ”の話をしようと思います。
”関わりしろ”というのは、そこに自分が関わる余白があるかどうか、ということを意味している造語で、教えてくれたのは昨今の地域活性のキーワード”関係人口”を提唱している、雑誌ソトコト編集長の指出一正さんや、ローカルジャーナリストの田中輝美さんです。ローカルの多くの地域で衰退が続く中で、地元を盛り上げるために何かをしたい!とか、好きなあの地域に自分も関わりたい!と思っている人が、実際に関わることのできる余白や余地を作ることだと僕は理解しています。博報堂グループがよく使う言葉”共創”にも不可欠な概念で、僕は最近、この”関わりしろ”の大切さを改めて感じています。
人というのは、自分が役に立ったと思えれば嬉しいものです。自分の働きが、結果にいい作用を与えていると感じられると嬉しい。今、世界を脅かしているコロナ禍で、人はそれぞれの立場やスキルで「自分には何ができるのか?」を模索しています。テイクアウトを始めた地元の飲食店を知らせる仕組みを作る人、有用な情報をまとめたりシェアする人、Stay HomeとSNSのアイコンにつけるための仕組みを作る人など様々です。その、何かできるフレームに、何かしたい人が乗っかることで、取り組みが広がっていきます。星野源さんがinstagramにアップした曲「うちで踊ろう」も、投稿で「誰か、この動画に楽器の伴奏やコーラスやダンスを重ねてくれないかな?」と投げかけ、”関わりしろ”を意図的に作ったことで、たくさんの人がそれぞれの立場やスキルでできることを考えて、コラボ動画が次々とアップされていきました。これも共創です。
打開すべき状況が目の前にある時、誰もが画期的なアイデアを思いつけるわけではありません。日本の地域活性もまた、打開すべき状況が長く続いていて、なんとかしたいと思っている人がたくさんいます。この打開は、どこからかスーパーマンがやってきて解決してくれるわけではなく、街に住む人たちの力でやらなければ本質的な活性になりません。主役は、その地域に生きる人たちです。私が関わった、群馬県高崎市の企画『絶メシリスト』も広島県の観光キャンペーン『牡蠣食う研(かきくうけん)』も、主役は地域に生きる人たちですから、その方々と”共創”することが大切だと僕は考えました。ローカルでは、僕たちからみたら、すごいことをしている人々が、地元では当たり前の存在だったり、知る人ぞ知るだったりすることが本当に多いです。外から目線で見ると「すごい!」ってなる人がローカルにはたくさんいます。僕は、その方々がこういう”関わりしろ”のある企画フレームに賛同して、一つの塊になり、アクションを起こすことで、街の状況に変化させることを意識してプロデュースをしています。
一つ、印象的なエピソードがあります。大分県別府市のBEPPU PROJECTが開催した「混浴温泉世界」というアートイベントが、2009年に市民の力を借りながら一定の成果を納めたことを受け、3年後の2012年に事務局の人員を雇って体制を増強して準備をしていたら、前回に比べて事前の集客が芳しくない状況が生まれたそうです。原因を突き止めたところ、増強した事務局が、前回は市民の方々を巻き込んでやっていた部分を、全部自分たちでこなしてしまっていたと。それで、事務局は増強したのにめちゃめちゃ忙しいわ、市民はイベントの準備が進んでいることを知らないので集客が進まないわで、そのリカバーにとても大変な思いをすることになったのだと、BEPPU PROJECT代表の山出淳也さんが教えてくださいました。これも”関わりしろ”のプロデュースの重要性を端的に感じられるエピソードです。その後のBEPPU PROJECTは、様々なカタチで別府市民との共創を続けていらっしゃいます。
地方創生とか地域活性とかいう言葉を作らないといけなくなる前は、ローカルの都市それぞれの繁栄が普通にありました。明治維新以降、人口がどんどん増え、街が”シムシティ”のように大きくなる時代には、それぞれの地域のまちづくりに尽力した人たちがいて、商いで稼いだ私財を投じたりもしながら、地域に生きる人たちの手で街を作っていたはずです。街に”関わりしろ”がたくさんあって、街が”共創”されてたのではないか。ちなみに、江戸幕府成立時の日本の人口は1227万人、明治維新の時で3300万人、第二次世界大戦終了時が7199万人。ピークの2004年が1億2784万人だそうです(※国土交通省の資料より)
日本が大きくなっていく間に、都市化が進み、お互いが関係することが難しくなって、みんな企業戦士になって、”まち”は国や県や市や大手資本が作るもの、のような感覚がはびこって、地域に存在していたコミュニティが崩壊しました。しかし、それもこのコロナ騒動でもう一回の揺り戻しが来るんじゃないかなと思っています。街を作るのは、そこに住む人たちです。
ポストコロナとかウィズコロナという言葉も出てきていますが、この騒動が過ぎた時に世の中の価値観や行動は大きく変わっていくはずです。そもそも無理がきていた旧来型の行動パターンとかヒエラルキーがようやく崩れて、次の最適化への変化がものすごいスピードでやってきます。社会が作り上げたシステムの中に乗っかって安定して暮らすっていうのが薄まって、みんな自分で自分の居場所を作っていくような、”都市化の融解”が起こるのではないかと感じます。地方創生予算で何千億円もかけても生まれなかった東京一極集中からの逆流が起こるのか。その時に、気持ちを持って地域活性に取り組む人たちに、僕たちのようなコミュニケーションとかプロデュースのプロがどう作用できるのか。僕らのプロフェショナリティの真価が問われているんだと僕は思っています。

「別府観光の生みの親」と言われ、温泉マーク「♨」の発明者でもある油屋熊八像の前で

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






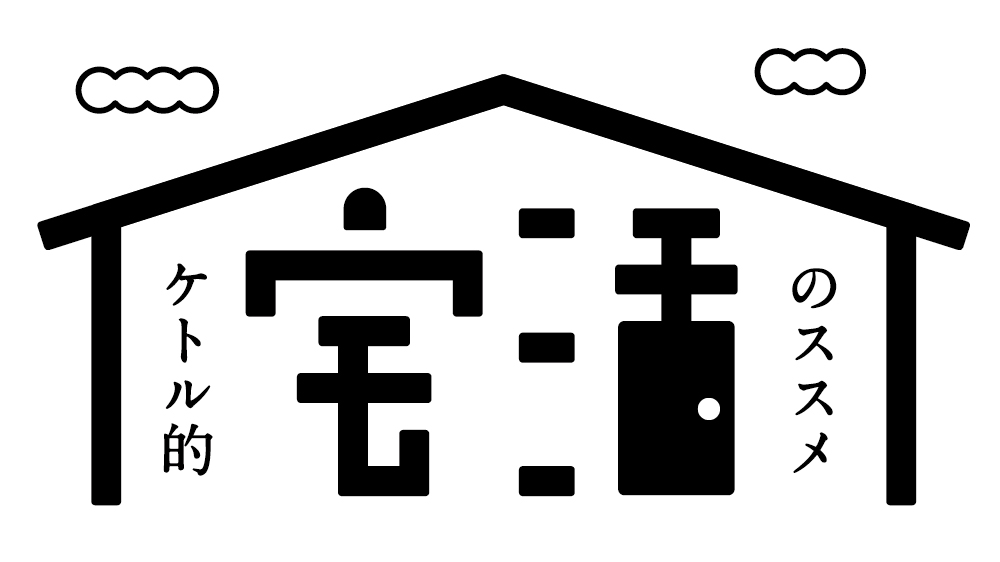



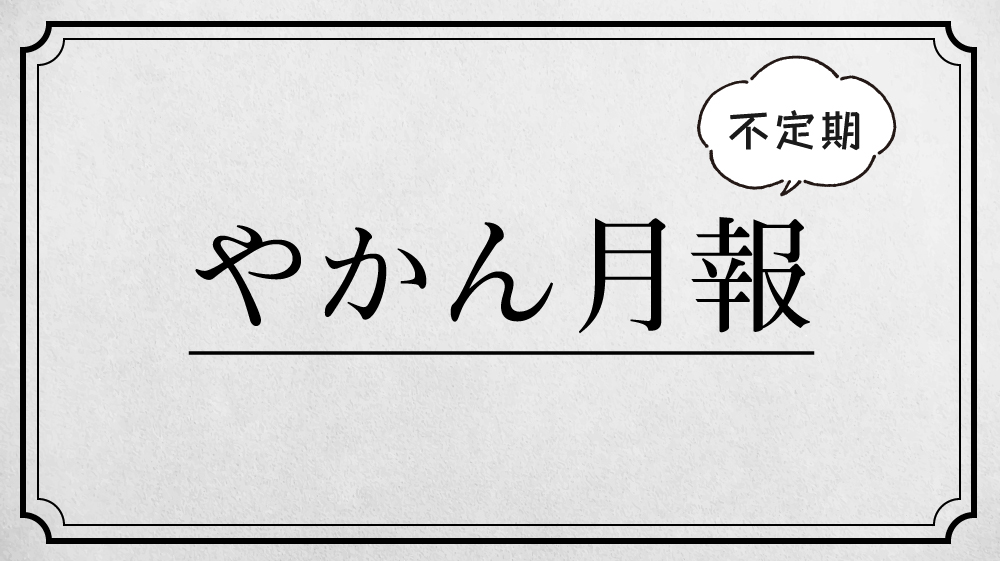












 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「プロデューサー道」記事一覧
「プロデューサー道」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター