2020/11/27
ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.2 井上岳一×馬場未織×日野昌暢② 「列島改造から列島回復へ―新しい社会の物語」
 日野昌暢
日野昌暢

ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.2
井上岳一×馬場未織×日野昌暢 前編 はこちら。
ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.2 井上岳一×馬場未織×日野昌暢①
前編に続いて、考えていきます。

(写真左上、井上岳一さん、右上、日野昌暢、写真下、馬場未織さん 以下敬称略)
日常に結びついた感覚
井上:山水郷のように、根源的な祝祭性みたいなものが手に入れられる場所と出会わずに、捨てていっちゃうのってすごくもったいなくて。僕も息子とイワナを手づかみで取ったりしてると、縄文人はこうやってイワナ取ってたんだと思うんですね。1万年が、ポーン! ってつながるんですよ。DNAが喜ぶというか。その感覚は多くの人が味わったらいいなと思うし、知らないで生きているのはもったいないなと思いますよ。
馬場:井上さんの本の中でエボリューションとインボリューションと書いてあって、まさにそこなんだよなと思ったんです。(※著書 p253 ”進化”は一般的に”Evolution”と訳され、(e)外へ+(volve)回転する+(tion)ものこと、を語源として「外に向かう変化」を意味する。これに対して哲学や現代思想の世界では”involition”という「内に向かう変化」の概念が言われるという記述。)人は外に向かって発展していこうとしますよね。それは、自己拡張の感覚があったり、満たされていく一方で、自分の中にきちっと根の生えた感覚がないと、不安が宿りっぱなしなんですよね。これは田舎暮らしを長く続けていくと、少しずつ解消されていきました。このつながった感は、都市だけでは得難かったなって思うんです。
井上:その一方で、日常と非日常とがあるけれど、日常だけだと人間ってつらくなるんですよね。そこに対して、「山のかなた」を夢見るという気持ちはすごくあって。そういう「山のかなた」を夢見る人が集まってきてつくったのが都市だと思っています。都市って、日常の重さから離れて生きていける場所。
馬場:そうですね、それはあります。
井上:すごく便利だし楽しいですよね。でも都市で消費だけの暮らしをしていると、暮らしの中に潜む根源的な祝祭性みたいなものに、気づけなくなっていく。暮らしと仕事が完全に分断されてしまっている。企業も昔は結構暮らしと近かったと思うんです。例えばホンダがホンダスーパーカブを開発した当時は1957年ですから、舗装路がほとんどなかった。だから、本田宗一郎と藤沢武夫が設定したカブの要件には舗装していない道を普通に走れるバイクっていうことがあったんですね。蕎麦屋の岡持が片手で出前を運べるという要件もあった。藤沢武夫は、女性がスカートでも乗れるという要件を追加しています。ここにあるのは、大地とか人間とか暮らしに対するまなざしです。それって多分すごい普遍的なものだから、ホンダのスーパーカブは、全世界で1億台以上、これまで人類が生み出した中で、最も売れたモビリティマシンになれたんです。でも、今の僕らは、どんどんそういうものから離れて商品企画してるような気がしています。企業は、地域とか町とか暮らしに近づいていくことによって、違うイノベーションを起こせるんじゃないかなと思っています。
子供に伝える
日野:なんだろう、ほとんどの大人がそういうまなざしを失った状態でサラリーマンになっちゃって。大人の時点でもってないから、子供に伝えられないし、子供はもっとそうなっていくバッドスパイラルがある中で、本の中の、ローカルが子供に教育を与えるという部分。地域の方が教育みたいなものをつくり出すことは、めちゃくちゃ大事だなあと思ってて。まさにそれを個人ベースで実践されたのが未織さんだと思うんです。

井上:だってお子さんの教育のために里山暮らし始めたんでしょう?
馬場:そうですね。息子が非常に虫好き、魚好き。まあ恐竜から始まって石とか星とか何でもそうなんですけど。私は、都市生活に不足があると1秒たりとも思ったことがなかったのに、自然が好きな男の子の視点で見たときの都市の貧しさにびっくりして。先ほど、日野さんが、大人が離れていくと子供も離れると言っていたように、子供が突然それを学び取るのはハードルが高くって。子供は大人の姿を真似て育っていく部分があるので。そのときにどういうリテラシーをもった大人がその教育をするといいのかというところまで考えると、時間がかかる話だなというふうに思うんですよね。
手足の知性
井上:未織さんの話の中で、南房総のオジサンたちは何でもできるっていう話があったと思うんだけど、重機も扱えるし、本当に何でもできるんだよね。僕も神奈川の田舎の二宮って町に住んで、すぐ消防団に入ったんだけど、正直大学どころか高校もでてないような人もいっぱいいて。でも、消防団は年次が絶対だから、僕とかは消防団では先輩の年下の植木屋さんに「だから東大生はダメなんだ」とか言われてむちゃくちゃいじめられて(笑)。
だけど、そういう年下の植木屋さんとか大工さんと付き合って、発見したことがあって。彼らの手の使い方がとてもいいんですよ。何かを扱う時の手の使い方がとてもたおやかというか、無駄がなくて。それを見た時に、僕らはなんか知性というものをずっとなんか頭脳の知性だけだと思ってきたけど、実は手足の知性ってあるんだなと思ったんですよね。その手足の知性みたいなのって僕らはほとんど開発しないで、頭脳の知性ばっかりになっちゃったんだろうなと思ってて。
馬場:手足の知性という言葉がすごく好きなんですけど。その可能性の広がりって、手足の知性で止まらなくて、頭脳の知性にフィードバックするなという感覚があって。そういう学びは、東京とか都市部よりも、地方の方がつくりやすいかもしれないですね。

井上:後は単純に興味の対象がいろいろあるっていう。例えば虫でいえば、なんでこんなへんてこな形してるんだろうとか。山登った時も、「こんなでけぇもんは人間は造れねぇよな。誰が造るんだろう? やっぱ神か?」みたいなことを5歳の息子が言うとか。そういういろいろなものに誘われて、知的関心が広がっていくというのがあるんだろうなと。そのときに、うまくそれに合わせて、導いて教えてあげるようなやり方をすると、いろんな勉強もすっと入っていくんだろうなと思う。
回復の本質とは、引き受けること
井上:家族のこととか人生のこととか、田舎に生まれた人はその土地のこととか。みんな生きていればいろいろ厄介なことがあると思いますが、『日本列島回復論』で言いたかった回復の本質というのは、弱点も障がいも個性として引き受けて、その土地ならではの物語を紡いでいきましょうよっていうことです。自立ってことがこの本のテーマなんですが、自立の本質はやっぱりある種厄介なことも全部すべて引き受けて生きることなのかなと思って。
僕らは「引き受ける」ことをずっとしてこなかったんじゃないかなと。都市に生きていると、会社や住んでいる所だって、気に入らなければ変えればいいと思うわけですけど、そうではなくて、ある特定の場所とか人間関係とか、そういうことを引き受けるっていうふうに覚悟したときに初めて何かが開けてくる。そのとき初めて自立の足場がつくれるんじゃないかという気がしてそんなことを書いたんですね。
日野:未織さんから見て、井上さんの書かれた本にいろいろ感じるものがあったとおしゃってましたが、どういったことだったんでしょうか。
馬場:ギュッと詰まった中で自分の足が立たなくても、もたれ合いながら生きているような。「都市の密度感」ってそういう不健全さがあるような気がするんですよ。
自立って、言葉は綺麗ですけど大変な話で、井上さんも引き受けるっていう言葉を非常に前向きに書いているときと、面倒なものを引き受けるという部分で、ネガティブに使っているときがあって。多分そのどちらの意味も負わなきゃいけない。自立して生きるためには引き受けなきゃいけない。引き受けるためには、その個人が精神的に成熟しなきゃいけないというところで、プロセスはどうやって作ればいいんだろう?というのはすごく思うところなんですよね。
日野:うんうん。僕も井上さんの本を読んで、こんな社会が少しずつ広がっていくといいなと思います。井上さんの本に出てくる「引き受ける」というコンテクストに共感した人たちが行動を起こして、日本列島の豊かな自然の力をもう一度、今度はテクノロジーと掛け合わせることによって、違う形で今なりに再活用できる人たちがどんどん増えていくみたいなことなのかなあと思っています。
街を変えるのは「引き受ける」翻訳者
日野:未織さんが今、家を持たれているところは南房総。そこはもう昔から住まわれている高齢の方々がほとんどなんですか?
馬場:そうなんですよ。例年とはいわないけれど、隔年ぐらいで亡くなっていますね。
日野:井上さんの本にも書いてあったかなあ。安宅さん(『シン・ニホン』著者)が風の谷プロジェクトと言ってますが、開疎化が起こせる最適な場所を、井上さんのおっしゃってるソサエティー5.0の始まりの場所にする。次のテクノロジーを使った、テクノロジー×自然の新しい社会をつくるということは、今、未織さんが、第2の拠点にされているようなところから始まるのだろうなあと思っていたりするんですけど。
田舎にはないけど都会からもち込まれた技術。未織さんだったら、建築みたいなことかもしれないし。その可能性みたいなものを、今の2拠点生活の中で感じたことはありますか?
馬場:そうですね。井上さんの本の中で、南相馬のおじいちゃんおばあちゃんが自動運転のことをすごい喜んで、村の未来を見いだすかのように語るという文脈があって。私すごく分かるんですよね。なので、実証実験を各地でやって特色をつけていくと面白いんじゃないかなと思いますね。ただ、やろうと思うと問題があって。企業が例えばそういうことを起こそうとすると、地域との温度差が大きいんですよね。企業の先進事例づくりは結構遅いけど、おじいちゃんおばあちゃんたちは結構早く見たい。そのあたりの熱烈歓迎ぶりと、実際の動きの温度差で、逆に冷えていってしまうという難しさも感じたりしますね。
井上:うん。1980年代、アメリカは日本に負けてダメになってて。シリコンバレーとかも、コンピューターで発展したんだけど、80年代後半になると一気に冷え込んじゃって。人口流出もあって街も荒んでというのが、80年代後半から90年代前半にかけてのシリコンバレー。そのときにインターネットを使って、もう1回街をつくり直そうと考えた人たちがいたんですよね。それをやったのはみんなNPO。企業が町をつくると、企業の理屈で企業のテクノロジーを入れるための場になっちゃうじゃないですか。そうなったら、栄えない。インターネットがどうなるか分かんないけど、それを暮らしの文脈、町の文脈に引き寄せて、それでどう使えるかを考えようと言った連中がシリコンバレーにいたんですよ。
馬場:すごく分かります。要するに引き受けるという話だと思うんですけど、失敗も引き受けるということ。過疎地って、企業からそういう話って結構来るんですよ。でも、本当に自走した例をほとんど見たことがない。そのリスクを自分がとろうと思う人が中にいない限り、成就しない。
井上: シリコンバレー発展の立役者となったNPOのプロジェクトの採択基準が結構面白くて。本当にそれはシリコンバレーに住んでる人たちの役に立つか。街のためになるかというのを考えて。結果としてあの形になっていくという。そういうことを見て、じゃあ本気になって企業もやってくれるんだったら、行政の側も本気になって規制緩和します、みたいなね。持ちつ持たれつをすることによって、初めて新しいことが生まれてくるんだろうなと。
日野:さっきの教育の話もそうですし、そういう山水郷に対して、翻訳者みたいな人が必要で。東京側にずっといる人だけでもダメだし、田舎、ローカルの方にずっといる人はもう気付きようがないし。お互いにないものを欲しがってはいるけども、それでバチンと会うとマッチングしないというか。だから両方を行き来する人が、そこで何か起こしてやろうって思いがあるということが大事だと思います。
今日実は、トークを聞いてくれているみなさまの中に、「関係人口」という言葉の提唱をされている田中輝美さん(ローカルおじさん十番勝負vol.6に登壇予定)という方がいて、一緒に議論したいなと思っています。アフタートークという形でこの後は話していこうと思います。

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






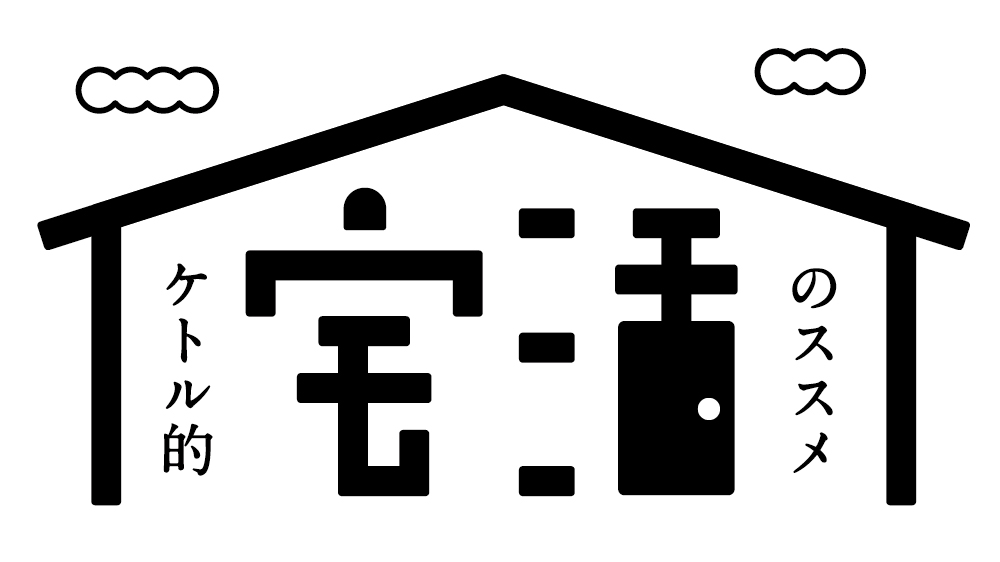



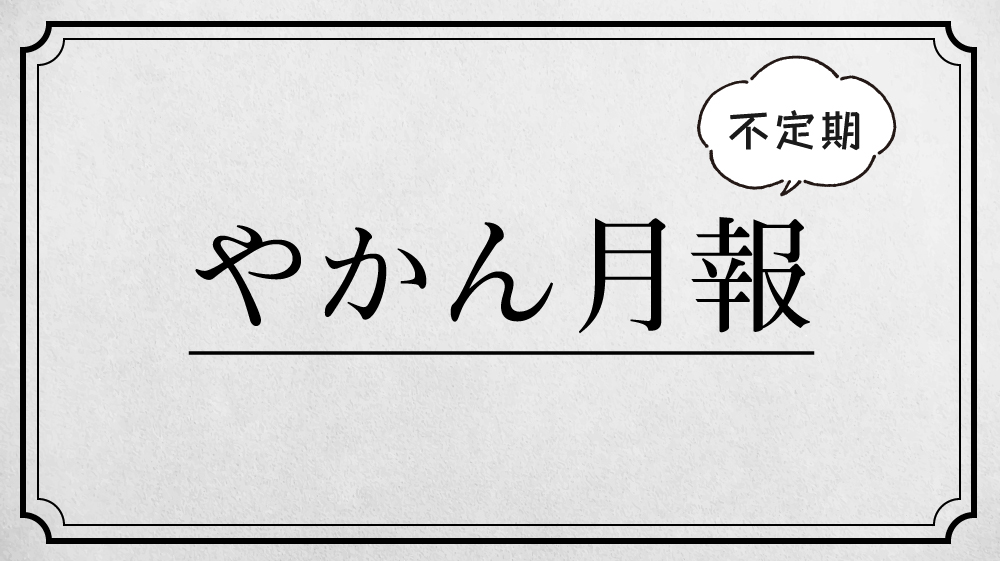












 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧
「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター