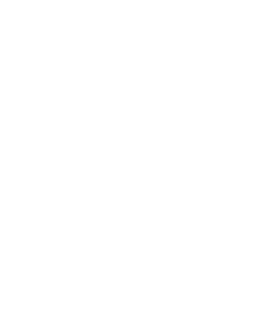2020/12/30
“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.3 石丸修平×高島宗一郎×日野昌暢「最強都市 福岡のネクストステージを語る」『超成長都市「福岡」の秘密』(日本経済新聞出版)刊行記念 中編
 日野昌暢
日野昌暢
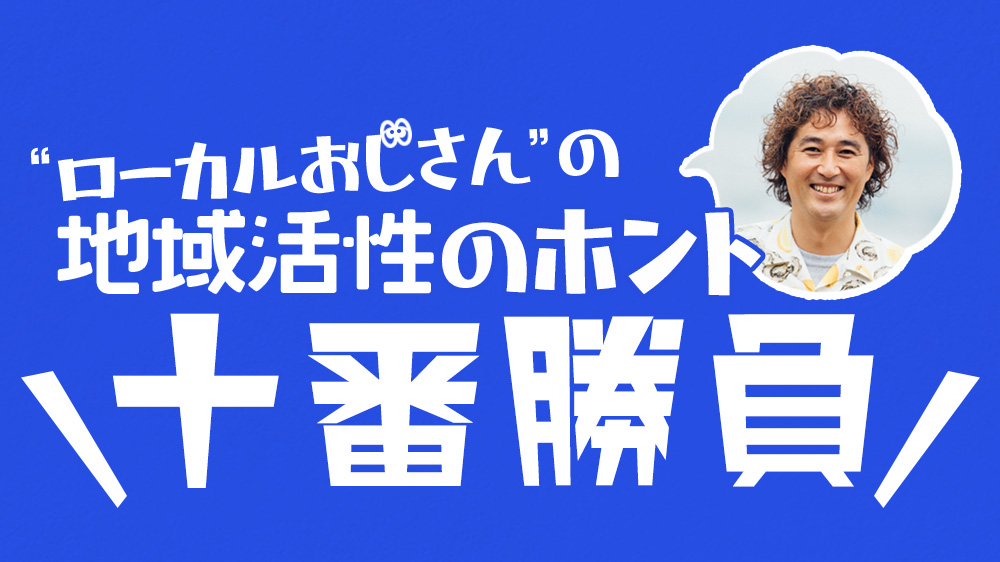
“ローカルおじさん”の地域活性のホント十番勝負 vol.3
石丸修平×高島宗一郎×日野昌暢 前編はこちら

(写真左上、福岡市長/高島宗一郎さん、写真右上、福岡地域戦略推進協議会事務局長/石丸修平さん、写真下、博報堂ケトル 日野昌暢 以下、敬称略)
前編では、石丸さんが執筆した『超成長都市「福岡」の秘密 世界が注目するイノベーションの仕組み』を通して、地域をアップデートするために必要な、産学官民の連携、広域連携を福岡地域戦略推進協議会(FDC)がどのように取り組んでいるかを聞きました。どうすれば福岡のようにできるのか問い合わせが増えているそうです。高島市長が考えるその秘訣、そして、いち早く感染症対応シティを打ち出し、ポストコロナの最強都市と言われている福岡のあり方についても話していきます。
民間でのまとまり
日野:コロナの後にお二人に届く声だとか、問い合わせみたいなことではどういうことを感じていますか?
石丸:FDCには他の政令市の方はだいたい訪ねて来られました。官民連携を中心に正しい取り組みをやっていかなきゃいけないとみんな考えていらっしゃるんですけれども、なかなかそのやり方が分からないというのが現状なんだろうと思います。
特徴的なのは、だいたい役所の方が来て「こういったものを作りたいんですけれども、民間サイドがなかなか動いてくださらない」と悩んでいるパターンが多いんです。対話の場がなかったり、きっかけがなかったり、同じ方向を向いて認識合わせできるような場がなかったりとか、課題が深そうです。福岡の場合はそういった課題はむしろないです。首長の強力な理解とコミットがある状況ですから、枠組みの中でいろいろと、役割をどういうふうに動くべきかを考え、走っている関係性であるというのは相当大きな差だなあと思います。
日野:行政の方が、民間が動かないとおっしゃることが多いんですね。意外。
石丸:民間の方からは、どうやったらまとまれるかという相談が多いですね。
日野:なるほどなるほど。福岡市は、みんな距離が近いというか、なんかこう、屋台で隣に座ったらちょっと友達扱いとして喋り始めるみたいな。まちの風土とか気質みたいなことも関係あるとか、民間で作ってきたまちだからということを耳にすることもあるんですけどね。どういったところが影響していて、何が福岡市のいいところなのかというのは、高島さんはどのように見られていますか?
鍵は”Think & Do”
高島:もちろん、今おっしゃったような風土とかはあると思うんですけど、なぜ福岡がうまく展開しているかを構造的に考えた時に、FDCがハブになっていて、これがthink tankじゃなくてthink & do tankというところが大きかったのかなと思います。
FDCは、自分たちで事業を行ってそれで自主財源を得て独立しています。つまり行政からお金をもらって予算をこなして報告書を作ることが目的ではなく、まちを変えていくことが目的なんです。doまでできるので、FDCに参画する事業者の本気度もすごく変わってくる。また、行政と一緒に両輪のイメージで取り組んでいて、FDCで作った成長戦略やプランと福岡市の政策推進プランとをうまくリンクさせています。独立したFDCだけの話で終わらず、それを行政との連携に落とし込むという仕組みまで持っているので、両輪ともにガッツリ地面をグリップして前に進むような形になっています。全国いろんなところで、まちづくりイベントがあってもそこの首長が知らないところでやっているとか、今日はいい話になったよね、いい提言だったよねっていう自己満足で終わりになっていることがよくあると思います。福岡市はそうじゃなくて、本当に連携するように、最後の詰めまで落とし込むための仕組みまで設計されているんです。

また、民間と行政のスピード感は全然違っていて、行政は基本的に3月の予算議会で予算が可決されたら、それを4月から1年間かけて執行していくという仕事です。でも民間は、もっとタームが早いし、スタートアップだともっと早いわけですね。思い立ったら他がする前にやってみて、トライ&エラーで修正をしていきながら、いかに成功モデルを早く作るかということが大事です。でも実は、行政と連携しなきゃできないこともいっぱいあるんです。こういう時、福岡にはFDCがあります。FDCの事業とすれば、行政と連携をして行政の後ろ盾や連携ができつつ、民間のスピード感を持てる、ちょうど民間と行政の間のいいとこどりで、うまくスタビライズ(安定性を確保)してくれるんです。
福岡でならチャレンジできると思える訳
日野:産官学民を超えて実現していく、社会実装していくというのは、相当いろんな困難があるでしょうが、それをFDCとか福岡市と一緒にやったらできるんだとみんなに思ってもらえることの積み重ねが、どんどん人を引き寄せるということですね。福岡市やFDCがみんなから、バッて向いてもらうきっかけになった一番大きなトリガーって何かあるんですかね。
石丸:なんでしょうね。少なくとも福岡市がそもそもそういう場所であるということが当然重要で、首長が成果を出していくことから、新しいチャンスがあるんだというところがちゃんと見えることですね。でも、今元気な福岡市に自分たちが関わっていこうとした時に、実際にどう関わっていいか分からない。そこをワンストップで受け止められるFDCなんかがある。でも仮にその受け止める仕組みがあったとしてもそれだけでは難しくて。関わりたい自治体の意識だったり取り組みだったり特性だったり、そういったものが見えている中で、FDCの役割がちゃんと見える、この2段構えが整ってくるのは大事だったのかなと思いますね。
高島:1,000キロ東には東京、1,000キロ西には上海、もっと近くには釜山やソウルもあるメガシティのど真ん中に位置している、人口160万人の福岡市がどうやって生き残っていくか。まず、場所の特性として政令市で唯一、一級河川がありません。一級河川がなく工場を作ることができないので、知識創造型産業で生きていくしかない。だから、知識創造層の人たちをまちの中で囲い込んでいくための都市としての存在感を出すことがすごく大事になってきます。どうやって存在感を出すかを考えた時、東京でもほかの場所でもできない、福岡だったらチャレンジできるということが1つ大きな個性になると思います。
新しいテクノロジーから新しいビジネスモデルや製品がどんどん生まれて、面白いものやこれまで想像もしなかったようなものが生まれる。さらにこれが、社会で使われるようになるまで落とし込むことが大事なんです。
Uberやセグウェイ、キックボードといった、すごく便利なものが海外では使われています。じゃあどうして日本で使われないのかというと、それを使っていい社会にするかどうかは作った企業ではなく、政治や行政が決めるからなんです。だから起業家だけでは社会は変えていけないわけです。
この起業家の発想と、行政や政治という社会を規定する意思が1つになった時に、初めて社会や世界は変わっていくのに、それをどう落とし込むかという議論がみんなすっかり抜けているんです。これを福岡市でやれば、世界の最先端の人たちが福岡でチャレンジしたいとか、福岡に行けば私たちの成果を現実の社会で見せることができると思うようになります。そして福岡市でうまくいけば、マネタイズはメガシティでという流れもできるんですね。だから、世界の優秀な、最先端の人材を福岡に囲い込んでいこうと思っています。

これからの日本に必要な「破壊的イノベーション」
日野:なるほど。僕も『#FUKUOKA』という福岡市のWebメディアで、ITクリエイティブ系の方々を取材し続けるということをさせていただいたので、福岡にはちゃんとクリエイティブの人たちのシーンがあるなーって思っています。チャレンジできるまちのための国家戦略特区だとか、増えてきている今のITクリエイティブシーンみたいなのについて、お話を伺いたいです。
高島:スマートフォンという、市民みんなが手にする新しいデバイスが登場して、その上に乗せるサービスが無限に広がっています。デバイスを変えなくてもどんどん新しい利便を享受できるような時代になっています。社会が不完全なところほどデジタル化しやすい面があって、社会がアップデートされるんですけど、日本は一旦出来上がった国だからガチガチでデジタルが入り込む余地がない。そこで、破壊的イノベーションが大事です。これまでの秩序を一旦壊す作業が必要で、実はこれは不完全な中に入っていくより大変な作業です。でもそれなくしては、絶対に社会が変わっていくことはないです。
私は今、福岡市長をやっていますけども、もちろん日本がよくなってほしいと思っています。しかし、まちの個性も違えば強みも違うわけですから、全国で一律に「こうすれば一気に変わる」なんてことはありません。国家戦略特区でエリアを定めて、その中で規制緩和や優遇措置などの後押しによってモデルを作ることが、福岡はもちろん、ひいては日本全体を速く良くして、変えていくということになると思います。福岡で頑張る人たちには、ここで頑張っていけばこのモデルで日本も世界も変えていけるという、モチベーションが上がるような話をしています。
日野:ありがとうございます。ちょうど福岡市は、国家戦略特区を使って、ビルの高さ制限を緩和して、民間投資を呼び寄せて、ビルが新しく建て替わるというようなことをしているわけなんですけども。その途中でコロナがやってきて、多分デベロッパーの方々や建設会社の方々も、先が見えない中で必死にアジャスト(調整)をされると思うんですが、ビルが建て替わるというタイミングになってるっていうのも、ある意味ついてるなぁっていうか、今から考えられるというのはすごく面白い部分ではないでしょうか。
ポストコロナはチャンスになる
高島:チャンスです。普通だったら、東京と同じ機能を持った建物が福岡にもようやくできたということで終わりです。しかし、非接触、身体的な距離、通信環境といったコロナ対策を施したビルに一斉に建て替われば、東京にはない、福岡にしかない機能ができます。これは大きな強みであり、チャンスだと捉えるべきだと思います。
日野:石丸さん、その辺りFDC的には、動きはどんなふうになってますかね。
石丸:まさに、さあいよいよこれからだというタイミングでコロナがきたんです。緊急事態宣言の時は、結構民間サイドからは不安の声が出てきました。それをいち早く、デベロッパーとか地域の重要な役割になっている会社の社長さんや、今後の世界とか人類の生き方も含めて問題提起されてる方にも入っていただいて、本当にまっさらで議論させていただいたんです。あの場を設定できたということが、やっぱりFDCの価値なんだろうなということは改めて思ったんですね。
実際にあそこで交わされた議論をいち早く踏まえて、すぐ“感染症対応シティ”ということで発信までして、政策的なインセンティブを少し柔軟に対応していくとか、期間を延長するとか、そうした政策変更をしました。これ、さっき市長がおっしゃったように、政策を変えるのは簡単ではないんですけど、スピード感を踏まえてやれたということ自体が福岡のスピード感、コミットの力なのかなというふうに思いました。本当に対応が早かったですね。
日野:こんな塊でまるごと変わっていくっていうのはなかなか例を見ないと思うので、当然日本だけじゃなくて世界からも注目される部分になって、とても楽しみだなと思っています。
1つになって、九州を考える
日野:さっきちょっと話が出てました、九州のなかの福岡に関して、石丸さんも「ONE KYUSHU」といって、九州を1つの塊として考えるという思考をお持ちになられていますよね。先日のabemaTVで高島市長が橋下(徹)さんと出演された時に道州制の話をされていましたが、僕も『Qualities』というWebメディアをやっていて思うのが、 面白いプレイヤーがいっぱいいるけど、熊本の人と鹿児島の人と宮崎の人とか福岡の人は、お互いのことを知るきっかけがないんですよね。新聞もテレビ放送も県で分かれていますし、ローカルはWebメディアがなかなか成立しづらいので、九州の他のエリアの情報にはどうしても接することが少ない。でも、新幹線で1時間半で福岡から鹿児島まで行けちゃうような近さで、1つの島っていう仲間意識がもちやすい塊の中にみんないるんで、これをちゃんと考えていったほうがいいなと僕も強く思っています。そのあたりについて、道州制がいいのか、「ONE KYUSHU」がいいのか、どう思いますか?

高島:これからのマーケットはグローバルに考えるしかないと思うんです。その時に、九州の野菜や青果物は大きな強みになります。海外に出す時はロット数を一定以上確実に納められることが、販路を切り開くうえで大事な条件になってきます。台風が来ると農作物は被害を受けますが、九州の北部が被害にあった時は南部から出して、南が厳しい時は北から出すというように、いまは九州全体で考えることができません。各県に農協が分かれて存在していて、あまおうは「福岡県のあまおう」であって、鹿児島のあまおうにはできないんです。一方、北海道は北海道産でいけるわけですよ。九州は、北海道より小さいのにさらに細分化されているんですね。
一番大きい問題は、海外に進出しようとした時「九州」という地名は、日本地図の中に存在しないことです。北海道は「Hokkaido」って名前が出てくるけれども、九州はどこの地名にも住所にもないんです。これまでの狭いエリアでのエコノミーを考えるんだったらそれでも構いませんが、1,000万人規模で1つにならないと、グローバルではすごく弱くなってしまうんです。マーケットとしての魅力をアピールするには、そろそろこういう単位で考えることが大事だと思います。


「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






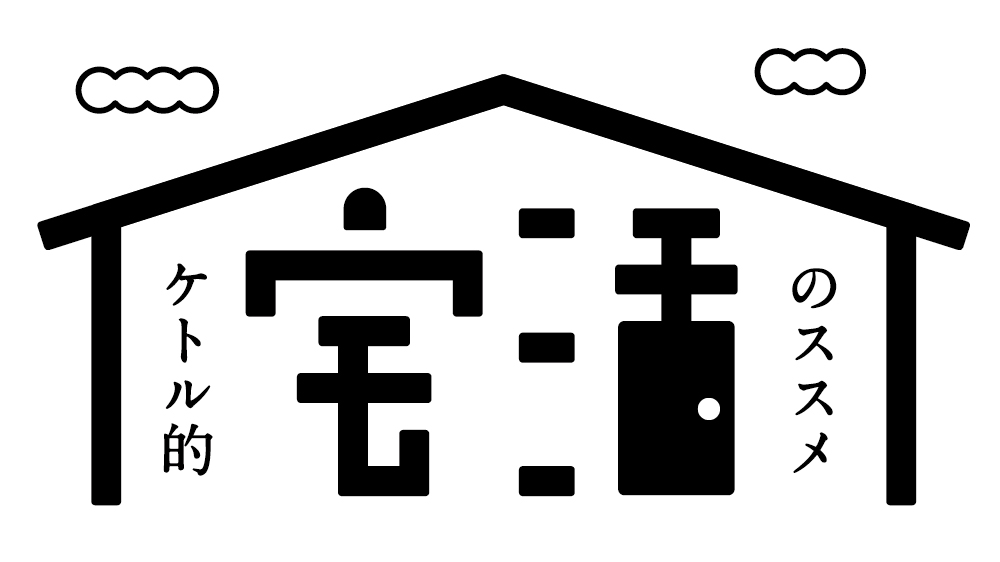

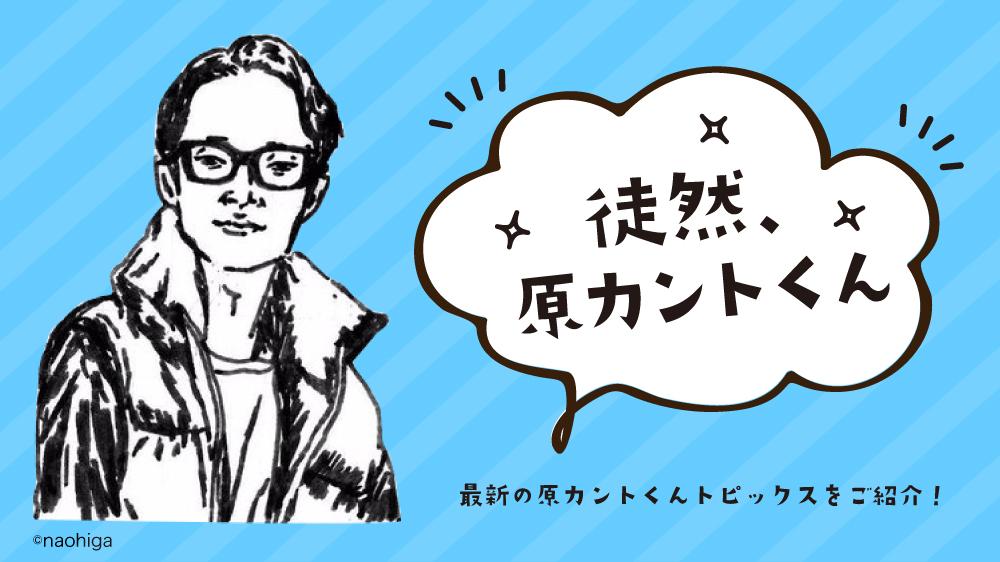

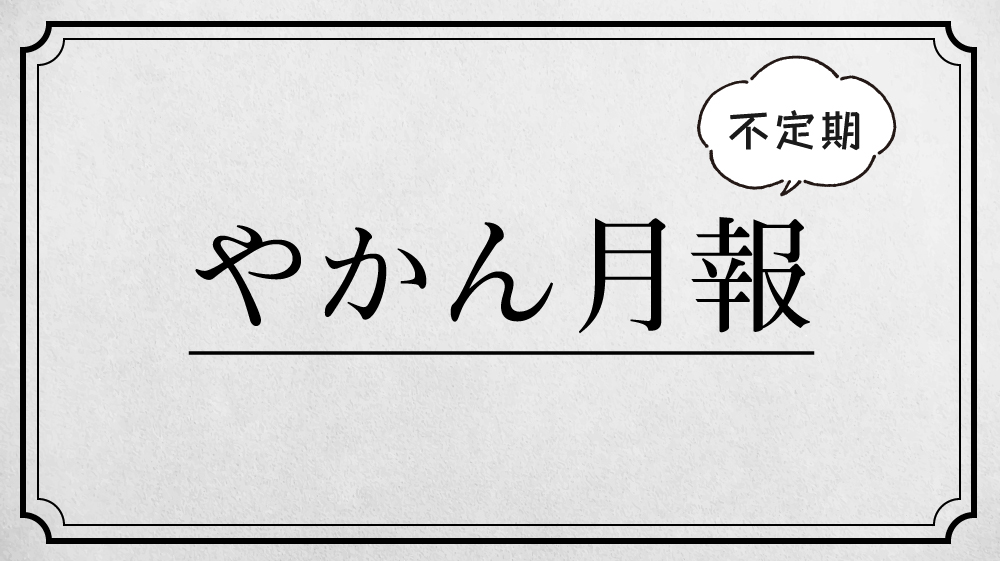
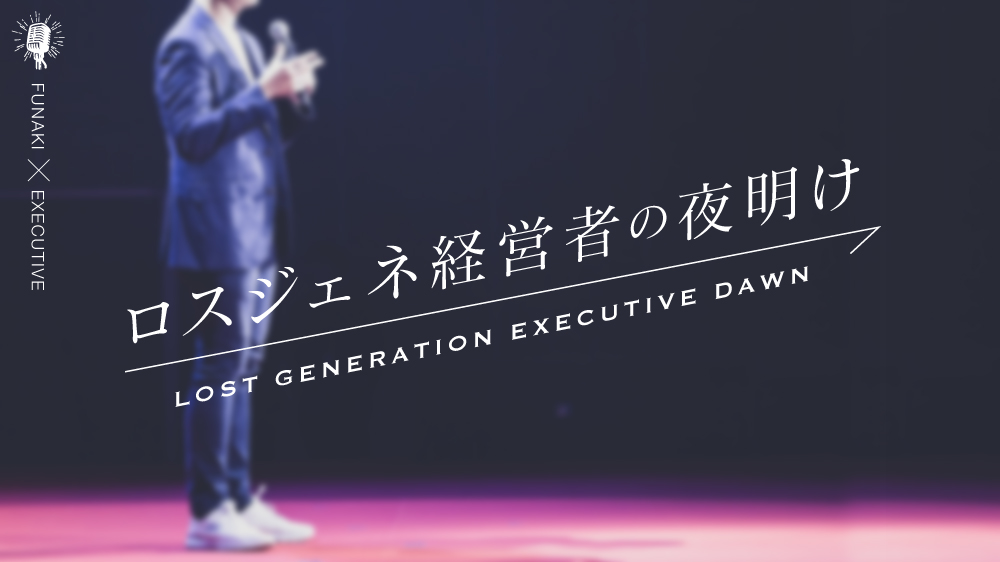

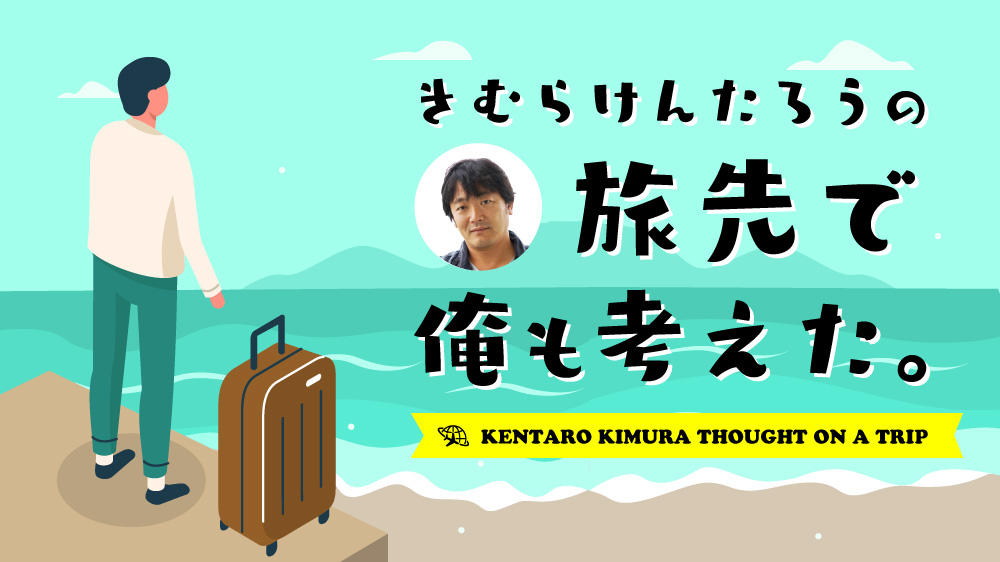

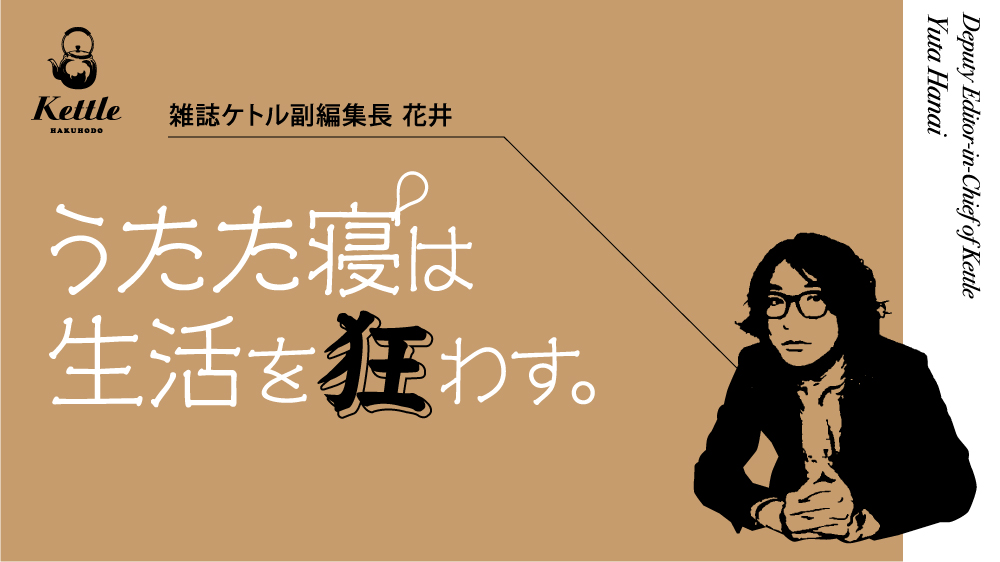






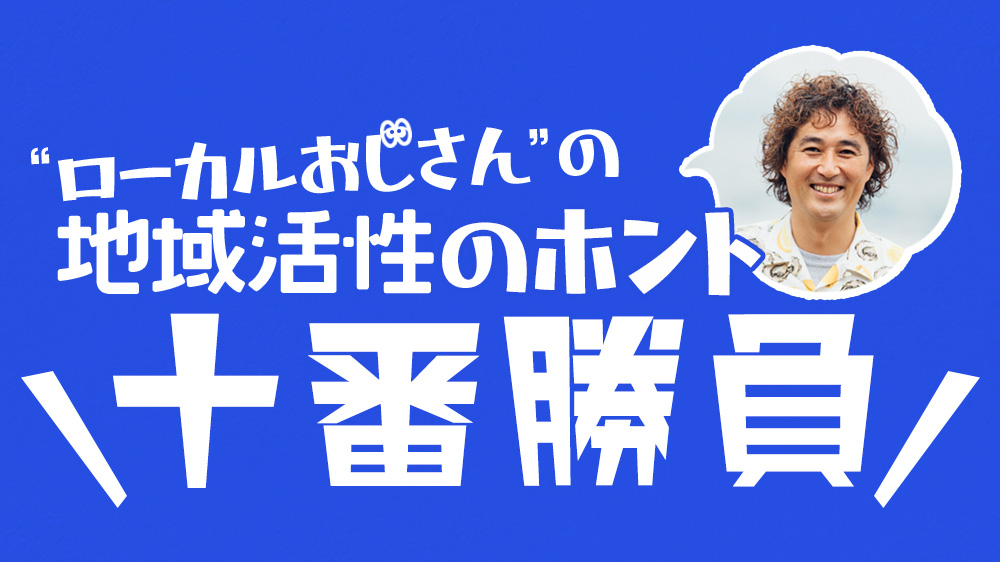
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧
「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター