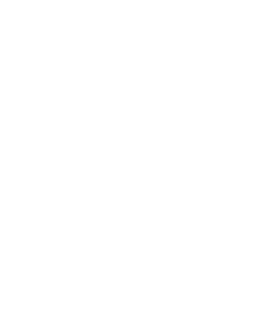2020/12/30
“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.3 石丸修平×高島宗一郎×日野昌暢「最強都市 福岡のネクストステージを語る」『超成長都市「福岡」の秘密』(日本経済新聞出版)刊行記念 後編
 日野昌暢
日野昌暢
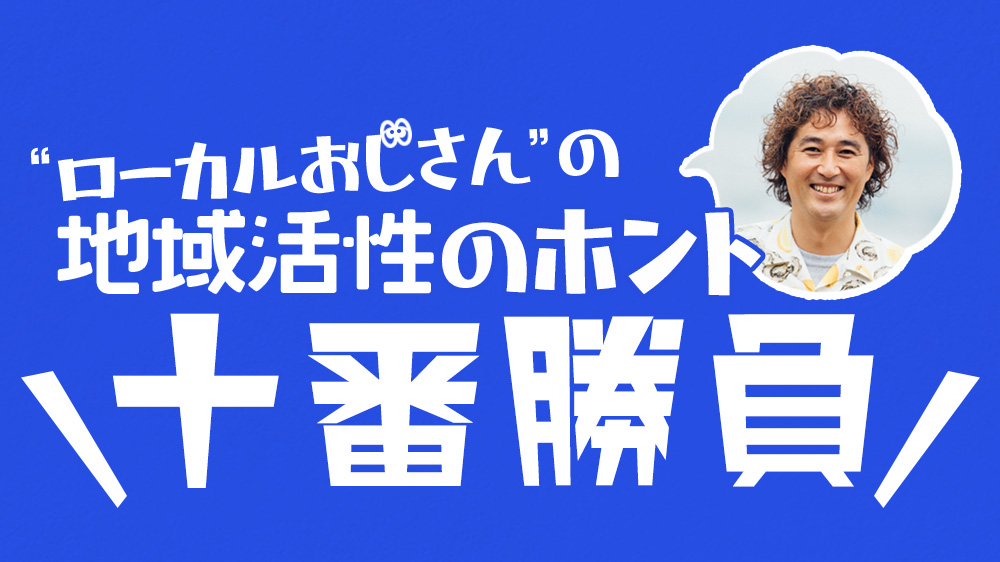
“ローカルおじさん”の地域活性のホント十番勝負 vol.3
石丸修平×高島宗一郎×日野昌暢 中編はこちら
“ローカルおじさん”の地域活性のホント十番勝負 vol.3 石丸修平×高島宗一郎×日野昌暢 中編
中編に引き続き、九州が1つになり、みんなでまちを作っていくことについてお話しします。

(写真左上、福岡市長/高島宗一郎さん、写真右上、福岡地域戦略推進協議会事務局長/石丸修平さん、写真下、博報堂ケトル 日野昌暢 以下、敬称略)
九州が1つになるトリガーは何か
日野:国が今、道州制に持っていこうとはしていない中で、とりあえず九州としての塊で考えたほうがいいよねと思った時に、やりようはあるんですかね。
石丸:そうですね。「九州は1つ」という時に、立場によって全然思い描くものが違うと思ってて。私も行政機構みたいな観点からいくと、もう100%道州制論者なので、現場と広域行政をつないでいける仕組みを作って、スピード感を持って進めていける体制という意味ではいいと思っています。「ONE KYUSHU サミット」(九州廃校サミットを発展させたイベント。石丸さんは副会長を務めた)では、民間サイド、市民サイドでも、九州が1つになればいいのにと思っている人がいっぱいいるので、事業会社見てもJRとかは九州全部で事業してるわけですから。そういった人たちも含めて、九州単位でやるということによってメリットを感じたり、よりよくなると思っている人たちと一緒になって流れを作っていくということですね。そういった動きを民間サイドでやっていきながら、私としては道州制みたいな議論がもう一度出てくる中で、机上の空論ではなく、今後すぐにdo tankとして動き出せるというところを準備していきたいなと思います。

議論には現場の声が必要
石丸:財界と知事会が一緒になった九州地域戦略会議というものがあるのですが、そこで感じるのは、政令市が入ってないんですよね。政令市が入ってない弊害が2つあると思ってて、1つは、そもそも政令市は県並みの権限を持っているので、そこに入ってしっかりと九州全体を考えていく役割を担っていくべきだと思うんです。もう1つ私が思うのは、現場感覚の議論が難しいということです。政令市は基礎自治体として現場を持ってるので、まずは政令市だけでも入っていただいて、現場サイドから見た九州をちゃんと議論することが大事だと思うんです。九州1つになるべきだと一番思っているのは、実は現場の人だというのがあるわけですよ。その意見が反映されないのはもったいないなと思います。
点と点をつないで広がっていく
高島:行政が対応を変えるには、すごく時間も手間もかかります。そんなめんどくさいことはすっ飛ばして、現場が先に行動して、ソフトとしてつながったり、発信をしていく動きがとても大事だと思います。
石丸:そうですね。福岡市は、「WITH THE KYUSHU」(九州各地の自治体と連携し、九州の発展につなげることを目指したプロジェクト)という形で都市間をつないで、九州一体になってやられているんですけど、すごくいいですよね。統治機構を動かしてくということよりも、各都市のニーズに応じて福岡市が支えたりとか、連携して価値を創っていくみたいな素地がすでに九州にあるなーってことは思っています。ああいった都市間連携みたいなもので、点と点でつないでいたものがいずれ広がってた、みたいな流れができてくるといいですね。

日野:僕も『Qualities』でいろんな方々を取材させていただいていて、各県にいらっしゃる、僕も知らなかっためっちゃ面白い方々を、次に会ったこれまた面白い方々に話してくと、「その人ちょっと紹介してください」みたいになったりします。そうやって、九州という1つの箱を見つめた時に、ただ佐賀だけとか福岡だけで見てるものとは違うものが生まれてくる可能性があるので、九州を取材して回る『Qualities』というメディアで出会った方々を混ぜ合わせて、新しい面白いことが起こるような箱にしていきたいなと僕も思っています。
高島:ヨーロッパでは、国民国家の形成に、新聞が大きな役割を果たしたという歴史があります。印刷技術ができて新聞ができて、みんなが同じものを読むことで、あたかも同じように体験しているかのようになったんです。テレビもすごく影響力がありますが、放送エリアは県ごとなんです。放送と通信が今後融和するような規制緩和が始まり、九州エリアの番組ができたらいいと思います。
私は昔『アサデス。九州・山口』っていう九州ブロックで放送されている番組を担当していましたが、そういう広域エリアをカバーする番組がもっとできたら、意識が変わるんじゃないかと思います。今、県域ごとにあるものでも一緒に見ることで「俺たちのコンテンツ」という意識になり、みんなで知恵を出して、プロモーションは福岡のここが得意、生産は佐賀のここが得意、パッケージは宮崎のここが得意とか、うまく九州の中で結びついていったらいいなと思います。
日野:そうですね。あと、僕がWebメディアをやる時に困るのが、ライターさんがそんなにたくさんいらっしゃらないことなんです。
高島:そうなんですか、意外です。
日野:福岡は書く仕事が一定あるのでライターさんがいますし、熊本もタウン誌の文化が豊かだったからか、まちに密着して書ける人が結構な人数いるんですよね。でもほかの県だと、メディアがなかなか存在できていなくて書く場所がないので、ライターさんがいなくなっていくんですよね。そうすると、地域の眠れる資産に光を当てて文字にする人の総量がどんどん減っちゃうんで、そこがもったいない状態を生んでる1つの要因にもなってるんだと思っています。そしてそういう書ける舞台を作っていくっていうのもすごい大事だなと思ってるんです。じゃあ地方で書ける人がどこにいるかというと、基本的には新聞記者なんですけど、新聞って役割があって、フラットな目線であらねばならない。特定のものをいきなり応援するということはあんまりできなくて、ちゃんと報道として報じていかなければいけないミッションがあるんですね。今、日本全国いろんな地域が元気なくなっていて、いろんなことを応援しなきゃいけない時に、純粋に応援目線で伝えるということとかも、新聞はできにくいけど、誰かがやらないといけないと思うんです。
高島:たぶん、テレビは情報が映像と音から入ってくる、感覚に訴える感性のメディアなんですよね。一方新聞は、読む、知性のメディアですから、人の裏側とか努力とか汗を伝えることは、ひょっとしたら新聞のほうが得意かもしれないですね。
みんなでまちをつくっていく
高島:いずれにしても、チームで力を合わせていかないと、日本全体・九州全体では人口減少はもう始まっている。どんどん進化していく技術・テクノロジーをうまく活用しながら、これまでの延長線上ではない、新しい化学反応で、これまでになかったようなサービスや価値を作り出していかなくちゃいけないんです。その時に福岡が社会実装できるようなチャレンジをしたりとか、あと石丸さんがされてるようなFDCみたいな組織が仲立ちをして、いろんな人をつないでいくということがすごく大事になってきますよね。
日野:そうですね。なんかまちを作るプロセスっていうのが、みんなで共有できるような感じになっていけるといいのかなと思って。さっき聞き忘れたことを1つ思い出したんですけども、箱崎の九大跡地をまちにする“Fukuoka Smart East”についてなんですが。ここもポストコロナのまちづくりというところで非常に可能性があって、1つのデベロッパーが計画して作っていくというより、住民とともに作ろうみたいなことになるのかすごく興味を持っています。
高島:まず、地域の人たちとかと勉強会・研究会を立ち上げて、外の地域の人の意見を聞いて、それからこのエリアをどういうゾーニングにしていこうかという話をしてきました。それから、落合陽一さんはじめ時代のトップを走っているみなさんに入っていただいて、どんな“スマート”を実装していくのかを考え続けています。そして、これが全部出揃ったところで、両方の意見を段階に応じて取り入れていくという感じですかね。
石丸:そうですね。住民との接点とか、住民を踏まえてみたいなところは当然あると思います。そもそも、昔ながらの住民もいらっしゃるんです。そういった意味で2つ要素があって、1つは地域住民も含めた、福岡市民の課題やお困りごとを解決していくスマートシティという側面ですね。これは社会課題解決型のスマートシティをやっていくためのソリューションを実装していくことを視野に入れたものです。もう1つは、福岡がアジアのリーダー都市になっていって、九州全体を引っ張っていく拠点としての側面が当然必要だと思います。
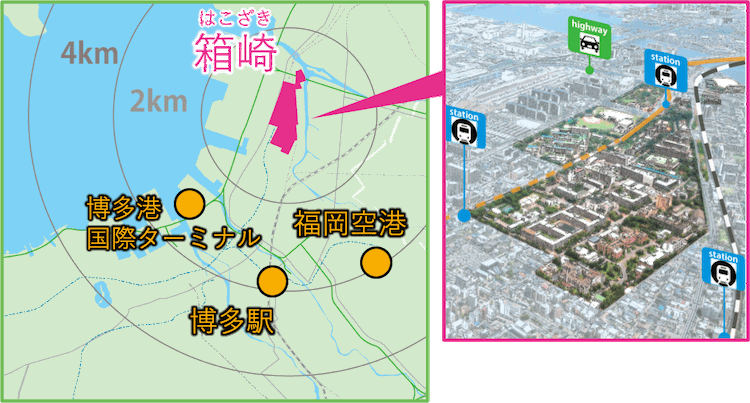
石丸:いろんな地域で、福岡が独り勝ちだって結構怒られたりするんですけど、でもどっかが尖って、世界に冠たるまちになっていかないと全体のボリュームを失っていくんですよね。そのために、福岡に人とか富を集めていくことが重要で、これをいかに九州に、福岡だけじゃない富とか需要を作っていくかも1つの福岡の役割なので。その2つをどうやって折り合いをつけて新しいまちづくりをしていくかですね。新しいスマートシティって、どんどんアップデートされていきますので、新しいサービス開発みたいなものを地域の人が関わっていけるような場所分けであったり、最先端の動きがいち早く感じられる場所があったりとか、しっかりと一緒にやっていきながら地域を持続可能にしていく仕組みができていければいいなと思いますね。
高島:スマートシティというと、「若い人たちで機械がいっぱいのまちをつくるわけ?」みたいに言われることもあります。でもそうじゃないんです。スマートシティだろうとなかろうと、基本的にはほかの地域と変わらない、自助・共助・公助の、人と人とのぬくもりのあるまちを作っていくんです。ただ、今せっかく便利なものがいっぱいできていて、例えばこれからの高齢化社会、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃんが徘徊したらとか、子供が行方不明になったらとか。こういうことがあっても、例えばセンサーがまちにあれば、ちゃんと居場所が分かるとか。
今あるまちに組み込もうとすると大変なことでも、新しいエリアであれば最初から作ることができます。だから、普通のまちと変わらないけれど、そこにプラス、便利なものを最初から使えるまちに設計することができるんです。コロナ対策を前提にしたまちの設計もできる。安宅さん(慶応義塾大学安宅教授)は、人類の最高の発明が都市だとおっしゃいます。しかし効率的な今の都市ですが、パンデミックには弱かったということが今回よく分かりました。次に新しく作るまちだったら、感染症対策もしっかりできる構造にしようとか、これから絵が描ける。まさにこれからのモデルになる、素敵なまちができたらいいなと思っています。
日野:そうですね。僕も福岡市の南区出身なので実は東区にあんまり縁がなくて、今年になって初めてゆっくりと回ってみたんです。九州大学が長年そこにあったおかげで、昔ながらのお店なんかがかなり残っていて、まちの風情がすごくいいんだなということに気付いて。そこにスマートシティが出来上がっていく中で、いま箱崎に残っている魅力的な感じと、新しくできるエリアが、どう交わっていくのかなというのをすごく楽しみに思っています。
次の福岡を見据えて
日野: FDCの立場で石丸さんが考えるこれからの福岡とか、次のテーマみたいなこととかって何かありますか?
石丸:これまでの福岡都市圏の10年間は、一言で言うと経済のパイを増やして経済的な利益を享受できる人たちが増えてきた10年だと思います。今後の10年、FDCが考えていかなきゃいけないのが、一人ひとりにフォーカスしていくことです。なので、次のステップに行く時は、全体のボリュームというよりは、一人ひとりの暮らし方や働き方にフォーカスして、暮らしやすさとかリバブル(住みやすい)であるみたいなところを実感として作っていきたいです。
もう1つ僕が重要だと思うのは、スタートアップなんですね。この政策の一番すごかったところは選択肢が増えたことだと思うんです。例えば、九州大学で起業部が出てきましたけど、親からすると大手企業の社員とか官僚になってほしいって思ってるのに、その息子・娘が急に、「いや、俺起業するばい」みたいなことを言い出すのって、すごいパラダイムシフトだと思うんですよね。コロナでどんなにワークスタイルがパラダイムシフトだって言ったって、基本的なマインドセットが変わらない限り多分進まないんです。でも福岡は、もう5年以上前ぐらいからパラダイムが変わっているんです。若い人たちが高校や大学を卒業したら、起業みたいなことが選択肢に入ってるってことはすごいことです。そういった働き方の人生の選択も多様なまちを今後作っていくというところです。
高島:今は福岡を次のステージに持っていくチャンスです。天神ビッグバンにしても規制緩和とインセンティブによって30棟の民間ビルが建て替わる目標だったのが、実際には70棟ぐらい建て替わります。ハード整備中心の再開発プロジェクトと思われているかもしれませんけど、本質はソフトなんです。中にどんな企業が入るか、どういう機能が入るかというところがすごく大事です。で、これまでは福岡は賑わっていると言われたけれども、でも実際に行くと、高付加価値のビジネスが集積できるようなハードがなかったんです。これから生産性を上げていくためには、高付加価値のビジネスがここに来るということが大事です。
実際に福岡に進出するという企業のお話もたくさんあります。今後、こういう発表が次々にありますので、「あーそういうことか」と分かりますよ。つまりハードが変わったからこそソフトが変わっていく、産業が変わっていくというようなことが起きてくると、ますますいい循環が生まれてくるのかなと思っています。
福岡の強みを生かした金融を考える
高島:今言われているのは国際金融都市についてです。香港やニューヨーク、ロンドンなどがありますが、福岡が目指すのはどこなのか。そういったイメージについて、今福岡の経済界のみなさんと石丸さんにも入っていただいて勉強会を開いています。だんだんとクリアになってきましたので、これも近いうちに発表したいと思います。(※2020年9月29日に産官学の国際金融機能誘致組織「TEAM FUKUOKA」設立)
国際金融都市を目指していく過程は、様々なグローバル企業が集積できる素地を作るうえで大事なチャレンジです。こうした目に見える目標の中で産学官民が一緒になって力を合わせて、福岡を次のステージに進めていければと思っています。
日野:僕は金融に全く明るくないので、香港やロンドンと福岡が、金融という1つの軸で戦える部分があるのかとか、何か持たなきゃいけない機能があるのかがまだ理解できていないんですけども、教えていただいてもよろしいですか。
石丸:福岡は、例えばスタートアップのプレイヤーがいたり、BtoC向けのサービスを担っている人たちがいたり、キャシュレスを推進されていたりとか、金融の一機能である決済の部分で推奨もされています。
目指すべき都市のイメージ像は、例えばメルボルンとかですね。シアトルもそうですが、こういう都市は結構QOL(quality of life:一人ひとりの人生の内容の質や社会的に見た生活の質)が高かったりします。QOLを大事にしていく中で、プレイヤーが最終的にそういうところに住んでいきながら金融に関わっていく新しいトレンドも出てきています。そうであれば、福岡の強みとか、これまでやってきた文脈の中で、金融をうまく絡めながら組み立てていければ、それこそ東京やほかの都市と比べても戦えるストーリーができるんじゃないかなと期待しているんです。
日野:なるほど。福岡市を作っていくベースの中で、これからの金融のあり方を再構築するというのは、すごく興味深い話だなと思いました。
高島:東京はもう国際金融都市ですよね。でも、福岡が強みを持てる金融都市のロールモデルも世界にはあります。今、福岡がスタートアップを頑張っている中では、最初からグローバルというところが大事なんです。スケールアップ、グローバルというのは、すごく大事な2大テーマなんです。そういう時に金融機能が弱い。上場する上での相談相手になるような人材が福岡に不足してるので、企業が資金集めをしてグローバル展開していくのがまだ難しい。ここを強化すると、いい環境が整ってくると思います。
持続可能な都市づくりを目指して
日野:最近はSDGsバッチをつけている方が世の中に増えていて、持続可能な社会をみんなが作ろうという意識が高まっています。
アムステルダムでも『アイ・アムステルダム』というキャンペーンがうまくいって、住んでいることに対して市民が強い誇りを持っている状況が強まっているらしいですが、そこにはアムステルダムのまちとしての環境への取り組みの良さも作用していると聞いたことがあります。福岡市と環境周りはどういう感じになるのかについてお聞きしたいです。
石丸:持続可能な社会、都市づくりが求められる中で、サーキュラーエコノミーみたいなものに、世界の都市がいろいろとチャレンジされてると思うんですね。福岡は、もともとそういうところをすごく大事にしていて、世界に貢献する立場にあった都市だと思います。
市民生活の中でも、スマートシティが進んでいくことと合わせて、ここに新しい価値観とか暮らし方とがセットで調整していける可能性が充分あるんじゃないかなと思います。
スマートシティのソリューションを通じてサーキュラーエコノミーに寄与することもあるでしょうから。
いずれにしても、世界のトレンドがある中で、事業化を含めて我々FDCとして考えていけたらと思っています。
日野:世界で最も大きい課題のうちの1つだと思うので、まちのつくりが変わる中で、僕のお里である福岡市がリーダーになってくれるととても誇らしいなと思います。
高島:明日の夜も、オンラインでSDGs関係のイベントに出席します。リバプールの首長とかサンパウロの首長など。日本からは私が出席しますが、国連ハビタットの事務局長も出席して、都市間連携について発表する予定です。
福岡を考えるんだったら日本を、日本を考えるんだったら、世界を考えてないといけないと思います。世界の先進事例なども吸収しつつ、しっかり存在感をもって、発信していきたいと思います。
日野:僕も何らかの形で社会実装に関わりたいと思っているので、ぜひよろしくお願いします。
なぜ働けるのか
日野:質問がきています。日々馬車馬の如く働かれている高島さんと石丸さんの原点や心の拠り所とは何でしょうか。
石丸:『福岡市を経営する』を読んだら、だいたい書いてあるんですけどね。拠り所、心構え。
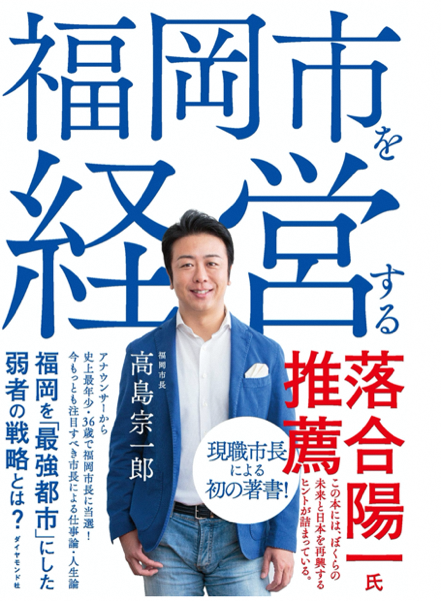
高島:宣伝いただいてありがとうございます。元気や体力があって話そうというモチベーションが湧いている時期はそんなに長くはないと思うんですよね。人生は80年か100年かもしれないけれども、自分のピークの時間というのはそう長くないんで。そう考えたら、今せっかくこうやってできる状況にあるんだったら、自分で働かないと罰が当たるというか。能力で言ったら私の1万倍優秀な人がたくさんいる中で、自分が今こういう位置にいてこういうことができているということは、やっぱりあんた何かしなさいという役割があるんだろうから。
日野:ありがとうございます(笑)。意外な方向性のコメントが出てきて、非常にしみわたりました。
石丸さんは、どうやってあの量の案件をこなしているのか、あの量の人とやり取りをしているのか、ThinkだけじゃなくてDoもやっているのか、僕は未だによく分からないなと思っているのですが……。
石丸:そう聞かれるとどう答えていいのかよく分からないんですけど、今のポジションで絶大なる信頼をしていただいて、こういった大きな役割をさせていただいてることに対してもう感謝しかないんですよね。ただ1つ思ったのが、やっぱり現場のことは現場で決めていく国にしたいという理由で経産省を辞めた立場としては、それを生まれ故郷の福岡でぜひやりたいっていうのが大きなモチベーションなのかな。自分のために頑張ることができないなーって思うんですけど、人のためだとなんか頑張れるっていうのがあって。そういった環境を与えられてる、役割が与えられてる間は、全力で頑張りたいと思います。
日野:ありがとうございます。本日は福岡市の勢いの一角になっているFDCという謎の組織の謎の事務局長・石丸さんが何をやってるかというところを解き明かしたいというのが1つのコンセプトだったんですけども、それを高島さんと共に取り上げていくという贅沢な時間だったなと思います。ちょっと長くなりましたけども、ありがとうございました。
あとがき
『おいしいもんと気のいいおっちゃんたちのまち、福岡。ずっと前に一度訪れてから、同じ印象を持ち続けていました。そんな福岡が知らないうちにアップデートされていて、ああなんだか、気のよさはそのままにスマートでやり手になった同級生に再会した気分です。
私は東京で暮らしていますが、関東圏として括られても他の県に対して仲間意識はあまり感じません。そういう意味で九州は、あの大きな島が一体感を持ちつつ、福岡が引っ張っていくという不思議な力強さがあり、それが今の急成長を支えているように思います。
どんどん変わっていく福岡、そして九州にまた会いに行きたくなりました。』
(法政大学藤代研究室 青柳美里)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






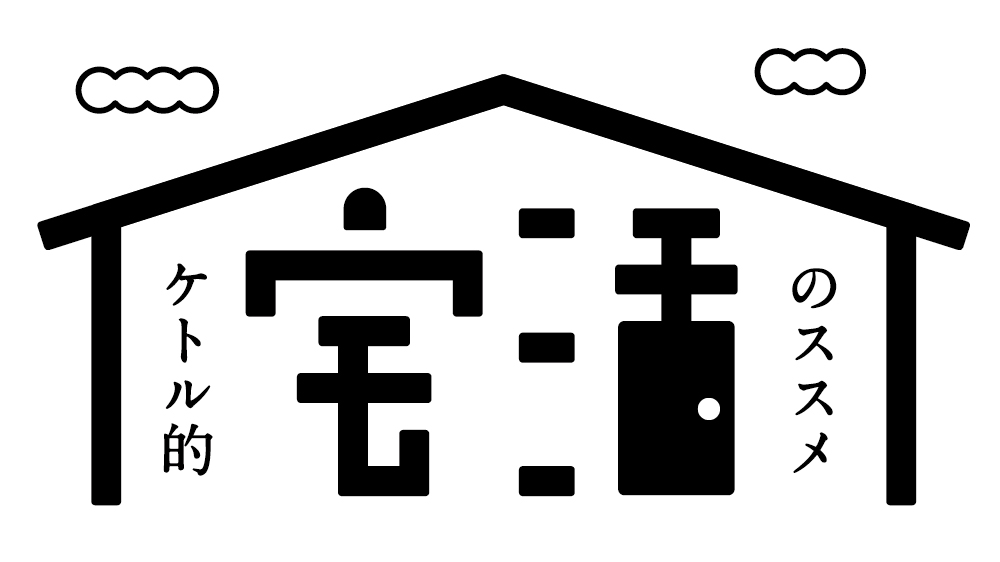

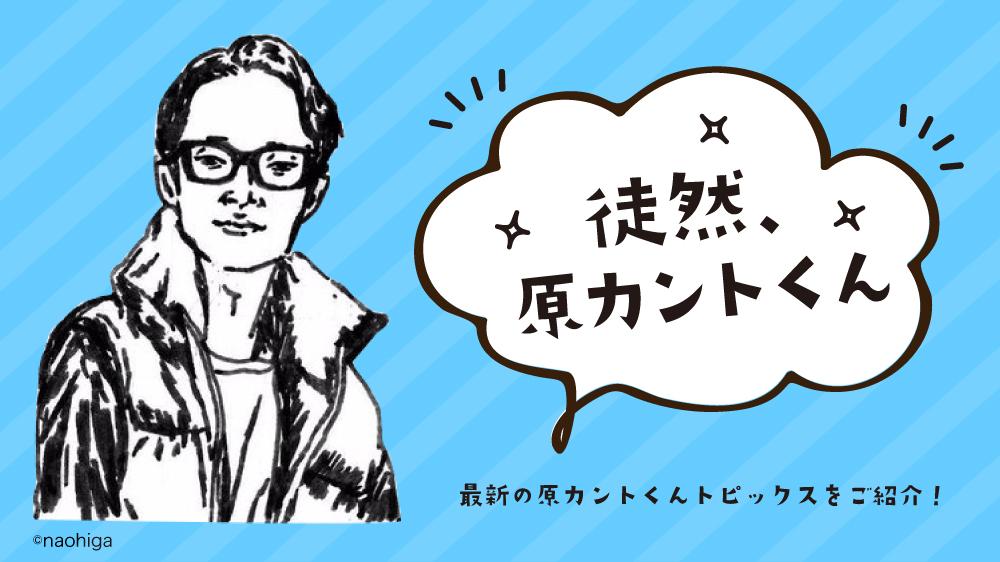

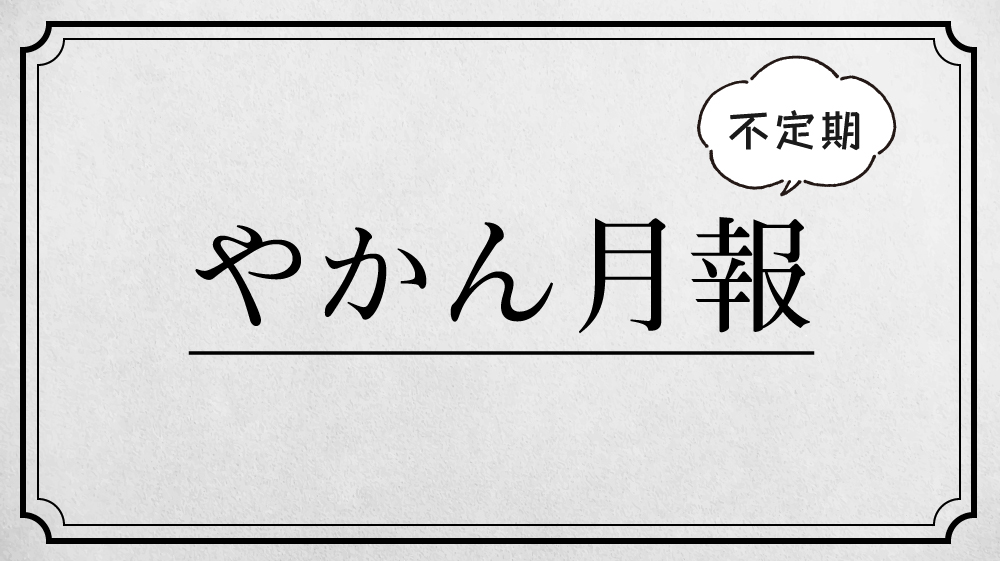
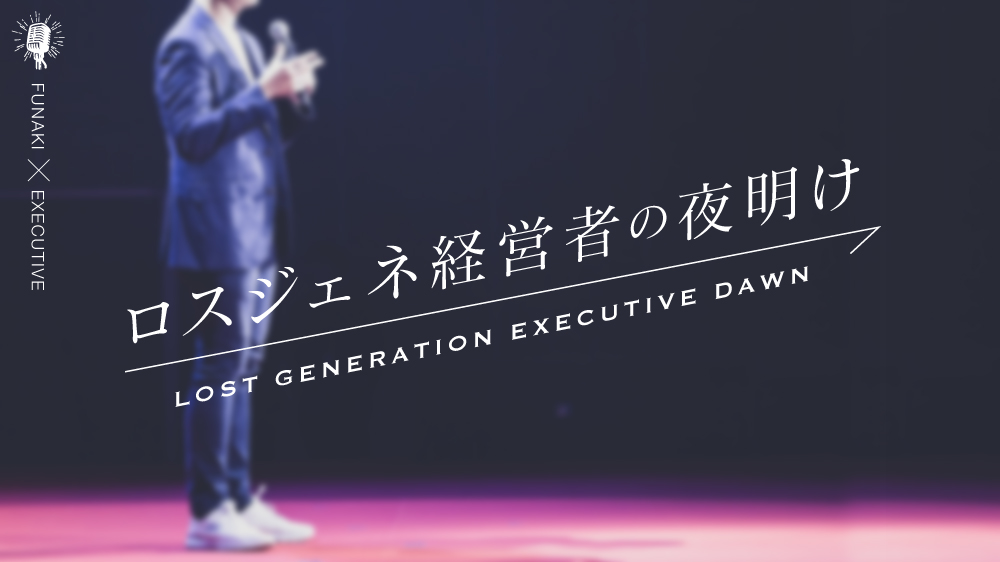

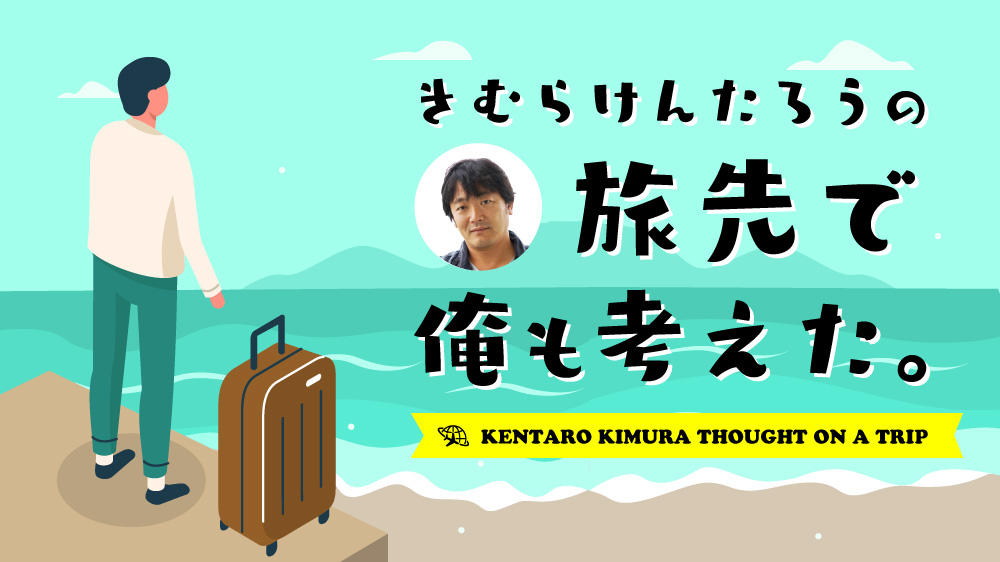

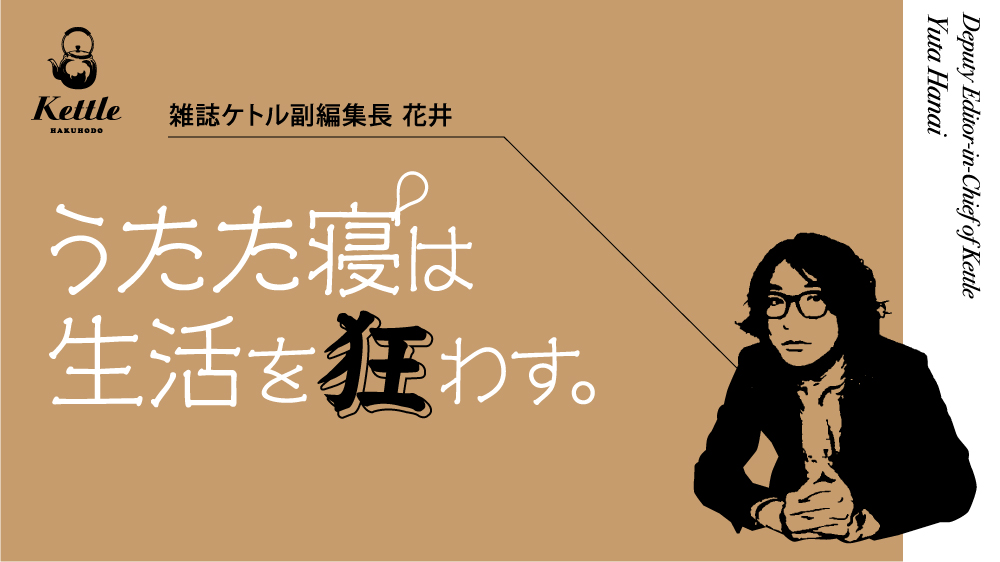






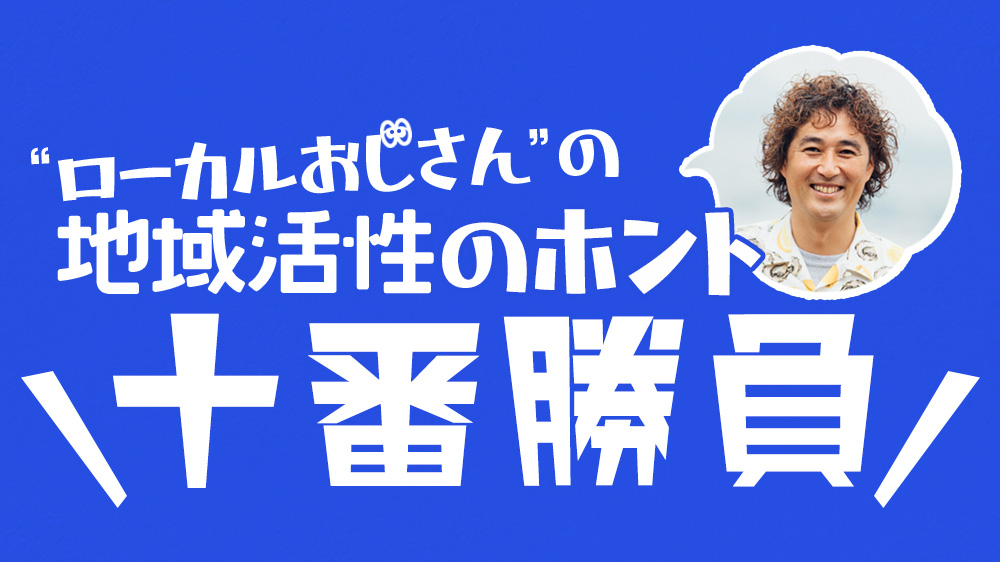
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧
「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター