2021/04/13
“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.6 七咲友梨×田中輝美×日野昌暢「ローカル発 新しいメディア、どうつくる?」『みんなでつくる中国山地』(中国山地編集舎)刊行記念 前編
 日野昌暢
日野昌暢

博報堂ケトルの“ローカルおじさん”こと日野昌暢が、本質的な地域活性を考え、実践する方々を本屋B&Bのオンラインイベントにお招きしたローカルシリーズ十番勝負の6戦目です。記事は法政大学藤代裕之研究室の学生がまとめています。昨年『みんなでつくる中国山地』が発売されました。
同書は、過疎の発祥地とされる中国山地から「過疎は終わった!」と提唱し、なぜ過疎が終わったと言えるのか、データ分析や現地取材、大学生の座談会など多角的に迫った一冊です。
中国山地生まれで、今回写真撮影を担当した写真家の七咲友梨さん、中国山地編集舎の発起人で中心的に企画・執筆したローカルジャーナリストの田中輝美さん。聞き手は、『絶メシリスト』のプロデュースで知られ、ローカル発Webメディア『Qualities』を立ち上げたばかりの博報堂ケトルの日野昌暢が務め、参加者とともに語り、考えます。
七咲友梨(ななさき・ゆり)
島根県出まれ。リアリズム演技を学び、役者として映画、ドラマ、舞台、CMなどで活動。その後、写真家・横木安良夫氏に師事、独立。ポートレイトや旅の写真を中心に雑誌、広告、書籍、webなどの分野で活動。CM、ミュージックビデオ、映画などの映像カメラマンも手がける。松浦弥太郎氏(エッセイスト)初監督作品の映画「場所はいつも旅先だった」では映像・写真の撮影をし、2020年に公開を予定している。また写真集制作、写真展など作品発表も行い、2019年秋にキヤノンギャラリー銀座・大阪にて個展「朝になれば鳥たちが騒ぎだすだろう」開催。同名の写真集も1.3H/イッテンサンジカンより発売。また、地元島根県西部地方にある「かきのき村」にてつくられるお茶を、地域の方と一緒に作るプロジェクト「ソットチャッカ」を2017年に立ち上げた。
田中輝美(たなか・てるみ)
島根県生まれ。山陰中央新報に入社後、ふるさとで働く喜びに目覚める。琉球新報社との合同企画「環(めぐ)りの海」で2013年新聞協会賞。2014年秋、退職し、ローカルジャーナリストとして島根に暮らしながら、地域のニュースを記録、発信する。著書に『地域ではたらく「風の人」という新しい選択』(ハーベスト出版) 『ローカル鉄道という希望』(河出書房新社)『関係人口をつくる−定住でも交流でもないローカルイノベーション』(木楽舎)など。
http://www.tanakaterumi.com/

(写真:左から時計回りに 七咲友梨さん、田中輝美さん、日野昌暢。以下敬称略)
自分の一番身近なところから
七咲:七咲友梨といいます。写真をやっておりまして島根県の益田市で育ち、生まれたのは柿木、吉賀町柿木村地域です。
日野:柿木村地域、すごいですね。
七咲:そうですね、合併して吉賀町になったんですけれども。おばあちゃん家が柿木なんで、島根にいる時は柿木に帰っています。普段は写真をやっていて、モデルさんを撮ったり、ポートレートを撮ったり。各地域に行ってそこのお店を撮ったりすることもあるし、料理のページを撮ったりする事もあるし。
日野:七咲さんは、撮るときに自分がお持ちになっているテーマ性みたいなものはあるんですか?
七咲:去年『朝になれば鳥たちが騒ぎ出すだろう』という写真集を出しました。それはオーストラリアに旅に行って撮った写真なのですが、一旦、旅モノとかはそこで自分の中では区切りが付きました。

7、8年ぐらい前から島根の実家のあたりを撮っていて、次はそれをまとめたいなと思っています。今『みんなでつくる中国山地』にも関わらせていただいて、ますますそっちの方に気持ちが向いているという感じですね。
あともう一つだけ。『ソットチャッカ』という、そっと着火するという意味で名前をつけたお茶のブランドを3年前から始めて。それは柿木に住む家族とご近所さんと一緒にやっています。

日野:なるほど、じゃあ20年離れている割にはすごく地元やご実家とかに関係して、写真撮られたり、作っているものをブランド化されたり、しているんですね。
「ローカルジャーナリスト」として生きていく
田中:私は島根県から出演しています。島根県の浜田市というところで生まれて、今も浜田市に住んでいます。
1回大学で県外に出た後に戻ってきて、山陰中央新報という新聞社に勤めました。地方紙の仕事は大好きだったんですが、もっとやってみたいなーと思って、独立しました。よく「東京に出るんだ、頑張ってね」と言われるから、いやいやいや、島根でやるんだよ、と分かってもらうために自分でローカルジャーナリストという名前を作って、今も島根でジャーナリズム活動をしています。
独立して6年、単著と共著で今8冊かな。なるべく、毎年1冊ぐらいは世に送り出したいなと思ってやっています。

日野:ほとんど島根に関わっている本だということですかね。
田中:そうですね。この中の『地域で働く「風の人」という新しい選択』は日野さんと出会うきっかけになった本ですね。
日野:僕がこの本を読んだところから輝美さんに会いに行きました。
田中:風の人というのは、風土という言葉から来ています。風土という言葉は土の人と風の人が合わさって風土。土の人、根付く人は大事だけど土の人ばっかりじゃなくて、去るかもしれないけど、風の人も大事だよということが書きたかったんです。風の人という民俗学で言われてきた言葉をクローズアップして、島根で働く人たちを書いた本です。これは藤代さんとそのゼミ生たちと一緒に書いています。
それと、『関係人口をつくる』という本は今1番知られているかなと思います。最新作がこの『みんなでつくる中国山地』です。
離れていてもできることはある
日野:関係人口は国の地方創生の中でかなり上位のキーワードになっていますよね。こういう言葉を生み出す、概念を生み出すというのはそうたやすくできることではないので、みんなが使っている言葉になっていて本当にすごいことだなと思っています。
田中:『関係人口をつくる』という本は、関係人口による地域再生のことを書いたつもりです。私が常に関心があるのが地域再生。島根県は過疎の発祥地で、ずっと再生や活性化に失敗してきたと言われていて、そんな地域が再生するってなんなんだろうとか、人口減少時代の地域再生ってなんなんだろうということに関心があります。教育、鉄道、よそ者、関係人口とかいろいろなアプローチで地域の再生を常に追いかけています。
日野:ありがとうございます。輝美さんの言葉で関係人口とは何かということに触れてもらってもいいですか?
田中:はい、そうですね。関係人口は、観光以上定住未満と言われることが多くて、観光客よりも関わるけど、定住まではしない人たちのことです。今まで地域と人の関わり方って観光客として消費しに行くか、一生住むみたいな骨を埋める覚悟、の2つしかなくて。すごくもったいないなって。離れていてもできることっていっぱいある。本質からずれた議論もいっぱいあるんですが、まあ言葉が広がるってそういうものだから、それも許容しながら良い事例が作れたらいいなと思っています。
地域に長く伝わるものを伝えていく
日野:『みんなでつくる中国山地』という雑誌が創刊しましたということで。輝美さんの手元に本はあるんでしょうか。
田中:それが手元にあるやつは全部売っちゃって。出会う人、出会う人に持ってないの? 持ってないの? と言われて、ある! とか言っていたら全部最後まで売ってしまって。今日ない! と思って! ではちょっと写真だけ。

日野:創刊号の表紙なのですごく意味があると思うんですけども、これは何ですか。
田中:これは実は絵でして、廻り舞台です。
日野:廻り舞台というのはなんでしょう。
田中:舞台が回るんです。地元の演劇ですね、地芝居。そこの廻り舞台、そこを開くと、実物の写真が出てきます。
日野:地芝居という言葉を初めて聞いたんですけど、一般的なんですか? 島根にはどこの街にも地芝居があるんですか?
田中:各地に結構あると思いますね。そうやってずっと続いてきている地域の文化を大切にするという意味で表紙にしています。
今こそ革命の時代
日野: 100年続くメディアの作り方も気になるのでそこにも触れていきたいんですけど、副題の「過疎地から始まる暮らしの革命記」というところに、『みんなでつくる中国山地』への想いがこもっていると思うので、2人にそれぞれお聞きしたいなと。
七咲:東京に住んでいて必ず聞かれるのは、出身地はどこかという話じゃないですか。「島根です」と言うと、「九州だよね」「行ったことあるよ、鳥取砂丘」とか、多くの人が島根の場所を知らないんです。
これは本当に島根県民あるあるなんですけど、私たちはすごく寂しい思いをしていて。親の世代も「こんな場所」とよく口にしているんですが、実はそんなことないぞということがここにきて浮上してきて活力を得ています。暮らしの革命記ですね。
日野:そんなことがないということに気がついたということですか?
七咲:私の場合は移住者の方々から逆に地元の良さを教わって、自分が気づいたという感じです。
日野:すごく大事ですよね。外の人たち、風の人。
田中:過疎地と書いて「ここ」と呼んでいます。中国山地が素晴らしいとだけが言いたいわけではなくて、中国山地は過疎地の発祥地であり先行地域だから、中国山地で起こっていることはこの先ほかの地域の皆さんでも関係があるし、みんなもこうなる可能性があるよと思っていて。そういう意味でどこからでも始められるし、他のみなさんにとっても、ここから始められるよということが言いたくて、「ここ」と表現したんですね。
もう1つ何が変わっていっているのかというと、結局暮らしなんじゃないかと。この本は元々ポスト2020。オリンピック後の日本は大変になるから、みんなで考えるものを作ろうというのを最初目指していたんです。それがポストコロナに、意味合いとしてはもうwithコロナに変わっちゃって。1足飛びに早く来たなあという感じがあって。
みんなが何を1番考え始めているかというと暮らし。そこが変わってきているし、変えなきゃいけないという時に、どんなメッセージがいいかというと、革命かなと。革命は、割と思想的に右左みたいな文脈で取る人もいて心配する声もあったんですけど、思い切ってここから始まる暮らしの革命記に決めました。
県境という砦を超えたから見えたもの
日野:いいですね。関係人口という言葉もそうですし、そこから具体的に島根じゃなくて中国山地になったところが興味深く思っています。
僕も九州というテリトリーで『Qualities』というメディアを始めるのにこだわっていて。福岡のメディアでも良かったかもしれなですけど、行政と一緒にやっていたので、福岡の経済圏に暮らしている人でも住んでいる場所とか会社の登記がそのエリアに無いと扱っちゃいけない、みたいになることがあって、少しもどかしかったんですよね。もったいないなと思って。
新幹線が通って、鹿児島とか、隣町に住んでいるぐらいの距離ですぐに会いに行ける。そこに、面白い人たちがいる。この九州という島をもっと面白くできる仲間がいるのを可視化した方がいいなあと思って、僕は九州というテリトリーにしました。でも『みんなでつくる中国山地』は中国山地という山地で括っているので凄く珍しいなあと思いました。
田中:本当にうれしい。
日野:輝美さんが中国山地始めたから、あ、これだと思ったんですよ。中国山地というところにした想いとかもお二人に聞いておきたいです。
田中:日野さんが九州のメディアを立ち上げたという時に、これからは広域だよね、みたいな話で盛り上がったのを覚えているんですけど。ここには2つ意味を込めていて。1つは私個人の想いとしても、島根人口減少がずっと進んでいて、県が最後の砦としての壁になっている。コロナも結局県境の壁が最後残ったじゃないですか。
日野:はい、ありましたね。
田中:でもそれだけだと持たないよねと思っているところもあります。もっと広くつながっていかんといかんなあと昔から思っていました。今回改めて中国山地で設定したのは、中国山地自体が過疎で貧しくて大変なところ、みたいなマイナスのイメージがあったので、それを変えていきたいなーという想いがあって。
過疎の最先端だからこそ、逆にここから始められるというか、最先端の動きが始まっている。そこのひっくり返しみたいなところもあって、中国山地にこだわりたかった。
その結果よかったなと思うのは、視点の転換というところ。中国山地は奥の方とか山の方とか辺境だと思うんですよ。都市側から見たら僻地なんですよね。でもそうじゃなくて、この暮らしの現場である私たち。ここから中国山地に立って見た時のつながり、1つの同じ文化と背景を持った連なりとして捉えたときに、全然景色が変わって見えて。つながりを意識できて仲間がここに居ると思えたのが1番嬉しいと参加してくれた人は言いいます
。
日野:本当に大事なことですね。
田中:広島とか島根と括っていては見えない、同じ背景、文化、共通の仲間の基盤みたいなところが、「中国山地」で設定したことで見えてきたというのはすごく 面白いと思います。ここにみんな仲間がいて、あの山の向こうにも連なりがあって…と思えるようになって。本当にその地区に彩りがあるように景色が感じられるようになりましたね。
地元の人が教えてくれる面白い人に書いてもらう
田中:すごく贅沢な本になったなと思いますね。写真は本の印象を決めるし、1000キロの旅も撮ってもらってね。
日野:1000キロの旅ってなんですか?
七咲:中国5県をぐるっと1周回るとちょうど1000キロだったということで、1000キロの旅という名前をつけて各地で面白いことをやっている人に会いに行ったんです。
日野:なるほど、面白い人はどうやって探すんですか?
田中:それがですね。ローカルジャーナリストの人たちに、今までのつながりを辿って地元の面白いこと教えてくれませんかと聞いて回ったんです。私も島根のこととか中国5県のことを見ていたつもりだったけれども全然知らない情報が出てきて、各地にローカルジャーナリスト必要だなと思って。
「この人は面白いよ」とその人たちが教えてくれました。最初は人のつながりだったんですけど、そこからどんどん広がっていって、「こんな取り組みあったんだ!」というのは地元の人が1番知っているなと思いましたね。
日野:輝美さんのような人でも、まだ知らない面白い人がうじゃうじゃいるということですね。
田中:そう。そこが発見だった今回。
七咲:本誌の中で、地元の方々に書いてもらっている企画の部分があるんですけど、そこがすごく良かったですね。
日野:地元で見つけた面白い人が書いているということですか?
田中:そうそう、だからローカルジャーナリストの書き方講座をやって書いてもらいました。目次を見ましょうか。
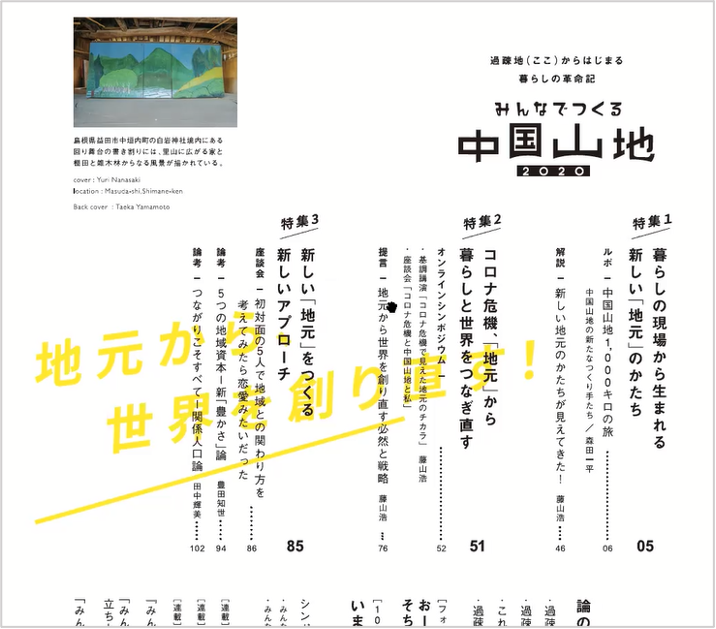
100年続けて中国山地で起こっている新しい営みを記録していこうという本なので、毎年今起こっている最新の面白いローカルのニュースを5県の書き手、ローカルジャーナリストに書いてもらうのが、企画の1つの大きな柱になっています。各県6つずつ、ローカルジャーナリストたちが「ここ面白い」「あそこ面白いよ」って言って書いてくれました。
七咲:やっぱり住んでいないと見えない小さなこと、活動とかも拾い集めている感じがして。あー各地にも面白いことやって、豊かに暮らしている人がいるんだなーということがすごいリアリティを持って伝わる企画になっています。
日野:なるほど。書く舞台ができれば、掘ろうとするし見つけようとするし、なんとか伝えたいと思うことが始まるんだと思うので、そういう意味でローカルのメディアはすごく大事ですよね。
地元のプレイヤーが地元のストーリーを発掘する
田中:関わってくれている人も、地元のプレイヤー(NPOや小さな食堂をやっているなど、実際に活動している人)に書き方を学んで書いてもらったんですよ。
日野:尊いな。
田中:結局その人たちも今までプレイヤーとして地域で気になることがあっても、取材ができないわけですよ。書くところがないから。「ところでなんでこのお店始めたんですか?」とか聞けないですよね。でも『みんなでつくる中国山地』で書くという言い訳ができたら、初めて突撃して詳しく聞いて、背景とが分かって面白かったと口々に言ってくれました。
あと、暮らしを衣食住に分解したときに、食と住は割とローカルにあると思うんですよ。だけど衣ってなかなかまだ海外勢が強くて難しいなと思っていたんですけど、『ちずぶるー』という、鳥取県の智頭で地元の人たちが地元の藍染をやっているのを探してきてくれて、すごくよかったです。

田中:後は、そうそう! 『過疎ビール』というのが発売されたんですよ。すごくないですか?

日野:ハハッ。過疎ビール! なかなかいいですね。
七咲:うん、美味しいです。
田中:すごく時代が変わったなと思っています。伝統は素晴らしいし、守ってきた人たちがいるから大事にしたいけど、それをふまえて新しい息吹を吹き込んで、新しい価値を出しているという取り組みをなるべく取り上げたつもりなので、『過疎ビール』はその典型かなあと思います。
七咲:「霧に包まれた向こうの人」みたいな感覚だったのが、「ああこういう風に生きているんだな、楽しくやっているんだなあ」とイメージできるのがすごくいいことだなと思いました。
日野:その人たちも、楽しく暮らしているつもりもなければ、霧に包まれているつもりもないですよね。日常だったりするのかもしれないですよね。でも、外の人がそれを面白いと言って、客観的な視点によって編集された時に、価値を放つみたいなことはもう死ぬほど日本中に転がっているんでしょうね。
七咲:まさに、私がお茶をやり始めたのも同じ理由です。各家庭で飲むお茶って、自分たちで作っていたんですよ。でも買った方が安くて作らなくなってしまって。「釜炒り茶」という窯で炒るお茶なんですけど、少しずつ各地で作り方が違っていて、九州の釜炒り茶とはまた違う風味のお茶ができています。
「こんなもの売れるんか?」とおじいちゃんおばあちゃん達が心配しているけど、すごく面白いしおいしいし。みんなオリジナリティを探しまくるけど、実は足元にすごくたくさんあるんだなと思いました。
田中:その話も次号にはぜひ書いていきたいですね。
(中編に続きます)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






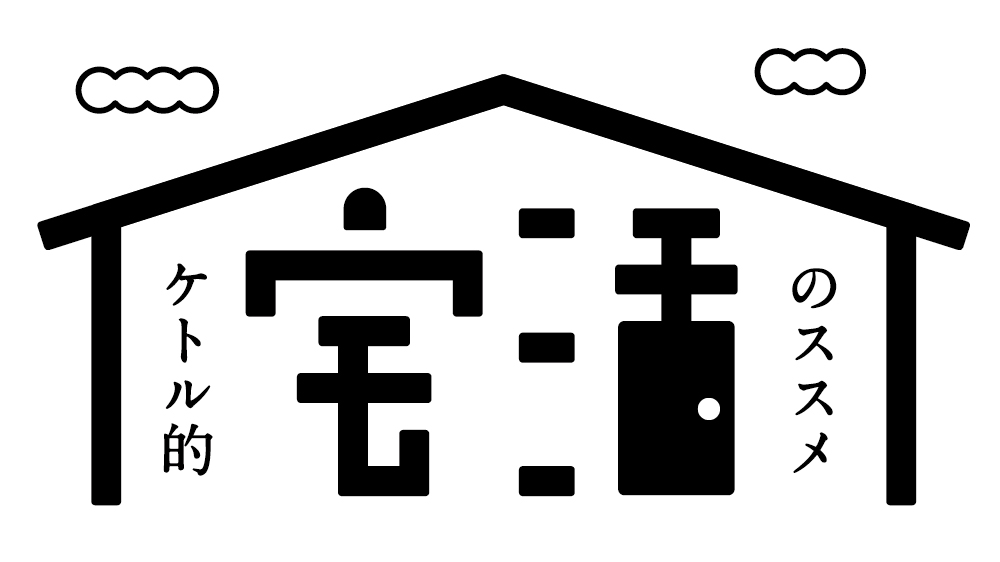



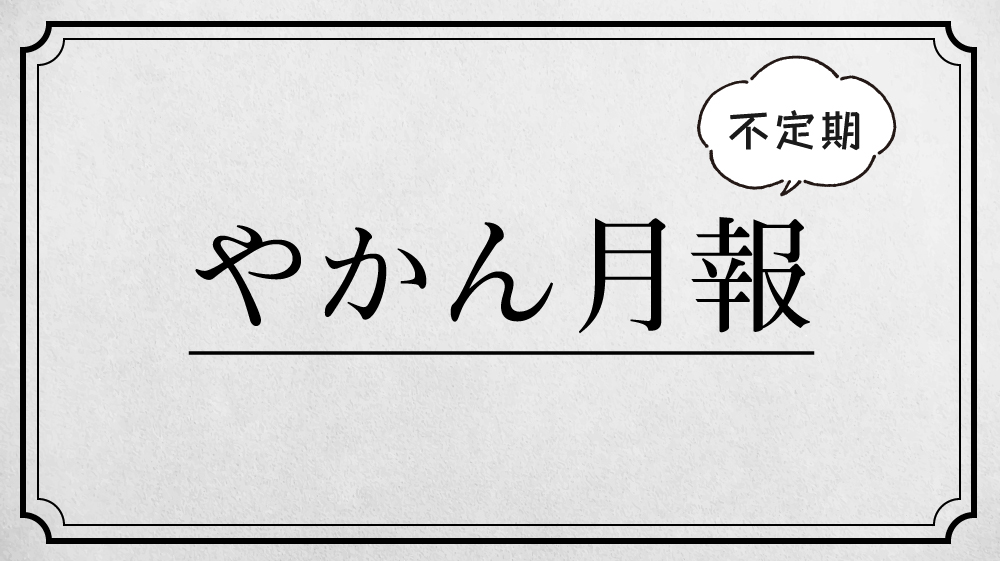












 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧
「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター