2021/04/13
“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.6 七咲友梨×田中輝美×日野昌暢「ローカル発 新しいメディア、どうつくる?」『みんなでつくる中国山地』(中国山地編集舎)刊行記念 中編
 日野昌暢
日野昌暢

“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.6
七咲友梨×田中輝美×日野昌暢 前編はこちら▼
“ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負 vol.6
七咲友梨×田中輝美×日野昌暢「ローカル発 新しいメディア、どうつくる?」『みんなでつくる中国山地』(中国山地編集舎)刊行記念 前編

(写真:左から時計回りに 七咲友梨さん、田中輝美さん、日野昌暢。以下敬称略)
当事者と第三者の二つの視点から書く
日野:100年続くメディアの作り方ですが、輝美さんは100年生きないですし、メディアを作るには誰かが書かなければいけないですね。ローカルには実は書く人がいないんですよね。『Qualities』でも、大分、長崎、鹿児島とかに行くと、書く人を見つけるのが大変だったんです。それは書く場所がないからというのがすごく大きいんですね。
メディアがあることで書ける人たちが舞台を持って、仕事にし始める人が増えるということも必要だなと思っています。以前に輝美さんが作られた『ローカルジャーナリストガイド』は、もともとそういう課題意識から作られたのかなと思うんです。

日野:いろいろな土地にいる人たちが、ローカルジャーナリストになるために何をしなければいけないか、取材の基本とは何かとか、そういうことがまとめられていたと思うんですが、それを使って『みんなでつくる中国山地』を地元の人たちに書いてもらうということを、挑戦しているということですよね。
田中:そうですね。今回の本でチャレンジしてやってみたかったことが、特集1にあります。西粟倉という岡山の有名なところを、事務局長でジャーナリストの森田さんが書いてくれています。そして、森田さんの視点から見た西粟倉と、西粟倉の地元の人たちが自分たちの視点から見た西粟倉を書いてくれているんですよ。
それも中国5県でやるようにしていて、私は、当事者だから書けることと、ジャーナリストとか第三者だから書けることは全然違うと思っています。なので、2つの視点から書いて、立体的に地域を見るということを昔からやってみたかったんです。

ローカルジャーナリストの可能性を感じているのは、書くことだけトレーニングしてきた人より、プレイヤーの人たちです。プレイヤーの人たちが、ちょっとしたコツでファクトを書けるようになる方が、目指すローカルジャーナリストに近いです。創刊準備号は4人でしたが、創刊号では執筆者の欄がダダダダッと長くなって、本当に嬉しいです。
「活性化気持ち悪い」から考える地域との向き合い方
日野:それではここからは進行役を七咲さんの方にお渡しして、やっていければなと。
七咲:はい。お二人とも若い方とか大学生とかとも活動されていますが、何か感じることはありますか?
田中:若者の座談会で「活性化気持ち悪い」というパワーワードが出てきて、やっぱり若者の本音は面白いなと思って。彼らは、地域にハッシュタグが欲しいっていうんですよ。
結局、自分たちの確固たるアイデンティティみたいなものが持てなくて、ハッシュタグの寄せ集めだと言うんですよね。私だったら#島根、#鉄道みたいな。そこで合う仲間と会うみたいな。だからハッシュタグがある地域だと関わりやすいと言っていたんです。
若い世代が未来をつくるから、若い世代の本音をちゃんと載せておきたいので、今回も初対面の5人に中国5県から集まってもらい、高校生から大学生、若手社会人で座談会をしたんですよ。初対面の5人で地域との関わり方を考えてみたら、結局地域との向き合い方は恋愛の向き合い方と似ているよね、みたいな話になって。彼らなりの感性って面白いなあと思いました。
日野:なるほど、「活性化気持ち悪い」をもうちょっと解説してもらってもいいですか?
田中:「地域活性化気持ち悪い」というのは、地域が主語になっているんですよ。「地域はこうあるべき」とか、今までの地域づくりは地域が主語だった気がします。
でもそうじゃなくて、彼らがなぜ地域と関わっているかと聞いていくと、結局個人の幸せが出発点なんですよね。その延長線上に地域の幸せもあるんですよ。
日野:そういう事ですよね。個人の幸せの集積が、地域の幸せですよね。
田中:そうそう。だから「活性化気持ち悪い」というのは、それを無視した地域が主語の在り方がよく分からないみたいなニュアンスだったと捉えています。個人から始まって地域に接続して、お互い幸せになるということですね。
私も今、地方が面白くなっているとか言っていますけど、だからと言って昔のままでいいと思ってはいなくて、課題感としてあるのはそこですよね。
まだまだ「骨をうずめる覚悟はあるのか」と言ってしまったり、個人を抑圧して地域が主語になったりするのは、今の時代違うなと。日野さんも言ってくれた、個人の幸せの集積が地域の幸せであるという地域をつくれば、若い人がどんどん来るというのがこの中国山地の取り組み見ていても思いますね。
あるもの生かしてそれぞれの本場に
田中:日野さんは外から入っていって、地域の文化とか歴史をちゃんと見て、見過ごされているものを掘っている気がするな。牡蠣もそうだし。
だから新しく特産品作ろうとしたときに、オリジナリティは足元にあるからそこにしかないものをつくるしかない。地方創生ってそういうことだと思うんですよね。それぞれの本場になるというか、足元にあるものを生かす。
日野:誰かの言葉ですけど、「ないものねだりじゃなくて、あるものいかしだよね」みたいな。
田中・七咲:うんうん。
日野:とにかく東京になりたくて、ないものをつくる。そのために日本列島改造論をやってきたわけですけど、だからこそ変なハコモノ施設とかできちゃって、大赤字をこいていると思うんです。だけど実は足元に素敵なものはたくさんあって、それの編集の仕方だとか生かし方でその地方が持てる資産のあり方は変わるというのは基本中の基本なので、それを探すということですね。
田中:そこは私も思っています。便利な方がすごいという今まで築いてきた価値観がずっとある中で、便利じゃない地方の人達というのは「なんもない地域」だと言われて、すごく傷ついてきた。でもそれは悪いわけじゃなくて、傷ついてきたからしょうがないと思っています。
そこに対して新たに「いやいや、ここすごいじゃないですか!」と言ってくれる若い世代、素直にいいと思う感性の人たちが来る。関係人口はそこに意味があるなと思いますね。
つながりがないから"しがらみ"たい
田中:つながりこそが地域の最大の資本であり、だからこそ若者とか関係人口が来ているよというのを、「つながりと地域の資源」にフューチャーした論考を書いていたりします。
日野:つながりこそすべてと書いてありますもんね。
田中:若い人が中国山地をはじめとした地方に来ている理由の1つに、地方がちゃんとまだつながりを保っているからだというのはあります。私たちから見ると「しがらみ」と言うんですけど、若い人たちはね、ちょっとぐらい「しがらみたい」というんですよ。
日野:若者が「ちょっとしがらんでみたいな」と。
田中:そう。そうやって言われるんですよ。ないものを求めるんでしょうね。人が多すぎてつながれない都会で繋がりを持てなくて、しがらんだり、つながったりするというのがないからそれが欲しいと言う。
地域の断絶とか分断が言われているからこそ、つながりこそが資源だし、それがある地方に惹かれるというのは、彼らなりの生存戦略だなと見ています。
つながりは、なんだかんだ言って地方がしがらみを大事に育ててきた結果だろうと思います。もちろん変わらんといけんとこもあるけどね。
住んでいる場所だけが地元じゃない
七咲:この創刊号の内容を決める時に「地元」というキーワードが出てきたじゃないですか。
田中:うんうん。
七咲:日野さんにとって地元ってなんですか?
日野:そうですね。地元は福岡だけど、『Qualities』を立ち上げたので、九州全体に気持ちはありますね。九州全体というのはおこがましいかもしれないですが、福岡もすごいけど、それ以上に宮崎とか長崎とか佐賀とか熊本や大分も、自然の持っている力とか食材のすさまじい旨さがすごいんですよね。
田中:なるほど、ちなみに七咲さんの地元はどこですか?
七咲:私結構狭くて、益田の中でも高津町というところが地元だと思っているし、最近はその柿の木エリア。その自分の記憶の中の懐かしい場所と、今関わっている場所の2つかな。
田中:中国山地1000キロの旅をした、森田さんが新しい地元が作られてきているという話をずっとしていて、お二人みたいにその土地に住んでいるわけではないけど、地域づくりに関わっている関係人口的な人達なんですよね。私もこれからの地方が変わらないといけない1つが、地域だけで頑張っちゃうという癖だと思います。
「住んでない人とも一緒に関わって、住んでない人にとっても新しい地元だし、住んでいる人にとっても新しい地元がどんどん中国山地にできていっている」というのが今回の創刊号の1つの柱なんですよ。誰でも地元は新しく作れるし、地域の人も地元を変えていけるんですよね。
地元へ出会いは関わることから
日野:その意図で言うと福岡も地元なんですけど、今住んでいる東京の品川区も地元感が出てきています。
七咲:結構長く住んでいるんですか?
日野:そう。10年くらい住んでいるんですけど、上京したての頃はなかったんです。きっかけは子供が小学校に入って、町内活動に参加し始めて、目黒のさんま祭りっていうのがあるんですよ。死ぬほどさんまが岩手県から送られてきて、小学校のおやじの会があって、駆り出されて1日中さんまを焼きまくるんです。
サラリーマンをやっていて家に寝るためだけに帰るとなると街に関わることがないかもしれないけど、そうやって街に関わっていくと地元に変わっていく感じはありますね。
七咲:今住んでいるエリアが渋谷区で、すごく好きなんですよ。だけど、地元という感じはしないですね。やっぱり地域の活動をやっていないからなのかな。
日野:そうだと思いますよ。さんま祭りを取り仕切っているのは、地元にずっと住んでいるおじさんたちで、いわゆる下町というか江戸弁なんですよね。「なんだこの野郎」「うるせえなぁ」とかですね。
僕らが使っているいわゆる標準的な言葉やビジネスの現場で使っている言葉ともちょっと違う、江戸なまりがあると感じた瞬間に、東京もローカルだわって思ったんですよね。それを思ったときに「ああ、江戸という、東京という地域にきているんだな」って。日本の首都としての東京ではなくて、ローカルとしての東京、ローカルとしての目黒に出会ったときにすごく愛着が湧いたんです。
自分なりのいい地域に出会う
七咲:なるほど。さっき輝美さんも仰っていた“しがらみたい”と言っていた子供たちはどこからの子たちですか? 関東?
田中:まあ全国かな。共通しているのは2つあって、1つは元々そうやってつながりがある地域に生きていて、都会に憧れて出てみたもののやっぱつながりがいいみたいなUターン系タイプ。もう1つは都会というより郊外の団地とかで育って、なかなかつながりが持てなくて、つながりたい・しがらみたいふるさと難民ってやつですね。
この前も日野さんと一緒に法政大学の「ローカルジャーナリズム論」という授業に出させてもらったんですけど、その時もやっぱり「自分の生まれたところが愛せません」みたいなコメントをもらったかな。私が言いたいのは、「生まれたところを愛せ」って言っているわけじゃなくて、自分なりの地元って今どこにでも作れるし、探せるからいい地元と出会って一緒に育ちあってほしいなってことなんですよね。でも結局いい地域との出会い方が分からないよねと日野さんと話していたんだよね。
面白い地域や情報にどう出会う?
日野:そうそう…。出会い方わからないですよね。僕の場合は「仕事」という入り口があって、声をかけていただいて入っていくから、相手の人がいろいろな人を紹介してくれる橋渡しがあります。だけど、大学生とかは両親、おじいちゃんおばあちゃんが全部東京の人で、地方への“関わりしろ”がないですよね。
田中:関心のある学生はいるけど、おもしろい地域の情報が全然届いてないよねというのが見えてきたんです。
日野:うんうん。ちゃんとその人たちに届くような発信をされている数量が圧倒的に少ないのはありますよね。
田中:そうですよね。でもせっかく地域に関心を持っている世代が増えているから、そうした人たちがきちんといい地域に出会えるような、仕掛けがもっとあったらいいなと思います。ここは地方がもうちょっと踏ん張って頑張らないとねとは思いますよね。
七咲:あと誰か1人キーパーソンというか、その地区でこの人面白いよという人が誰かいるじゃないですか。その人と繋がると一気にいろいろな人とつながりません?
日野:それが輝美さんと一緒に関係人口のことを広げていらっしゃるソトコトの編集長が仰っている「関係案内所」ですよね。関わりたい人の窓口になって、「そういうことだったら、あの人がいるよ」というように間をつなぐ、翻訳をする人はいた方がね。
田中:今ゲストハウスがみんな好きなのはそういうところだと思うんですよね。普通に旅に行って、シティホテルに泊まってもぴんと来ないというか、もっと人とつながりたいし、そのために旅に出ているからゲストハウスは最高だと思うんですよ。
安いのもあるし、オーナーの人が大体「関係案内人」になっているわけですよね。だからいきなり行って話聞けというよりは、ゲストハウスに行けという方がまだハードルが低いかもしれないですね。
(後編に続きます)

「預かったご予算を着実な効果にしてお戻しする」という強い想いとともに、何が社会を良くするのか?を考えるデザイン発想で、事業企画や商品開発から、PR、プロモーション、マスメディアでの広告などまで、幅広い経験を活かした統合プロデュースを手がける。
また「本質的な地域活性」をマイテーマに、“外から目線”で地域資産を再編集し、地域のプレイヤーの“関わりしろ”を作りながら、事業、プロジェクト、プロダクトを共創し、開発して、情報発信を行っていくことを得意とする通称”ローカルおじさん”。
2020年には九州を取材テリトリーにしたローカル発Webメディア Qualities(クオリティーズ)を企画プロデュースし、創刊編集長。観光庁や文化庁の採択事業者へのコーチングなども多数行っている。
主な受賞歴に、2度のACC TOKYO CREATIVE AWARD グランプリ(2018,2022)、グッドデザイン賞BEST100(2022)、Spikes Asia ゴールド(2019)、カンヌライオンズ ブロンズ(2013,2019)、ADFEST ゴールド(2019)など。






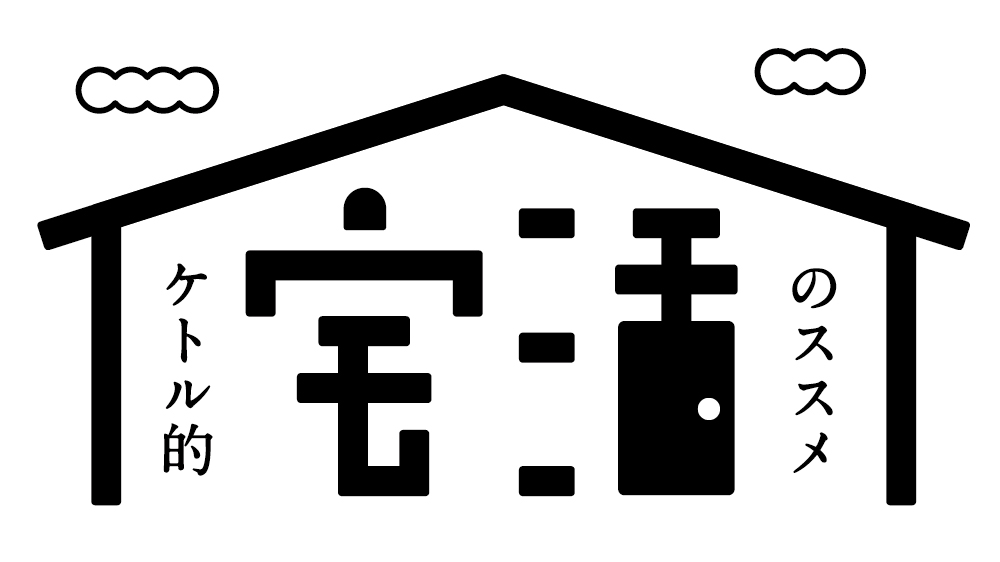



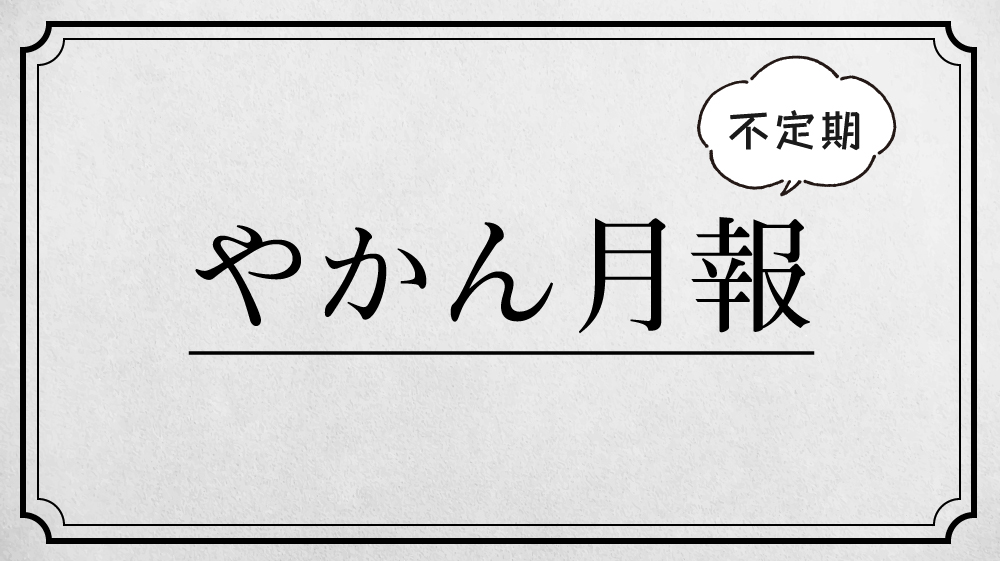












 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧
「”ローカルおじさん”の地域活性のホント 十番勝負」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター