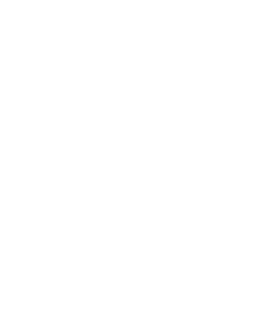2024/05/16
第20話 インドネシアで食文化について考えた。
 木村健太郎
木村健太郎
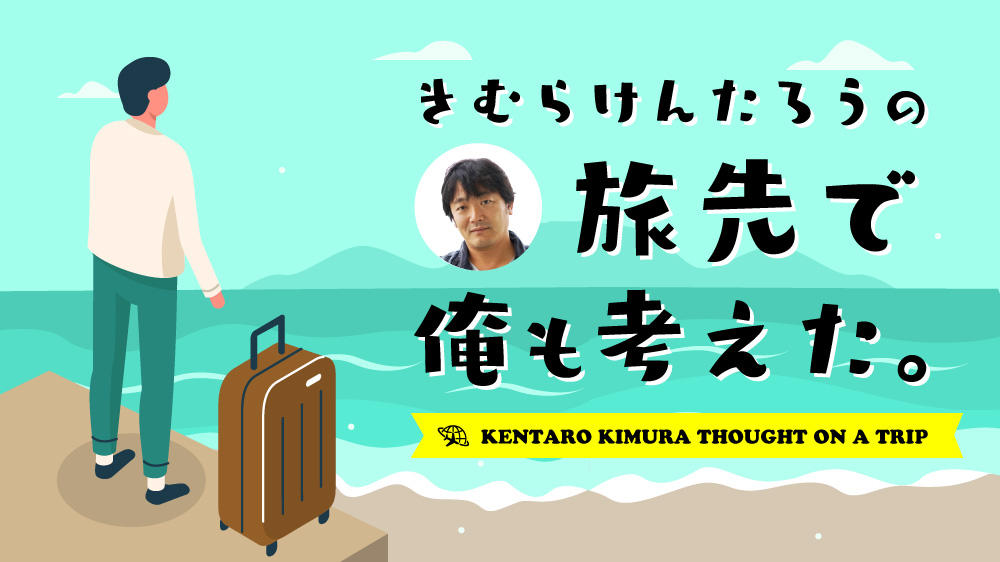
5月の初め、ゴールデンウィークにインドネシアに出張に行ってきました。
バリ・ナショナル・コンベンションセンターというところで2年に1度行われるAPMF(アジア・パシフィック・メディア・フォーラム)というカンファレンスがあります。広告賞ではないですが、参加人数の規模ではアドフェストやスパイクスアジアよりも大きい規模です。
今回はそこで最終日に登壇して、その後ジャカルタに飛んで、現地のオフィスでお仕事をしてきました。

滞在中に、インドネシア料理に加えて、現地に駐在している仲間たちに4回日本食屋さんに連れて行ってもらいました。
寿司、焼き肉、ラーメン、焼き鳥。
僕は美味しいものは大好きですが、その国のご飯を毎日おいしく食べていけるタイプの人間なので、あまり日本食が恋しくならず、こんなに日本食ばかり食べたのは珍しいです。
もちろん海外での日本食に関する楽しい思い出はいくつもあります。
中米コスタリカで食べた「ブエノスアイレスロール」というネタがなんなのか最後までわからなかった寿司。
カトマンドゥで食べたおいしいのに何かが決定的に足りないカツ丼。
バルセロナで食べた中華と和が微妙に混じった居酒屋料理など。
あるいはシンガポールのスーパーリッチたちに囲まれて食べた鉄板焼と懐石のコースや、ニューヨークでの有名な寿司屋など、「おれ自腹で日本食にこんな散財しちゃった」というマゾヒスティックな快感に浸ったネタもあります。
でもやっぱり日本食というのはレシピや調理方法だけではなく、素材や水、店内の雰囲気や食器、もっというと調理人のストイックな姿勢まで含めて日本食なんだな、そのためには日本の倍以上の金を出さなくちゃだめなんだな、というちょっと残念な気持ちで店を出た経験もたくさんありました。
実はここインドネシアでも過去に日本食レストランでがっかりした記憶があります。
しかし、今回連れて行ってもらった寿司屋、焼き肉屋、ラーメン屋、焼き鳥屋は、どれも感動的に美味かった。しかも値段もリーズナブルで、日本と一緒か少し安いくらいで、メニューの数も豊富。インドネシア人の店員さんも笑顔で「いらっしゃいませ」と日本の和食屋さんと同じサービスを提供してくれていて、ちゃんと日本食のよさを理解してくれているのを感じました。

現地の日本の食材を扱うスーパーにも行きましたが、日本と変わらない品揃えだし、現地の工場で生産しているものも多いらしく価格もリーズナブルです。
駐在員のお土産に、東京のスーパーでいろいろ日本の食材を買っていったのですが、そのほとんどそこに売っていました(笑)。



この変化、世界のいろいろな国で感じます。ここ数年の日本食ブームを経て、「日本食風」が多かった国に「本物の日本食」が定着した理由は、食材の物流のしくみの進化や、日本の料理人や事業者の海外進出と努力に加え、海外から多くの人が日本を訪れるようになって本物の日本食の味を知ったのも大きいと思います。
このようにして、海外において、エキゾチックなローカルフードだった日本食が、グローバルフードカルチャーとして確立してきたのだと思います。
ところで今回APMFで話した講演の冒頭は、若い頃インド人の知人に聞いたこんな食文化の話から始まります。
「世界中どこにいっても、ワインや寿司やハンバーガーがありますよね。
いまやこの3つはグローバルな食文化になりました。
でもなぜそうなったのでしょうか。
それはずっと現地の人々に愛されて続けているからなのです。
フランス人はワインをこよなく愛するし、日本には寿司職人が10万人ほどいて寿司を愛するお客さんのために技を磨いてるし、アメリカに行くとどんな街にもその街の人に愛され続けるハンバーガーショップがある。
すべてのグローバルカルチャーと呼ばれているものは、はじめからグローバルとして生まれるのではありません。
ローカルに深く根ざして愛され続けていることで、その愛が世界中に広がっていくのです。」

今回は、講演で自分が話した内容を、街で現実に舌で体感することができました。
インドネシアで、寿司、焼き肉、ラーメン、焼き鳥をもっと愛せるようになった気がします。








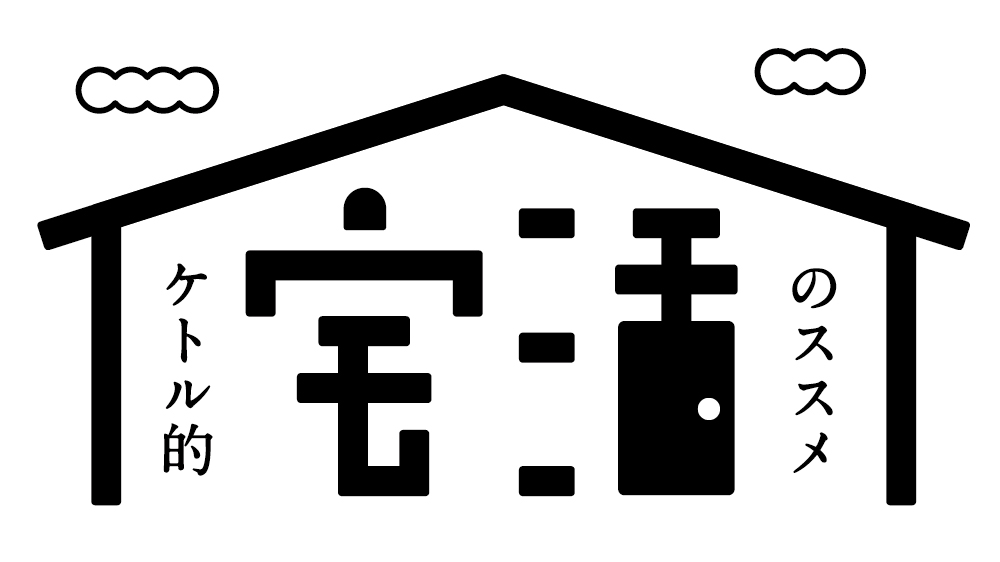

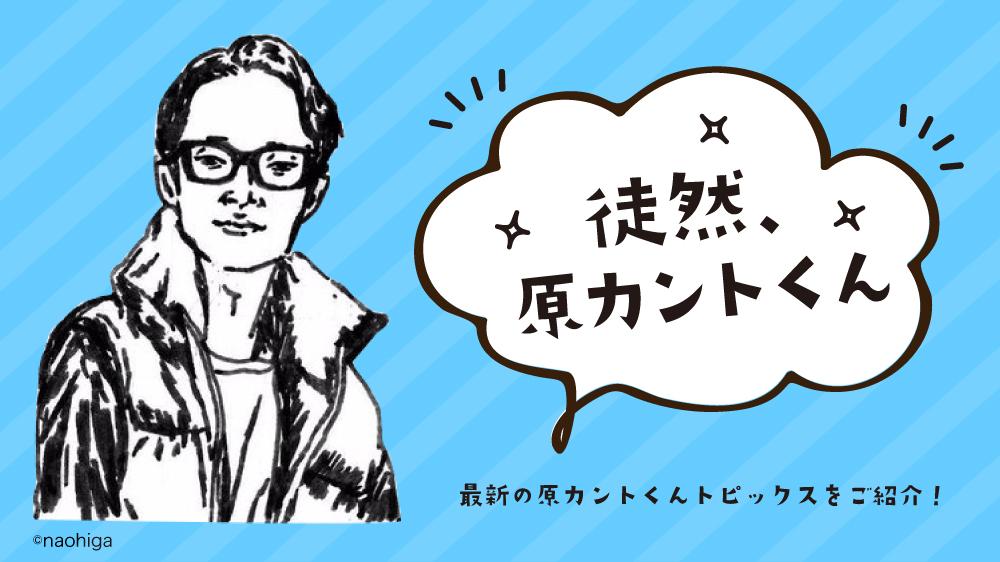

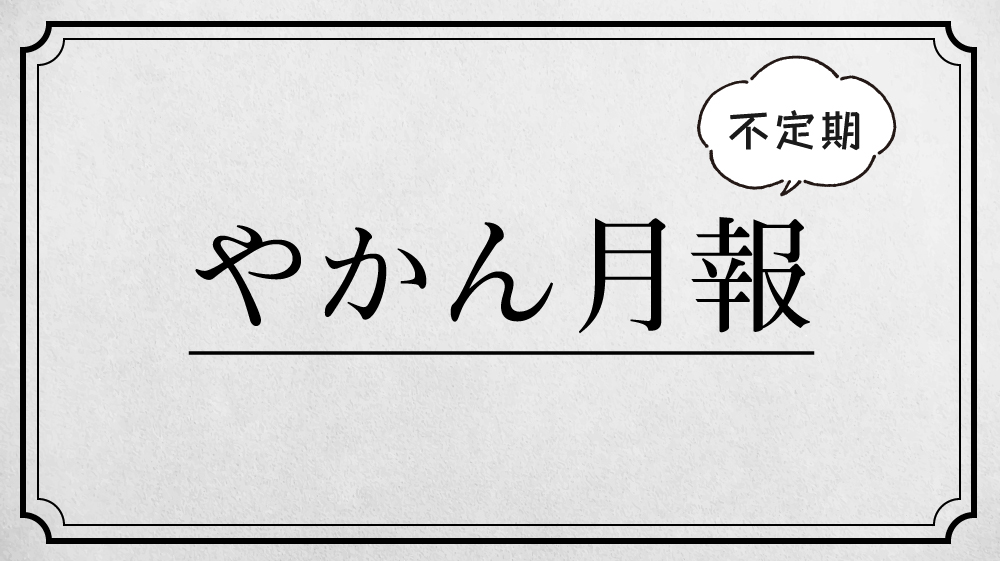
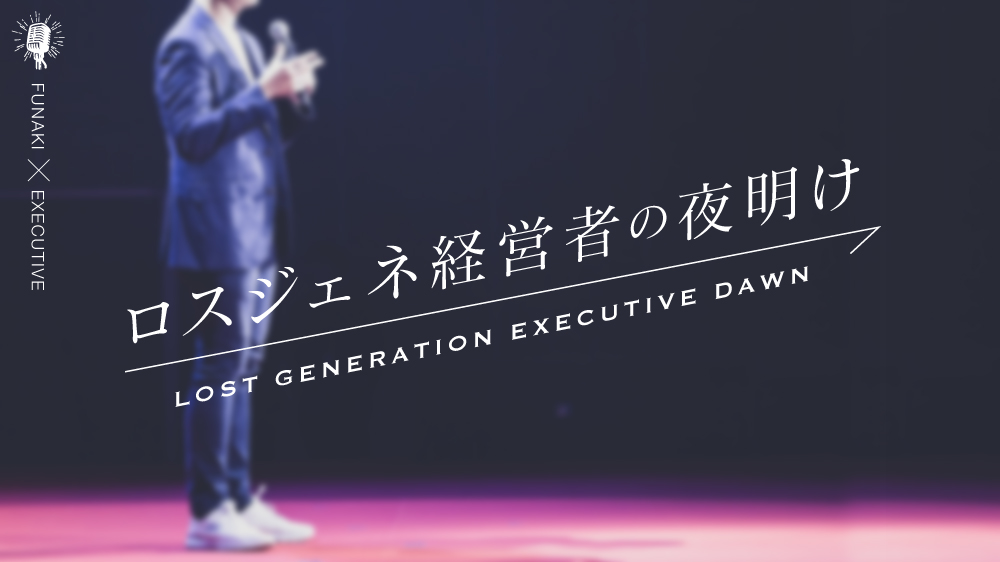

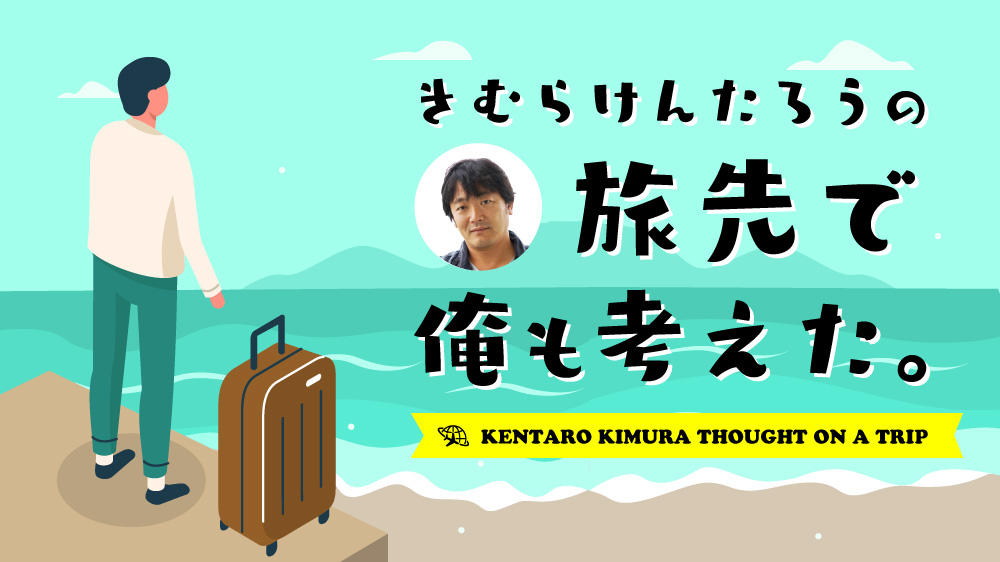

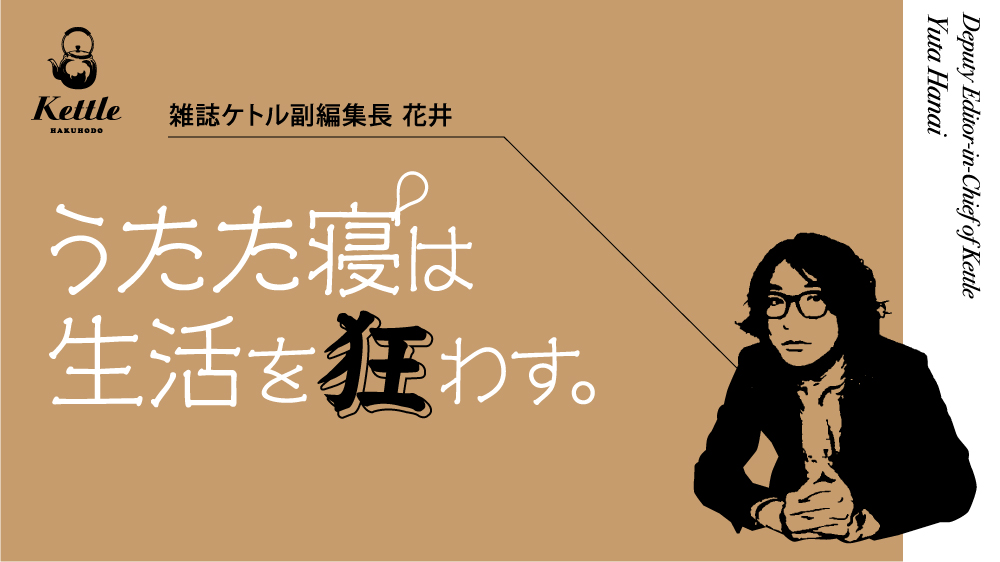






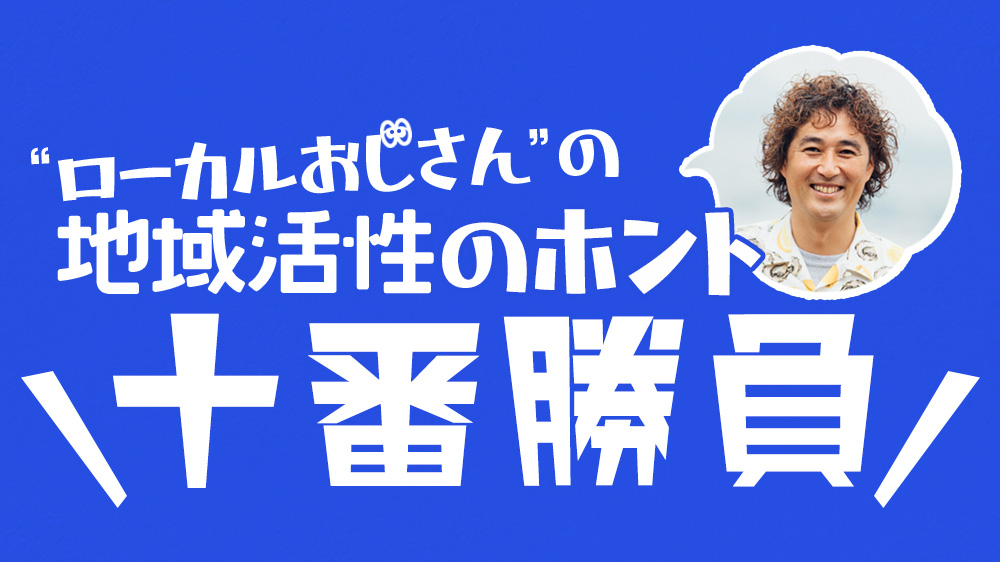
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ 「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧
「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター