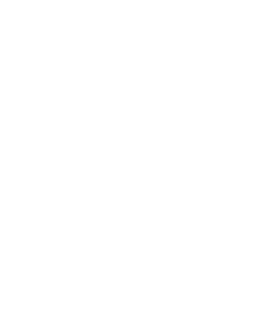2019/12/17
第2話 ニューヨークで、働き方について考えた。
 木村健太郎
木村健太郎
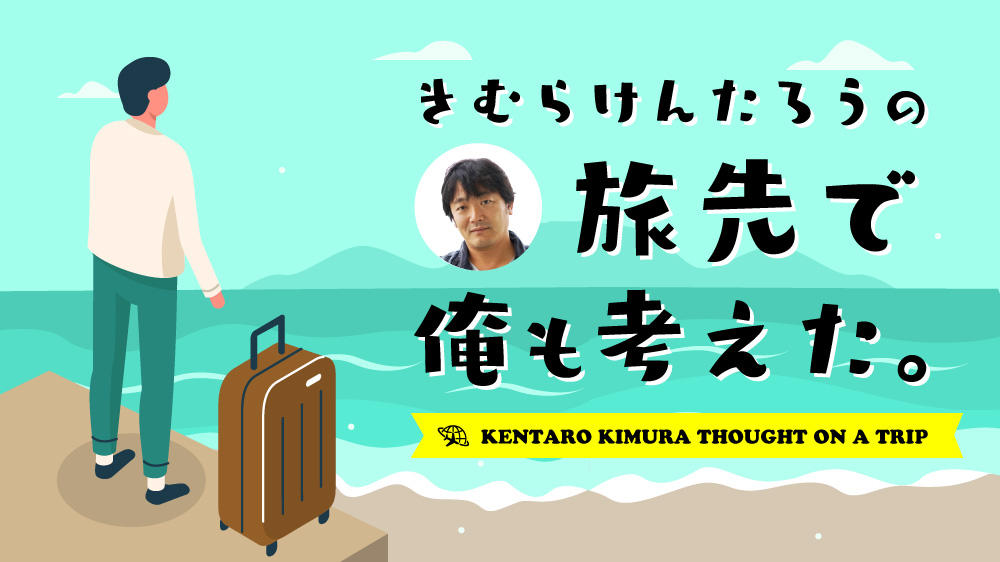
ニューヨークにあるグループエージェンシーの仲間たちと、あるプロジェクトの仕事をした時のことです。
東京とニューヨークでダブルでクリエイティブディレクターとストラテジーヘッドを立てて合同チームを編成し、僕が日本側のCDを、ケトルの伊藤源太がストラテジーのヘッドをやることにしました。とてもタイトなスケジュールだったのですが、何回かビデオ会議をしたのち、ニューヨークに飛びました。
現地では、プロジェクトマネージャーの人が、今日は午後2時までにストラテジーの方向を決めて、5時までにクリエイティブの方向を決めます、というように、かなり細かいアジェンダとスケジュールをひいていました。
実際に、1時半くらいになると、「はい、そろそろストラテジーをまとめてください」と急かされる。まだもうちょっと考えたいのに。そして2時には強制終了して休憩。
そのあと、その戦略に基づいて、クリエイティブのブレスト開始。同じように、もっとじっくり粘りたいと思っても4時半くらいにまとめにかかって、5時には強制的に終わる。ちょっと欲求不満だけど、「広げる脳」のスイッチを切って「まとめる脳」のスイッチを入れると、企画はすごいスピードで成立するものです。

その時間にはアートチームとプロダクションチームの人が待機していて、今生まれたアイデアを形にしていきます。結構そこでジャンプして素晴らしいアイデアになったりすることもあるのです。
6時には、ほぼ全員仕事が終わります。会議室にビールが出てきてポンポン栓を抜いて飲みはじめる。一本飲んだら、チームみんなで歩いて行けるバーに行きます。つまみは一品くらいしか頼まないでビールとかワインとか。もちろん仕事の話はもうしません。
で、8時前には解散して、ご飯はそれぞれ。家族で食べる人も、デートする人も、会食の人も、みんなで食べに行く人も。日本だと、プレゼン前だと、弁当をとって食べるか、打ち合わせが終わった後にみんなで深夜の焼肉とか行っちゃいますよね。でも、ニューヨークのこの感じ、いいなあって思ったのです。

広告会社の特にキャンペーン構築業務において、6時に終われない最大の理由は、仕事量が多いことに加えて、時間ギリギリまで粘ってしまうことにつきると思います。
今のアイデアに自信が持てなかったり、心配だからもう一案用意しようと思ったり、ラフやビデオコンテの完成度を必要以上に高めてしまったりすることもありますが、基本は「もっといいアイデアを探そう、もっといいものにしよう」というクリエイティブワークにとってポジティブな欲求です。ですから、全体を俯瞰して、時にはそのポジティブな意欲に水を差してパチっと脳のスイッチを切り替える役目の人が必要で、その人に時間管理においてはCD以上の権限がなければいけないのです。
俳優には監督が必要だし、アスリートにはコーチが必要です。同じようにクリエイターやプランナーにはプロジェクトマネージャーが必要なのだと思います。
つまり、夢中になって集中する人と、全体を俯瞰する人は、別の人である方が上手くいく。この、頭ではわかってるつもりだったことを、ニューヨークでは身体で痛感したわけです。
欧米の会社には、責任と権限を明解にして役割分担をするというシステムとカルチャーがあります。専門性を持った人に権限を委譲することで、意思決定のスピードを上げることができるのです。そのために、日本のような「チームのためならなんでもやります」的なメンバーシップ型雇用でなく、「私の仕事はここからここまで」的なジョブ型雇用がベースになっているのです。
このテーマ、ケトラーが全員集まる「やかんみがき」で議論したことがあります。
ケトルはそもそも、当時の広告業界における縦割りの分業システムを否定して、「ひとりのCDが全領域を見る」という統合コンセプトでやってきた会社です。いわば、ニューヨークと正反対のベクトルを突き進んできたクリエイティブエージェンシーです。
でも、いまはもしかしたら「統合」から「分業」にふりこをもどすべき時期なのではないか。結論はありませんでしたが、みんなでそんな議論をした記憶があります。
働き方改革という言葉が現れて数年経ちますが、問題の本質は先進国の中で低いと言われる日本企業の生産性をどう向上するかということだと思います。
生産性向上のキーには、ひとりひとりの意識改革や、テクノロジー活用で解決できる部分もあれば、雇用形態を変えないと解決しない部分もあると思うけれど、エージェンシーでまず進めるべきことは、「夢中と俯瞰の役割分担」なのではないか、と思いました。







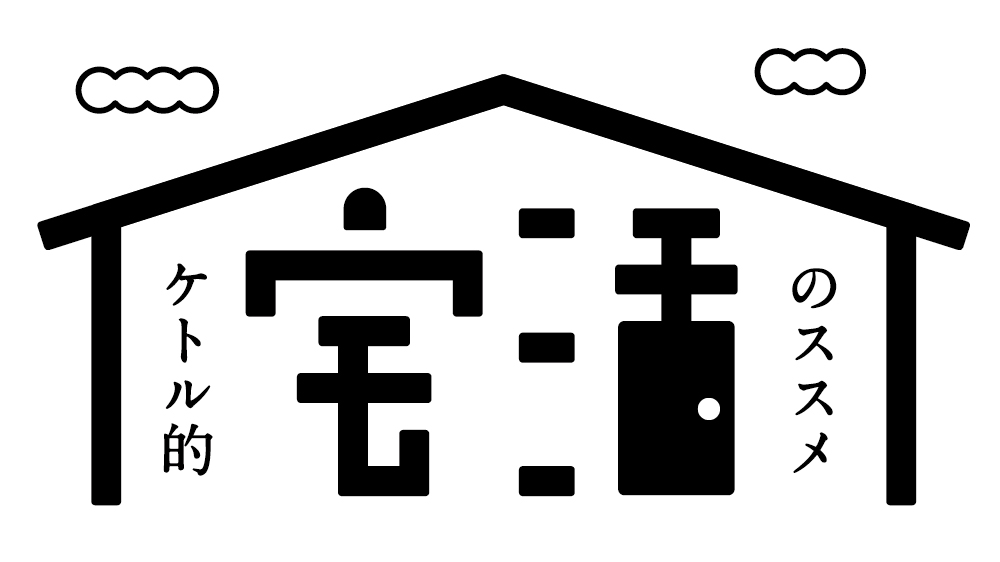

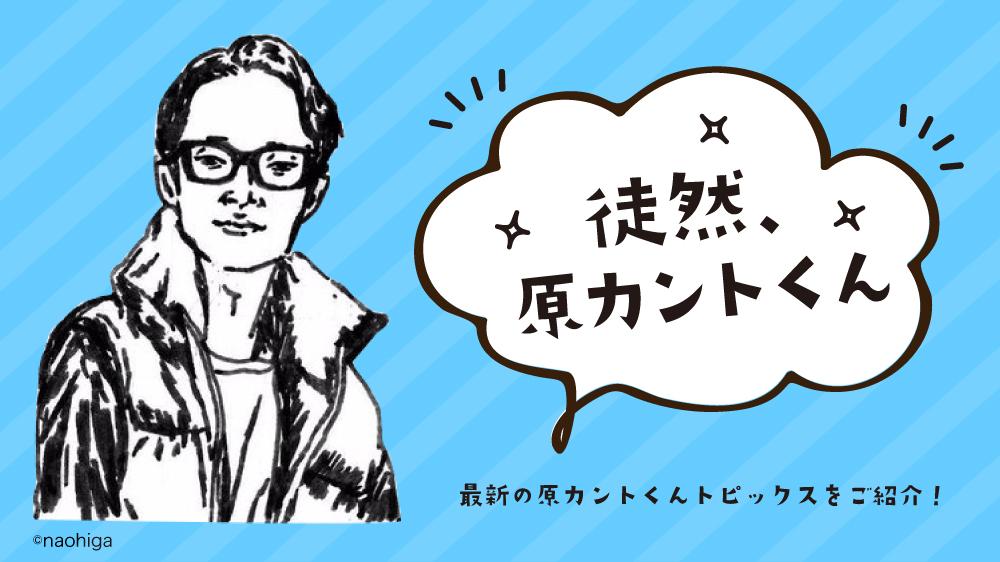

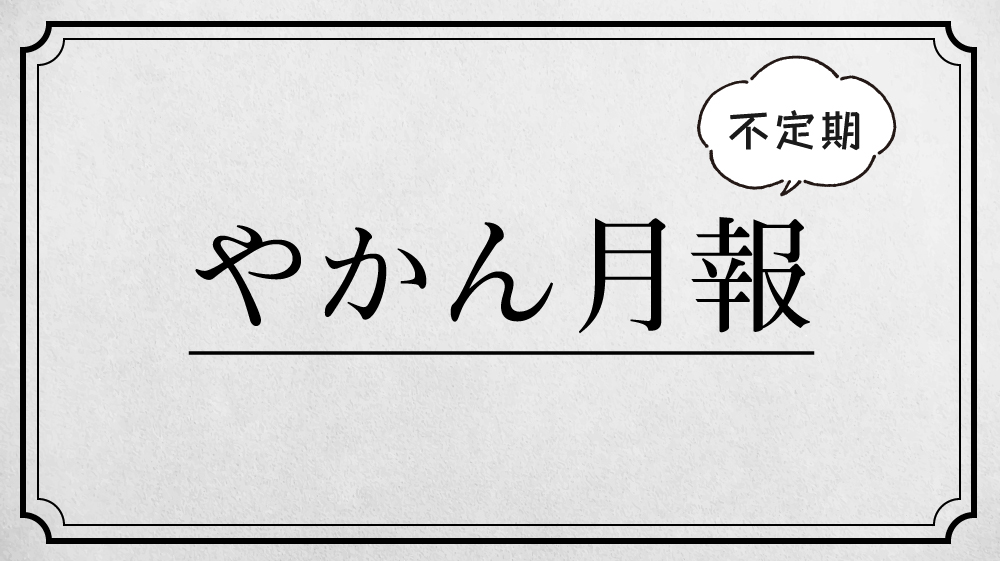
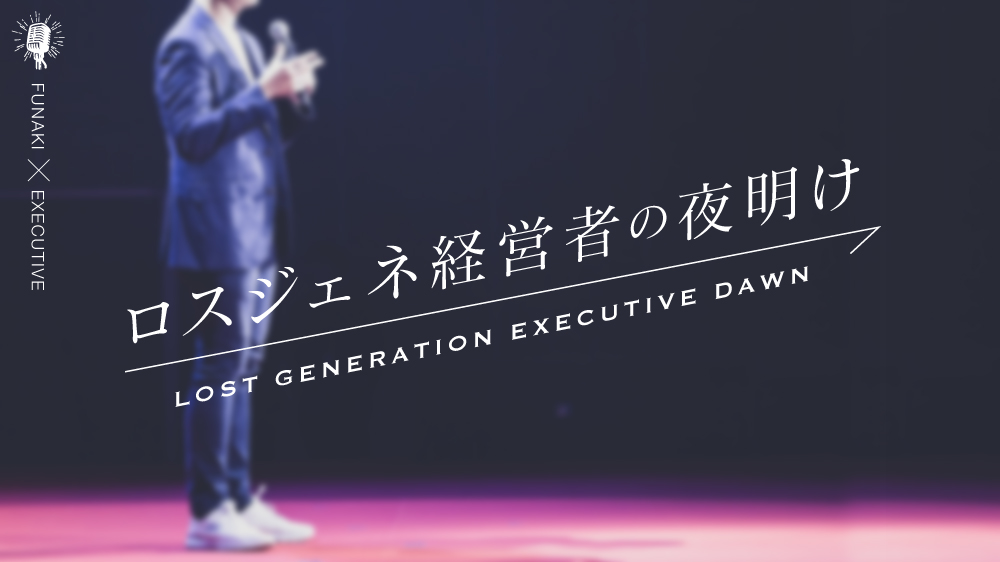

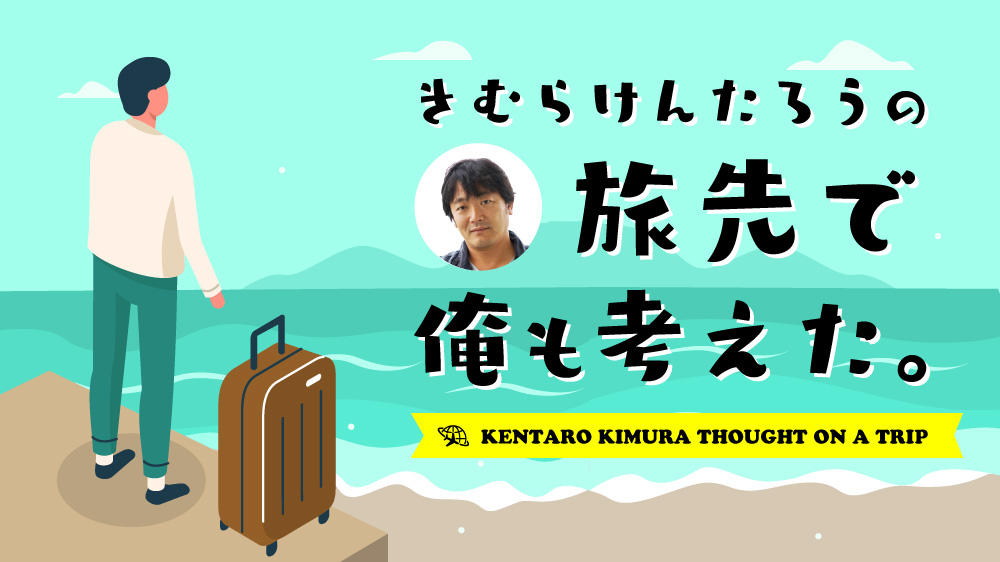

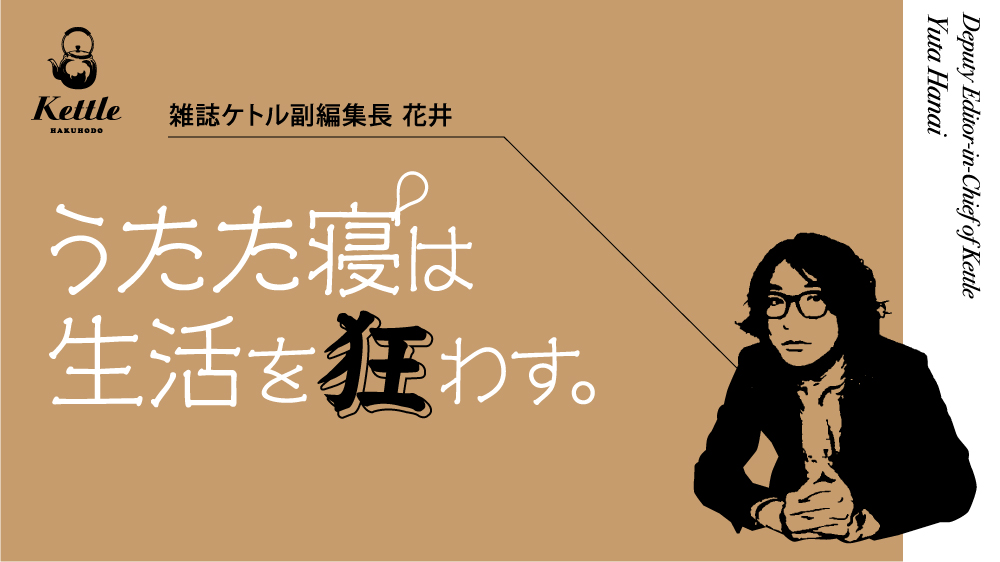






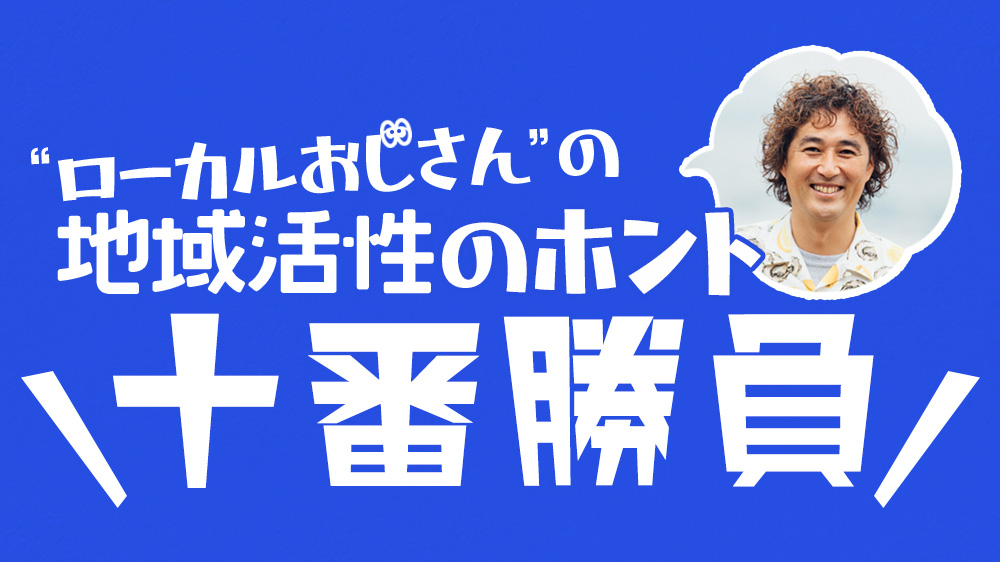
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧
「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター