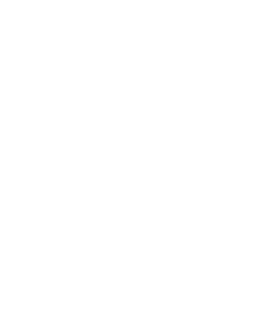2020/01/23
第6話 ボストンで、記憶と感情について考えた。
 木村健太郎
木村健太郎
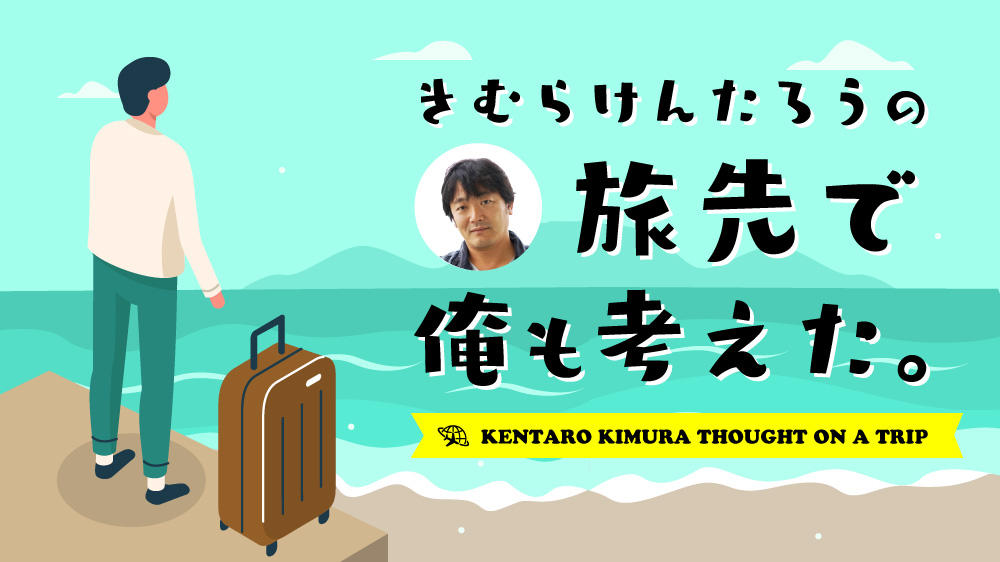
昨年夏、ボストンのバブソン大学というところで、ハーバードビジネススクールの教授たちの授業を受けるという機会に恵まれました。

行く前に日本で20冊近い分厚いケーススタディを読み込んで課題に答えなくてはならず、英語で高等教育を受けたことのない僕にとっては受験勉強並みの苦行でした。
でもその甲斐あって、ボストンでは刺激的な毎日を過ごすことができました。
5人の教授がかわるがわるやってきて、インタラクティブなディスカッション形式の授業をします。テーマは、マーケティングやトランスフォーメーションから、マネジメントやリーダーシップまで様々。昔、Eテレに「サンデル先生のハーバード白熱教室」という番組がありましたが、まさにあんな感じでした。
毎日楽しかったしとっても長く感じました。
この歳になって自分の考える枠がググッと広がるなんて経験はなかなかありません。
日本でもこのようなビジネススクール形式の講義は何度も受けたことあるけど、なんか特別な体験でした。
なんでだろう?
ハーバードの教授たちは、みんなキャラが立っていて、教授であるだけでなく、エンターテーナーで、コメディアンで、そしてストーリーテラーなのです。
3分に1回くらい笑わせてくれるし、叫んだり、走ったり、とにかく僕らを引き込んでくれます。僕らがどんな退屈な発言をしても、しっかり笑いに持っていってくれます。コスプレする教授や、コントみたいなことをする教授もいました。
でも単に笑かしてくれるというだけではありません。
ある授業では、鼻をすする音が聞こえてきました。気づけば自分のほほにも涙がつたっていました。
またある授業では、上司と部下に分かれて、上司が言いにくい不条理なことを部下に伝えるロールプレイで部下役をやったときは、思わず怒りがこみ上げてきました。
めちゃくちゃ難しい質問が飛んできて困り果てることもありました。たとえば「視野の狭いマネージャーに、そのことに気づかせるシンプルな質問を考えよ」とか。
笑う。泣く。怒る。困る。感動する。
そういった感情を揺さぶられる仕組みが授業に組み込まれているのです。

教授が「一番大切なのは、議論をどれだけ自分のこととして感じられるかだ」と言っていました。
他人事としてケースを評論したり分析するのではなく、自分ごととしてケースの主人公になれということです。
覚えたり、考えたりするのも、感情的に体験したほうがいい、ということです。
自転車は、何度も転んで、「痛い!」思いをしないとなかなか乗れるようにならないのと同じことですね。
実は、クリエイティブディレクションも、何回か痛い思いをしないと身につかないものだと思います。
感情は、企業経営にも大きな力を及ぼします。
マネジメントを、課題解決として捉えるのか、それとも人間の問題として捉えるのか、ということに迫る授業もありました。
「変革を達成しなかったら辞職する」と言って経営の目標を立てるCEOのケースもありました。
このように、感情の力を巻き込んで、より大きな影響力を行使することを「エモーショナル・コミットメント」と言います。
昨年のカンヌライオンズで、僕と一緒にセミナーに登壇したクリスティーナという脳科学者はこう言っていました。
「人間にとって“考える”といういうことは、猫にとっての“泳ぐ”ことに近い。
考えることは、できるけれど、なるべくやりたくないことなのだ。
人間とはロジカルではなくエモーショナルな生き物であり、我々の脳は考えるためというより感じるためのものとしてできている。
そして、ポジティブな感情だけでなく、悲しみ、怒り、失望といったネガティブな感情も行動誘発に効果的なのだ」

思考は、感情移入で深くなる。
記憶は、喜怒哀楽とともに刻み込まれる。
学習は、身体感覚とセットでやるのが効果的。
覚えたことや考えたこと以上に、自分の心の中に湧き起こるドラマが、僕のボストンでの最大の収穫でした。
様々な感情を味わえば味わうほど、人生を長く感じて生きることができると改めて思いました。
そんなことを経験したボストン、そろそろ2年目の準備を始めなくっちゃ。







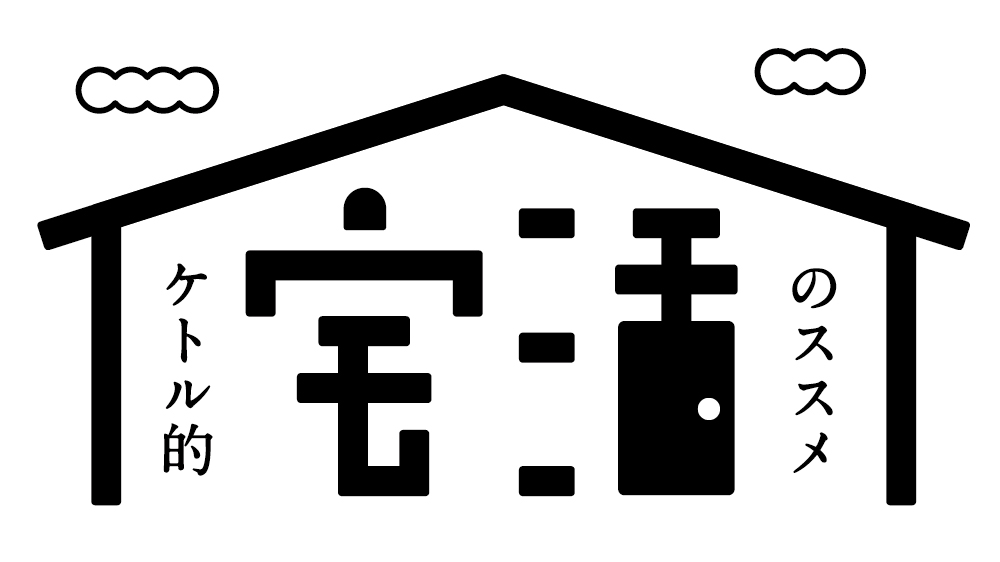

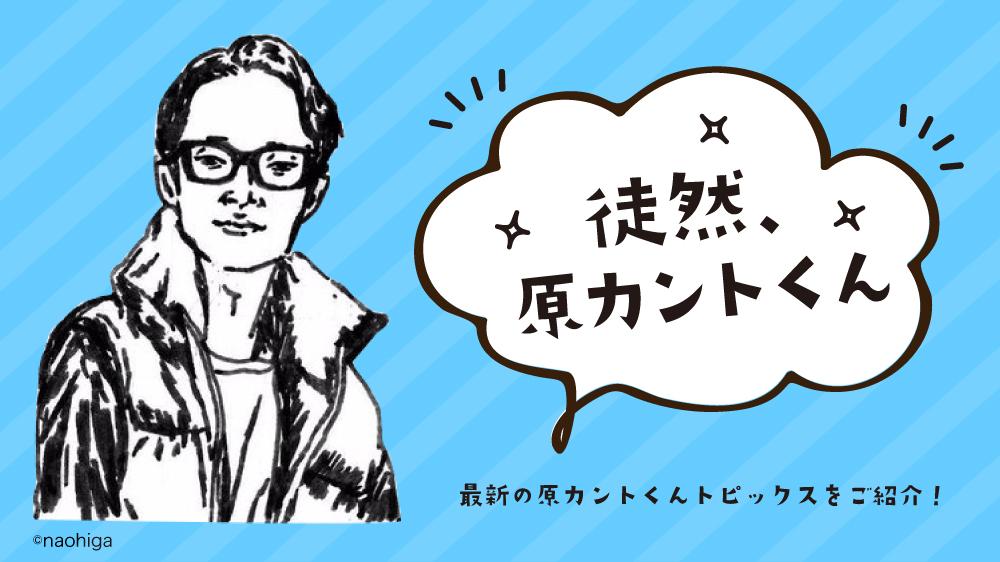

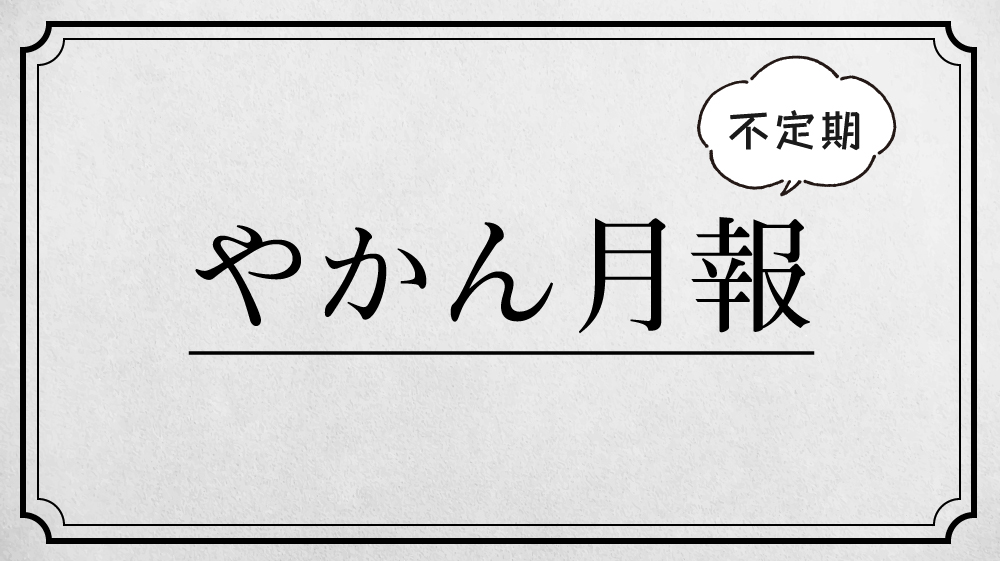
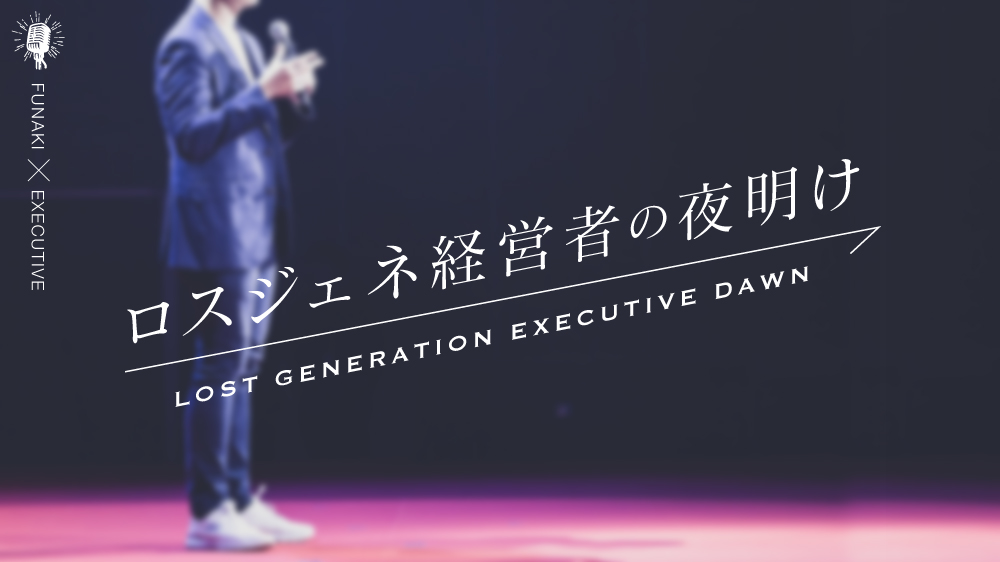

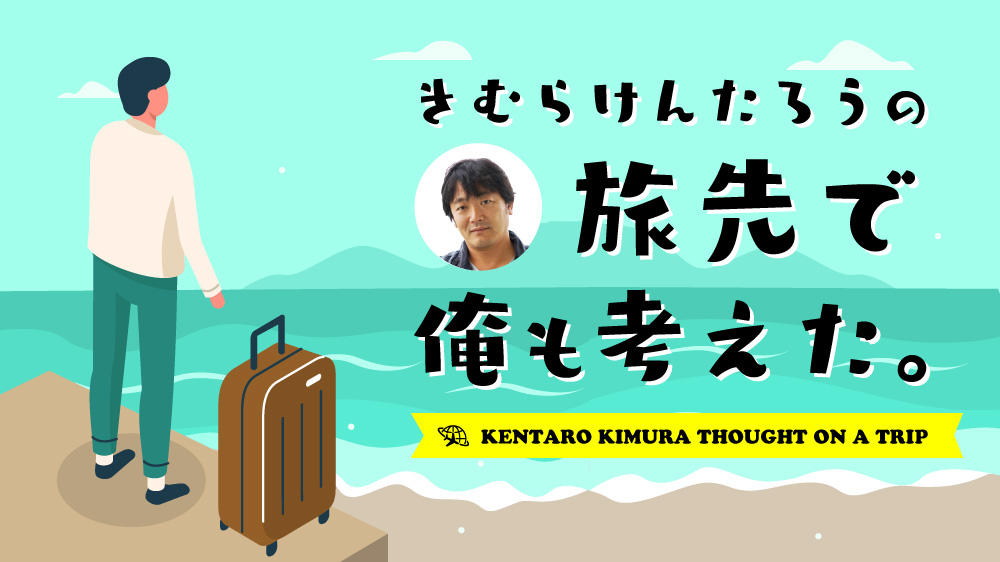

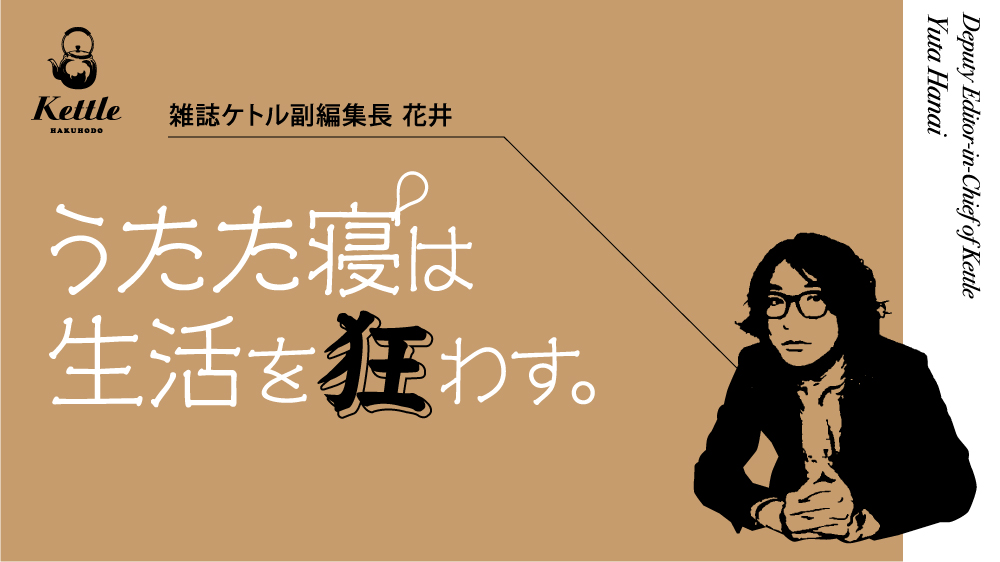






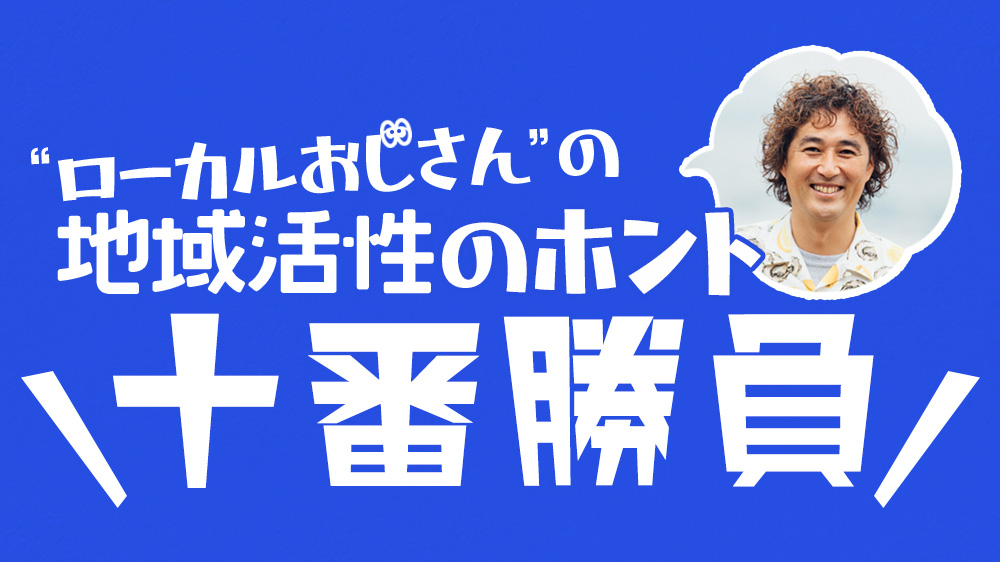
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧
「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター