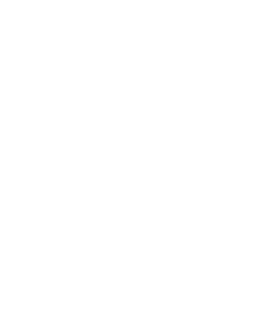2020/05/08
第10話 インドのリシケシで、パーパスについて考えた
 木村健太郎
木村健太郎
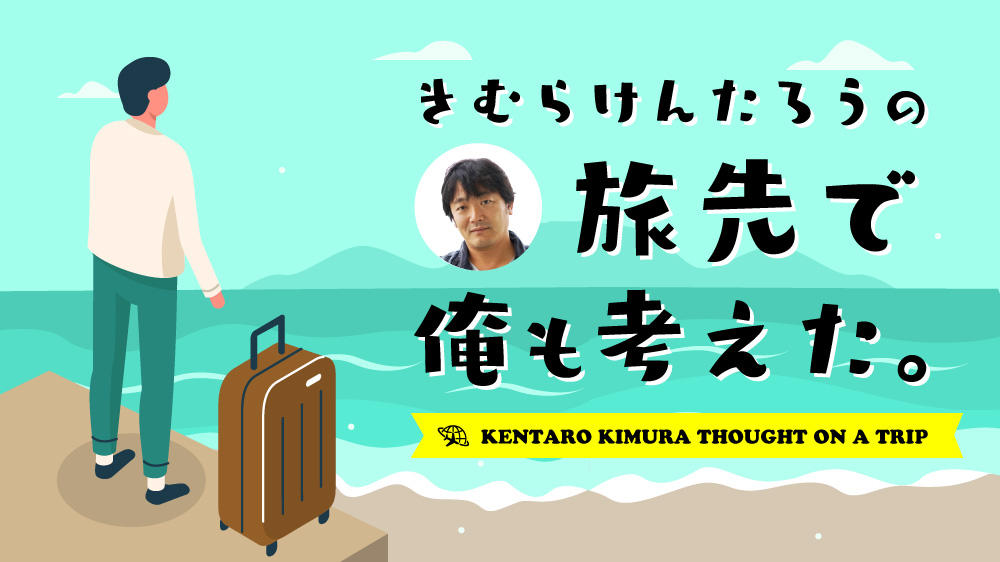
《インドのガンジス川が、新型コロナウィルス騒動によって、見たことのないくらい透明な清流になっている》ーーそんなニュースが、リシケシという街からSNSで流れてきています。
このリシケシという街、ヒマラヤのふもとにあるヨガの聖地です。1968年にビートルズが滞在してTMという瞑想法を学んだことでも有名ですね。
ガンジス川にかかる吊り橋を渡ったら、肉も魚も酒もタバコもクルマもない修行環境。僕はそこで、川のほとりにあるヨガのアシュラムに滞在していたことがあります。
アシュラムというのは、ヒンドゥー教の修行道場です。1回目は学生の時に3週間くらい、2回目は社会人になってから数日間。

朝起きたら、6時半に集まってマントラを唱えて瞑想します。そして、午前中はスワミ(先生)による授業。昼は自由時間で、散歩したり、河原でぼーっとしたり、本を読んだり。当時の僕は哲学や精神世界の本を読み漁って、「俺は何がしたいんだろう。何のために生きてるんだろう。」とか暗ーく考えたりしてました。
ここでは誰かに会うと、名前を紹介した後の次にすぐに修行や悟りの話になります。で、夕方からまたお堂に集まって、「ハタヨガ」と呼ばれる、いわゆる身体を動かすヨガをみっちりしたあと、座禅を組んで瞑想。自分の内面ととことん向き合う精神世界どっぷりな毎日です。

瞑想の話は、また別の機会にするとして、僕は、このお堂で行われる午前中の授業が好きでした。
ヨガや瞑想の知識や技術についてだけでなく、ヒンドゥー的な世界の捉え方や精神と肉体の構造についても話してくれます。当時のノートを見ると、ユニークな話がたくさん書いてあります。
たとえば、ここでは、人にはそれぞれ役割が割り振られているほうがいいのだと教えられます。全ての人間には、なんらかの存在する意義と果たすべき目的があるからです。
英語でいうと、パーパスですね。
でも、それを自分で認識するのは難しい。だから役割は誰かに規定してもらったほうがいい。そうでないとぼんやりした人生を過ごしてしまうことになりがち。その与えられた役割をしっかりこなすと、次の人生でドラクエのようにレベルアップできる。
それが輪廻というしくみです。
批判されることの多いカースト制度というのも、もともとは上下の序列を決めるためのものではなく、自分の人生の役割を決めるためのしくみだった、とスワミは説明していました。
このアシュラムには、世界各国から様々な人が来ていました。バックパッカーや精神世界好きから、会社の経営者やコンサルタント、ヨガの先生やアーティスト、お坊さんやニューエイジの人まで。なので、時々スワミの授業の質疑応答が議論になって白熱することがありました。ちょっとしたビジネススクールの授業みたいです。でも、どんな質問にもスワミは毅然として理路整然と答えていたのが印象的です。

ある朝、イスラエル人とドイツ人が、あるテーマについてスワミに議論を挑みました。
ところが話が若干宗教的なスタンスの違いにフォーカスしてしまったため、お互い一歩も譲れない状況になってしまい、議論は対立して平行線のまま。その時、スワミは両者の「違い」でなく「同じ」に焦点を当てて、こんな話で、我々生意気な生徒たちをうならせたのを覚えています。
「じゃあ君たち、想像してみてほしい。
私たちは今、エベレストに登っているとしよう。
あなたは山の南側から、あなたは西側から、そして私は山の東側の登り口から登っている。
3人とも同じ山頂を目指している。
でも、他の人が登っている反対側の登山道は見えないよね。
山頂に着いたときに、3人とも同じ山に登っていたことに初めて気づくのだ。
宗教の違いとはそういうものなんだ。
世界には様々な宗教があり、それぞれが自分たちの信じる道が正しいと信じている。
相手の道は見えないから、対立や紛争も起きてしまう。
しかし、どの宗教も実は同じ山頂を目指しているのだよ。
目指している山頂とは、幸せであり、愛と平和であり、悟り。
登り口と登り方が違うだけ。
今みんながここで学んでいるヒンドゥーのヨガは、
実はイスラムのスーフィーや、仏教の密教と、悟りへの近道という意味では同じなんだよ。
さあ、あなたたちも、私のように修行を積みなさい。
山頂からの眺めは素晴らしいですよ」

僕はこれまで、様々な企業や商品のミッション策定やブランドパーパスのお仕事をさせていただいてきました。
でも、ベースになる考え方は、今でもこのシンプルな「エベレスト理論」です。僕は、どんなブランドにも、必ず世の中に果たしている役割があり、存在意義があると考えています。そして、どんなブランドも「豊かで幸せな社会を作る」という共通の山頂に向かって歩んでいると思うのです。
ゴールは同じ。違うのはその登り口。
それぞれのブランドには、それぞれの信じる道があり、それが与えられた役割なのです。そのブランドは、何を増やすことによって、社会に貢献するのか。創造性なのか、勇気なのか、安全なのか、健康なのか、機会なのか、情報なのか、会話なのか、感動なのか……。
僕は、それがそのブランドや企業が存在する理由、つまりパーパスだと捉えています。そしてそれは、その製品やサービスが世の中に提供している価値の延長線上にあるはずです。
パーパスは、よくソーシャルグッドと混同されますが、単なる社会貢献ではありません。その企業の本業の延長線上になければいけません。そこにブランドが提供している製品やサービスを超えた、社会的な存在意義があるのです。
僕がリシケシにいた頃は、ブランドパーパスなんて言葉はありませんでしたが、僕が習ったヨガの思想には現代のパーパス経営にちょっとだけ通じるものがあったのかもしれないなあ、と思います。
コロナ騒動が終わったら、透明なガンジス川の辺りで瞑想しに、またリシケシに行きたいです。







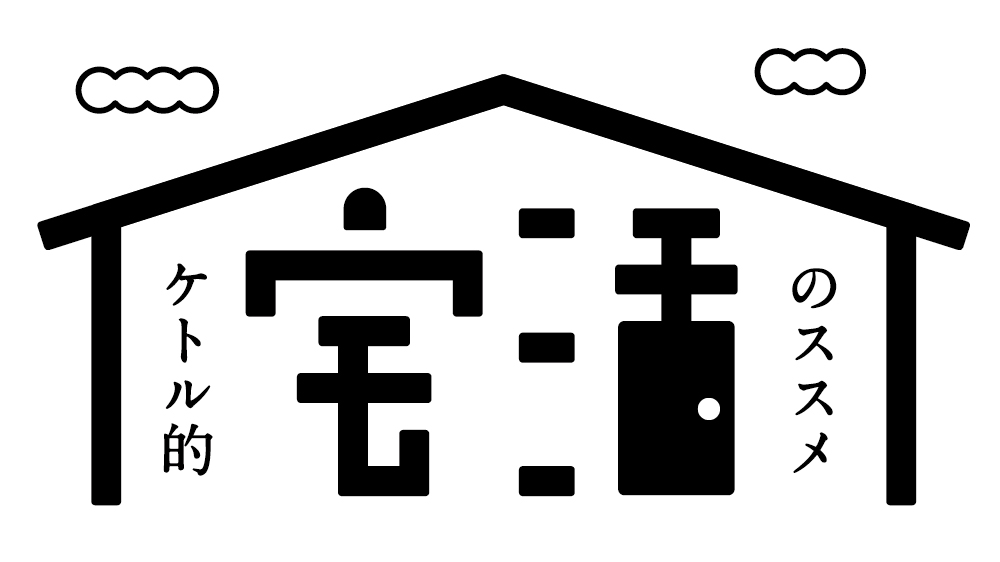

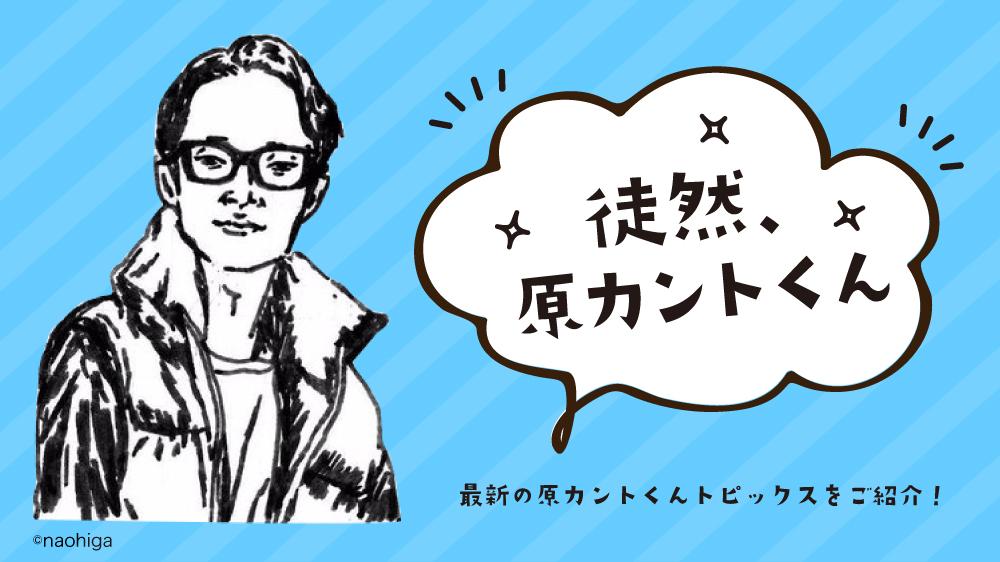

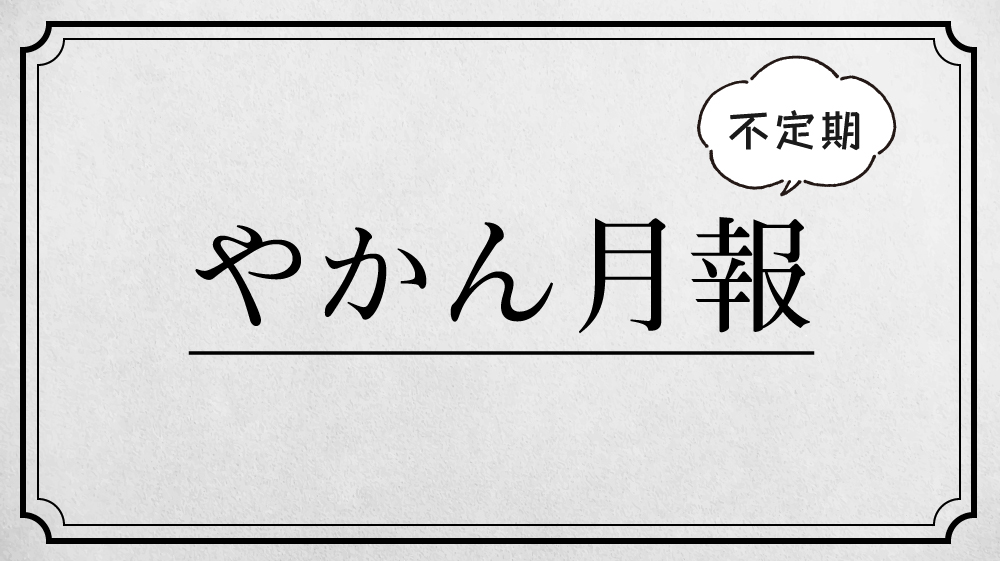
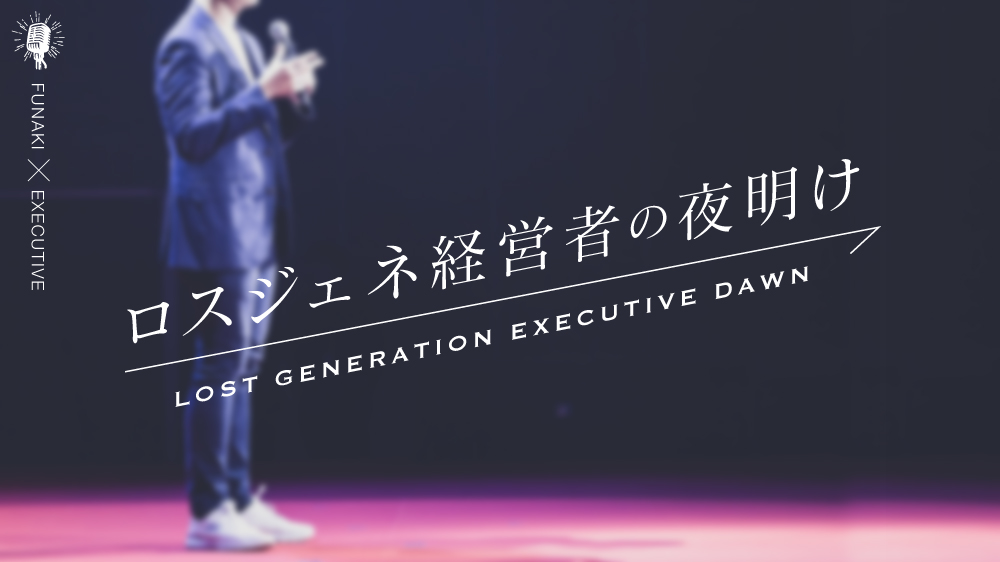

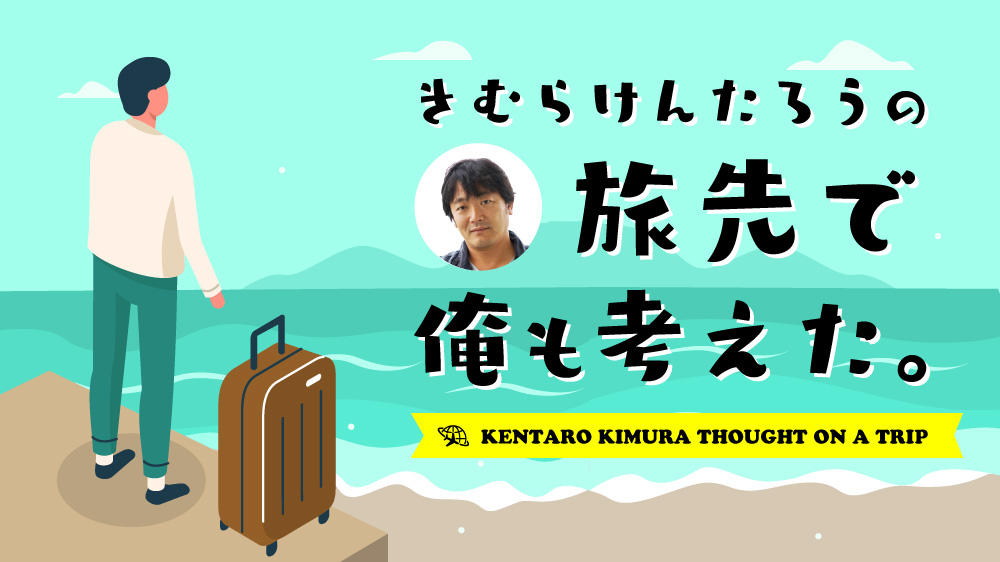

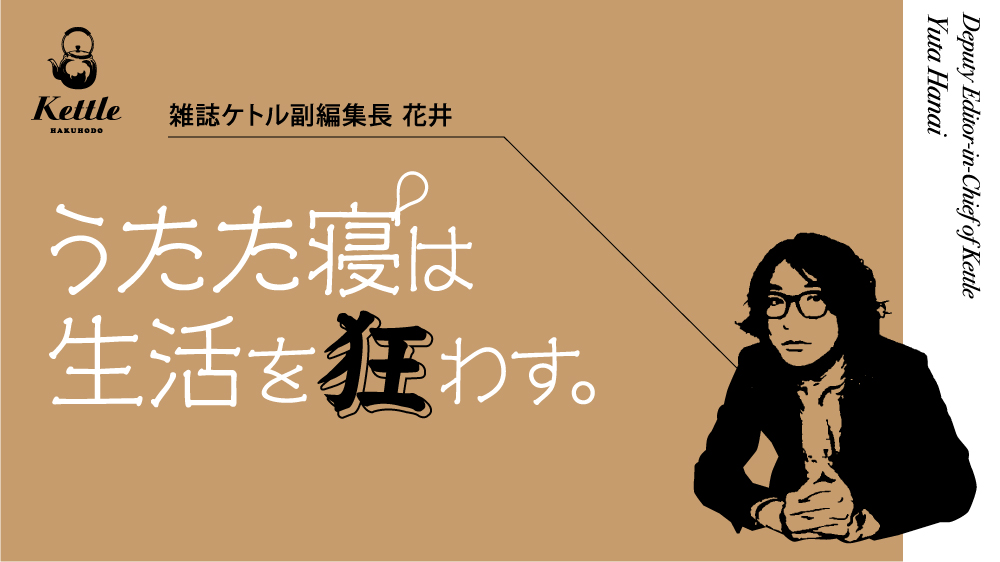






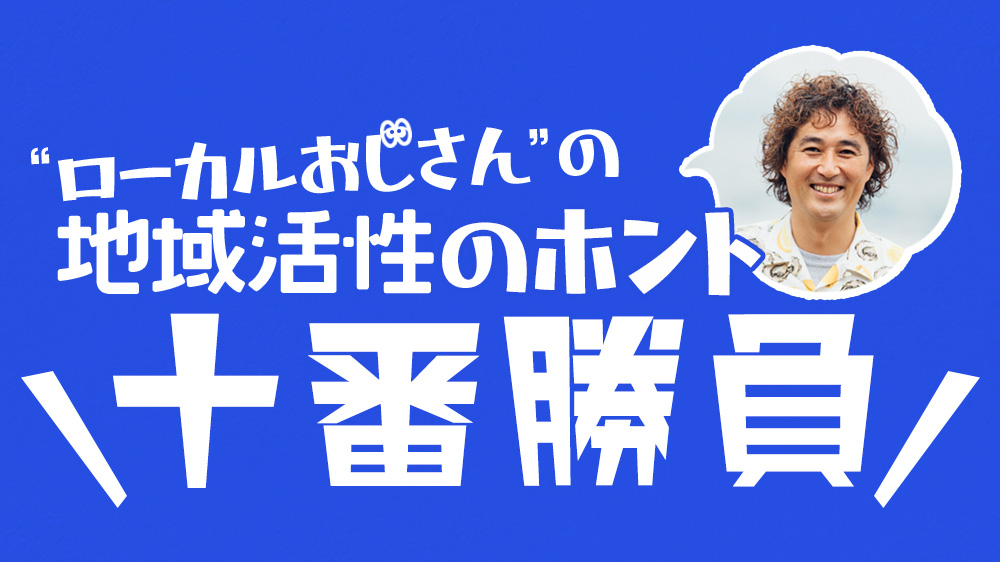
 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター 閉じる
閉じる 記事一覧
記事一覧 前の記事へ
前の記事へ
 「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧
「きむらけんたろうの旅先で俺も考えた。」記事一覧 公式Facebook
公式Facebook 公式ツイッター
公式ツイッター